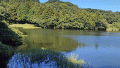冠婚葬祭の文化は地域によって様々ですが、その中でも沖縄には特徴的な葬儀文化があります。本州の一般的なお墓に比べて、沖縄のお墓はまるで小さな家のような外観。この背景には、かつて沖縄でおこなわれていた「風葬」という独特の葬儀文化が関係しています。
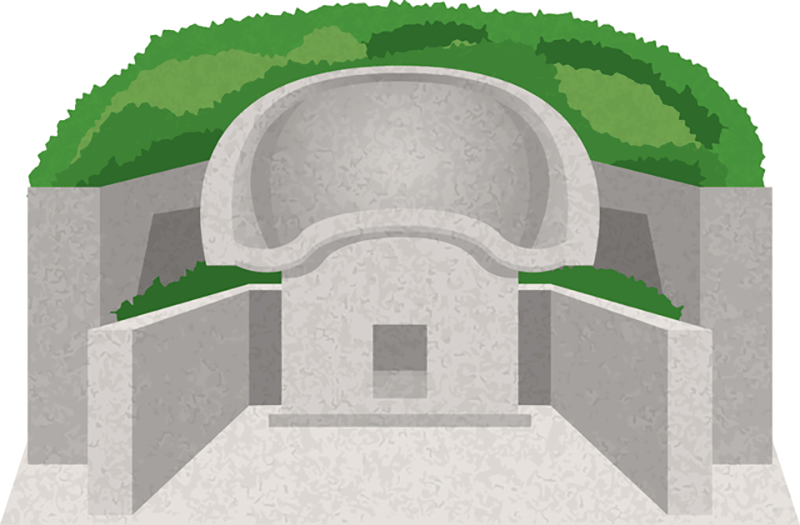
沖縄の風葬文化と大きなお墓の関係
沖縄でもともとおこなわれていた風葬とは、遺体をそのままお墓に安置し、自然の力で風化するのを待つという葬送方法。一定期間を経て骨になった遺体はあらためて骨壺に収められ、お墓の中へと納め直されます。風葬には遺体を安置する広い空間が必要とされたため、お墓自体も自然と大きな構造に。現在の沖縄では火葬が主流ですが、広いお墓の形だけは風葬の名残として受け継がれています。
また、風葬の時代には、自然風化した骨を納めるための骨壺である「ジーシガーミ」も大きく作られていました。風葬された遺骨は火葬された遺骨と比べて体積が大きいため、それに見合ったサイズの骨壺が必要になります。現在では他県と同じ骨壺に納めるのが一般的になっていますが、「ジーシガーミ」は美しい焼き物なので美術品としても評価されていました。
そして、葬儀にまつわるその他の習慣も沖縄ならでは。たとえば、死装束には針を襟元に刺す習わしがあり、これはあの世で水と交換できるという信仰に基づいたもの。また、遺体は西向きに安置されることが多く、これは太陽の沈む方角に向けるためです。
さらに、沖縄では「前火葬」といって、通夜や葬儀の前に火葬をおこなうのが一般的。本州では火葬が式の後におこなわれる場合が多いので、この違いに驚く方も少なくありません。また、沖縄の棺はやや小さめで深く作られており、遺体の脚を曲げて納めるのが特徴。これは「棺箱(クァンチェーバク)」と呼ばれる、かつて使用されていた小型の棺に由来するそうです。
このように、沖縄には他の地域とは異なる葬儀文化が今も根付いています。お墓の大きさはただの外観の特徴ではなく、長い歴史と文化を今でも大切にする想いが込められていました。