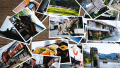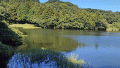終活を進めていると、「墓じまい」という言葉をよく耳にします。「墓じまい=お墓を片付ける」と推測はつくものの、実際に何をするのか、どんな人が墓じまいを検討すべきなのか明確に説明できる人は少ないのではないでしょうか。現在ご両親やご先祖様の墓石管理を任されている人は、この機会に墓じまいとは何か、手続きの方法や必要書類などもあわせて把握しておきましょう。
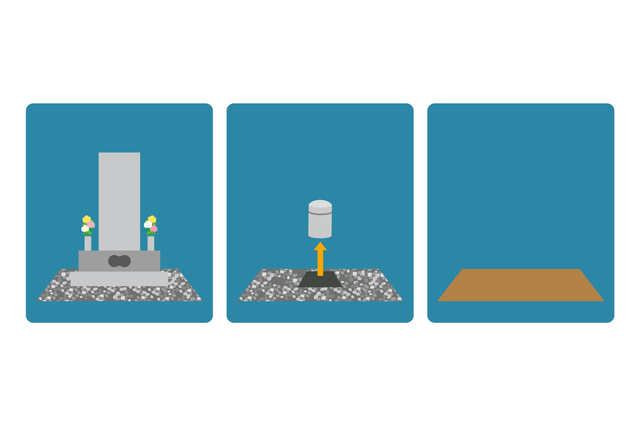
墓所の所有権を返還~遺骨を移動する「墓じまい」
墓じまいとは、墓石の撤去と同時に、墓石を建てていた土地を管理者に返還する手続きのことです。ただし墓じまいをすると、お墓に納骨されていたお骨の行き場がなくなってしまうことに。そのため墓じまいは墓石を撤去するだけでなく、永代供養墓や納骨堂など、新たな納骨先を用意するまでが一連の流れとなります。
高齢になって墓参りが困難になるなど、お墓を管理する親族がいなくなる場合に墓じまいを検討するケースが多いようです。ただし、墓じまいは独断で進めるとトラブルに発展しやすいので、必ず親族への相談が必要。全員の同意を得てから、新しい納骨先の決定や本格的な手続きに移りましょう。
また墓じまいを進める際は、墓所を管理する寺社や霊園とも話し合い、「離檀料」を納めることも少なくありません。離檀料の支払いは義務ではないものの、これまでのご厚意やご供養への感謝を示すもの。寺社や霊園に対し、3万~15万円程度の離檀料を納めるのが一般的と言われています。
墓じまいを進める際は、まず墓所の管理者から「埋葬証明書」、新しい納骨先の管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。その後、墓所を管轄する自治体で「改葬許可申請書」に両書類を添付して申請。すると「改葬許可証」が発行されるので、新しい納骨先の管理者へ提出しましょう。なお、墓じまいで散骨を選択する場合は、基本的に改葬許可を申請せず手続きを進めることが可能です。
墓石管理に難しさを感じてきた場合は、終活の一環として前向きに墓じまいを検討してみてはいかがでしょうか。