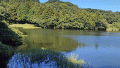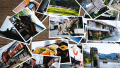人生の区切りのタイミングで考えたいのが「生前整理」。まだ元気なうちに、自分の財産や持ち物を整理しておくことを意味します。終活が「自分の人生を見つめ直す」行為であるのに対し、生前整理は「家族にかかる負担を減らす」ことを主とした、より実務的な作業です。

生前整理を始めるタイミングは? どうやって進めればいい?
生前整理を始めるタイミングとしておすすめなのは、子どもの独立や自身の退職など、人生の一区切りとなる場面。特に子どもが実家の財産情報を把握していないと、相続時の遺品整理に大きな負担がかかってしまいます。あらかじめ整理しておくことで、残された家族の負担をぐっと軽減できるでしょう。
生前整理は大きく「物品の整理」と「財産の整理」の2つに分けられます。物品の整理では、身の回りのものを「必要なもの」と「不要なもの」に分類することから始めましょう。不要なものは処分や売却を検討し、アルバムや記念品など、家族に受け継いでほしいものがある場合は、その意思を明確に伝えておきます。
また現代では、スマホやパソコンに保存された写真、メール、SNSアカウントなど、デジタル資産の整理も欠かせません。サブスクリプションの自動課金など、放置するとトラブルの種になりかねないものも多く存在します。不要なサービスは見直し、解約しておきましょう。
財産の整理では、預貯金、株式、不動産、車両、保険など、金銭に関わる資産の全体像をまずしっかりと把握します。その上で、どこに何があるのかを一覧にまとめ、信頼できる家族に伝えましょう。使っていない銀行口座やクレジットカードなどは放置すると管理が煩雑になるため、不要であれば解約するのが望ましいです。
整理した内容を伝える手段として、エンディングノートや遺言書があります。エンディングノートは法的効力を持つものではありませんが、自分の希望を自由に記せるため、家族にとっては大切な手がかりに。一方、遺言書には法的効力があるため、財産の相続に関する意思を明確に示すことができます。
不安がある方は、「生前整理アドバイザー」という民間資格を取得するのもいいでしょう。講座を受けることで整理の進め方や注意点を体系的に学ぶことができ、実際の行動に移しやすくなります。
元気なうちだからこそできる生前整理。一度に全てをおこなう必要はありません。気になる部分から、少しずつでも行動していくことが大切です。