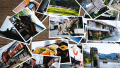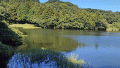人口減少と“移民”増加社会を迎えた日本において、外国にルーツを持つ人々の“弔い方”に関するトラブルが頻出している。特に、土葬を旨とするイスラム教徒をどこでどう葬るのかという問題は深刻だ。フィールドワークを軸にして研究を続ける文化人類学者が、イスラム墓地建設問題が持ち上がった大分県杵築市での実態調査などをもとに、「多文化共生」という美辞麗句のウラに隠された“落とし穴”を論じる。(文・写真:高木良子)
※この記事は「月刊終活2025年2月号」に掲載したものです。

「イスラム教徒が土葬墓地を求めるのは、これからイスラム教徒と結婚して改宗する日本人にも将来影響が出てくる問題だ。批判があっても土葬墓地設置の検討をやらなければならないと思う」
2024年12月23日、宮城県の村井嘉浩知事は定例会見の中で、「県内でのイスラム教徒向け土葬墓地設置の必要性」についてこう言及。これは、宮城県内にイスラム教徒(以下、ムスリム)の定住者が増え、彼らが宗教上の理由で土葬墓地を必要とするにもかかわらず、現状では東北に土葬可能な墓地がひとつもないことを背景とした発言であった。
しかしこの知事の言葉に、「なぜ宮城県にイスラム教徒が?」「どうしても土葬でなければならないのか?」と疑問を持った者も多くいたのではないだろうか。
実は私自身も、このニュースを驚きと違和感をもって受け止めた。私は文化人類学を専門とする研究者で、「弔い」をテーマとしている。これまで、日本国内の土葬墓地について情報を追い、現地調査も行ってきたが、「今の日本(今回の場合は東北)に土葬墓地が必要だ」という発言が行政側から出たということは実に画期的ではあった。
と同時に違和感をも覚えたのは、その後の知事コメント、すなわち「多文化共生社会と言いながら、そういったところ【在留外国人の墓地を指す/筆者補足】まで目が行き届いていないのは、私は行政としていかがかと強く感じた」という部分についてである。要は、「外国人を受け入れ多文化共生社会を謳うならば、彼らが日本国内でやがて迎える死までを受け入れる器が必要だ」というわけである。
しかし私は、日本国内におけるイスラム教徒向けの土葬墓地問題が「多文化共生」というキーワードのもとに語られがちなことに、以前から疑問を持ってきた。ゆえに村井知事の今回の発言も、「やはりか……」というのが正直な実感である。
そこで本稿では、今なぜこの問題が日本で起きつつあり、そして最終的にこの問題を解決に導くキーワードは本当に「多文化共生」なのかを、これまでの関連情報の整理と、私自身が行ってきた調査実例も交えながら、考えてみたいと思う。 まずは、なぜ今日本国内でイスラム教徒をめぐる土葬墓地が問題になっているのかを、日本の現状を示すデータとムスリムの死生観から概観してみよう。

ムスリムにとつて土葬は“必須”
現在、日本の人口は15年連続で減り続け、2050年には1億人を切るといわれている。その一方で過去最高数を記録しているのは在留外国人の数だ。少子高齢化が進み労働を担う若者が確保しづらい日本において、在留外国人は労働層としても期待されている。近年特に増えているのは、開発途上国から日本の技術や知識をOJT(On the Job Training)で学びにくる技能実習生だ。中でも多いのが、ベトナム、インドネシア、フィリピン出身者で、このうちインドネシアにはムスリムが多い。
2020年時点で日本にいるムスリムの数は約23万人で、うち日本国籍を有する人が約4万7000人。ムスリムと結婚し子をもうけた場合、教義上その配偶者と子どももイスラム教に改宗することになるため、この数には日本人も含まれている。宮城県での土葬墓地の需要も、2023年7月に県が人手不足を補うためにインドネシア政府と協定を結び、県内にインドネシア人労働者をさらに呼び込もうと取り組んでいるという事情が背景にある。
現在、この日本に在住するムスリムが抱える大きな問題が「土葬墓地」問題だ。なぜ彼らは土葬を必要とするのか? イスラム教では教義上、死後の「復活」のために身体が必要であるため、亡くなった後の速やかな土葬が必須とされる。また、死者の霊魂には意識や感覚もあるとされており、万一火葬されると、復活ができないだけでなく、地獄の業火で焼かれるような痛みをもたらすとされる。こうした理由から、ムスリムにとっては土葬以外の埋葬方法を選択する余地はないのだが、現代日本は火葬率99%を超える世界一の火葬大国であり、土葬を実現することへのハードルは高い。
もちろん日本でも土葬が多かった時代もあり、1910年代(大正初期)は50%が土葬であった。戦前の1930年代になると火葬が土葬の数を上回ったが、現在でも土葬は法的に禁じられているわけではない。しかし、限られた国土や公衆衛生を理由に火葬を進めてきた日本の背景をもってすると、土葬墓地を新たに開くことには住民の抵抗が大きい。仮にその用地を確保できたとしても、腐敗の進んでいく遺体をそのまま埋葬するという土葬のイメージは、公衆衛生という物質的な「汚れ」だけでなく、心理的な死の「穢れ」をも呼び起こすだろう。むろん住民の反対運動の中で前面に主張されるのは、前者の公衆衛生であることが多いが、実際の住民感情には、より直感的な心理的忌避感も含まれていることは想像に難くない。
「わが家の裏庭には置かないで」
こうした状況に、既存メディアが従来主張してきたのは「多文化共生の必要性」。つまり、国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的相違を認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていこうというわけだ。この問題に引き寄せて換言すれば、以下の通りだ。
「労働力を提供すべく日本で尽力してきた在留外国人が日本人と同じように国内で死を迎えることを、日本人は対等な立場で認めるべきであり、彼らが異なる宗教や文化的相違を持ち異なる墓地を求めることも、日本人と同じように受け入れるべきだ」
要は、「外国人に働くだけ働かせて、彼らに安心して死ねる場所を与えないというのはどうなのか」という問題提起である。しかし私は、土葬をめぐる諸問題が、異文化・異宗教共生の問題だと決めつけるのは、やや拙速な議論に思えてならない。
英語に「NIMBY」という言葉がある。「Not In My Backyard」、つまり「わが家の裏庭には置かないで」というわけだ。
「廃棄物処理施設や原子力発電所のような“嫌われものの施設”が公共に必要であることは認める。しかし、それが自宅近くに建設されるのは嫌だ」
“NIMBY”的なこの感情こそ筆者には、「ムスリムの土葬墓地」を考えるうえで、より本質的なのではないかと思われる。
そこで次に、ムスリムの土葬墓地開設をめぐって、まさにこの“NIMBY”的な反対運動が実際に起きた大分県日出町での事例を見てみよう。
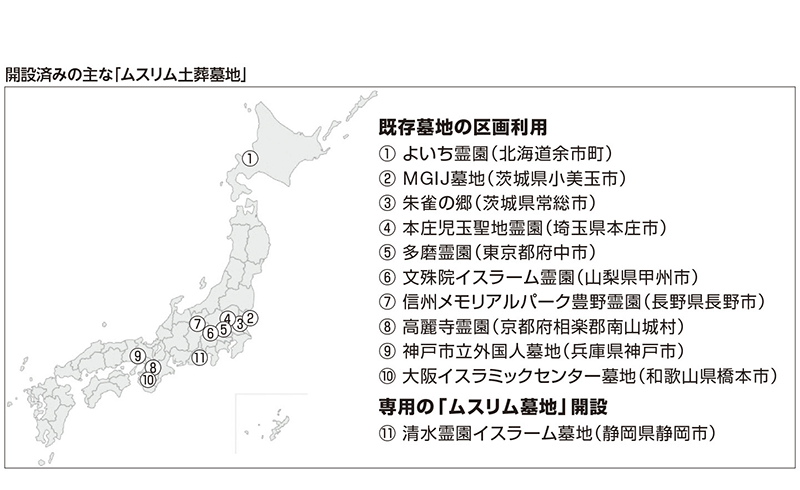
静岡県静岡市清水区の清水霊園イスラーム墓地(画像は筆者提供)
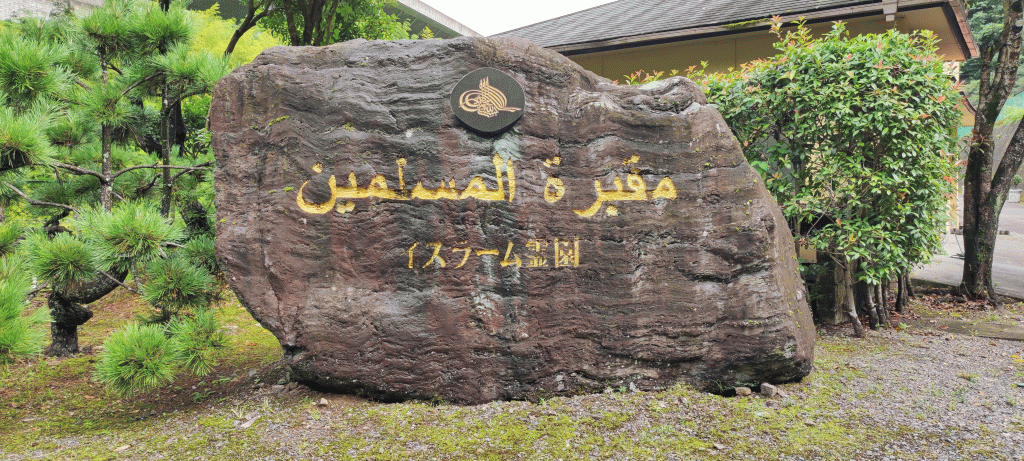

大分での「土葬墓地反対の陳情」
上図の通り、現在国内には、開設済み、ないし既存墓地の区画利用によって土葬可能な墓地は、全国で11カ所ある。
そのうち、現在進行形で開設に対して住民とムスリム団体、行政の間で議論が紛糾しているのが、大分県速見郡日出町での土葬墓地建設だ。
事の発端は2018年に遡る。大分県在住のムスリムコミュニティである宗教法人「別府ムスリム協会」(BMA)は、それまで10年ほど土葬墓地の開設準備を進め、同年、ようやく別府市に隣接する日出町の山中に「ムスリム墓地」用地として土地を購入した。
しかし2020年3月に同地での墓地開設許可をBMAが日出町に申請すると、これに対し同年12月、日出町議会が「水資源の汚染」を危惧する同町住民ら100名の署名を付した開設反対の陳情を採択。日出町の本田博文町長は「陳情は尊重する」としつつ、許可申請に対する判断を保留し、翌年1月、代替地として町有地を「ムスリム墓地」用地とすること、BMA・住民の双方で協定を結ぶことを提案した。
しかし、この提案に日出町住民より早く反対の声を上げたのは、代替地に隣接する杵築市山香町の住民ら。実は、日出町が代替地として選んだ町有地は、山香町住民の使用する水源からたった550メートルの場所に位置していたのである。山香町の住民は、土葬墓地建設によるこの水源へのネガティブな影響を懸念したのである。
こうした動きを、地元メディアを中心に多くのメディアが報じていく。それらを筆者の視点で大別すると、①経緯を説明するもの、②在日ムスリムの声を取り上げるもの(大分合同新聞/2022年1月4日付、フジテレビ/2024年11月23日放送)、③解決策として多文化共生や異宗教との共存を問うもの(NHK/2021年7月21日放送、大分合同新聞/2022年1月4日付け、2023年5月25日付)などがあった。しかしそこではなぜか、現地住民らの生の声が報じられることはほぼなかった。
では、このとき住民は実際に何を感じ、何に反対していたのだろうか。筆者は2023年7月に、山香町でのこの反対運動の先頭を担った同町上地区で実地調査を行い、上地区住民自治協議会のメンバーにインタビューを行った。次項では、その詳細を書いていこう。
なんとか許されたインタビュー取材
私が取材の申し入れをしたのはInstagramから。本来なら紹介などのルートを介したかったのだが、唯一わかったのは上地区住民自治協議会のInstagramアカウントのみだったのだ。
先方へのメッセージで私は自身が研究者であることを名乗り、インタビューの目的を記載。
「内容はわかりました。ただ、他のメンバーも含めSNS上のやり取りに不安が正直あります」
数日後に届いた返信にはこうあり、相当な警戒心を抱かせてしまったように感じられた。不躾な連絡を改めて詫びた上で、筆者の身元を証す情報を送り、現地の民泊へしばらく滞在する旨を伝える。住民から話が聞けるかどうかにかかわらず私は、現場に行くことをもう決めていた。
「現地でお会いしたいと思います」
さらに数週間後に先方より届いたこの返信に対し、不安に思いながらも私と会う決断をしてもらえたことに深く感謝しながら、私は現地へと向かったのだった。
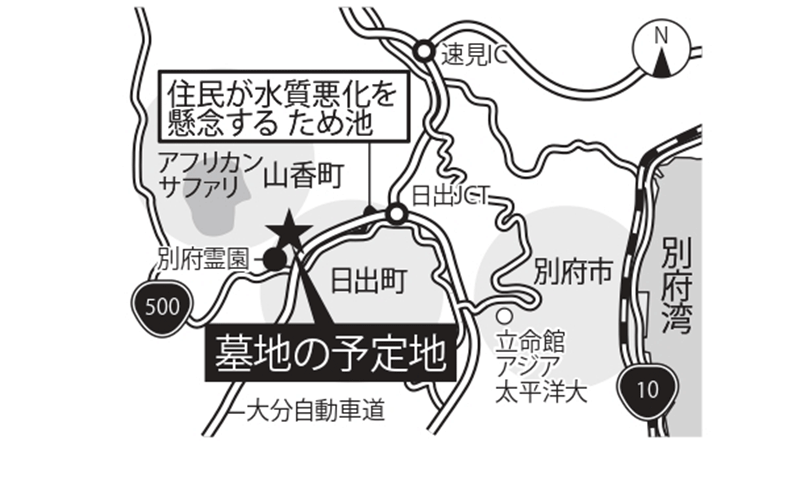
「私たちはムスリムフォビアではない」
到着した日の翌朝、宿泊先の民泊まで、協議会のメンバーが車でわざわざ迎えにきてくれた。途中さらに2人を拾って上地区の寄り合い施設へ到着すると、ようやくその2人が上地区住民自治協議会の会長と当地の水源関連施設の方であることを知った。
部屋へ入り、まずはSNSからコンタクトしたことの非礼を詫び、あらためてインタビュー承諾への礼を伝える。
「身分証まで見せてここまで来るという、あんたの意気込みに応えたわけじゃけど。ただ、まず聞きたいことがある」
座り直した会長の顔が、みるみるうちに厳しく変わる。
「単刀直入に聞くけども、あんたの目的は何で、何を書きにきた?」
訝しむような、恐れるような眼差し。私は、前日夜に書き出しておいたメモも取り出し、彼らに見せながら答えた。
「私が知りたいのは、この土葬墓地をめぐって起きている問題が、本当に多文化共生の問題なのかという点なんです。私はそうではないのではないかと思っています。この地域の郷土資料を見ると、水源がとても重視されてきた歴史があることがわかりました。そう考えると、今問題になっている『水質汚染』を心配する皆さんのお気持ちには、そうした水源信仰もかかわっているのではないかと。だから、この地域の水源にかかわる場所や、祭り、神楽など、昔から続く風習の調査に来たんです」
そう説明すると、ようやく彼らの表情も少しずつ和らぎ、ふたたび会長が口を開く。
「よし、わかった。さきほどは申し訳なかった。あんたを疑ったり責めたりするつもりはなかったんじゃが、メディアにはこれまでいろんなことを言われてきたもんでねえ。本意でないことを書かれるのはもうたくさんなんじゃ」
繰り返し語られたのは、イスラム土葬墓地問題をめぐってこれまで接してきた一部メディアへの不信と、メディアを通じたイメージから世間へ広がる風評への恐怖。
「私らがイスラムさんのことを毛嫌いしとるっちゅう人も出てきて。差別じゃとか。私らそんなことは一言も言うとらんのに」
彼らは、SNSでつぶやかれる言葉も拾っているようだった。筆者がSNSを通じてコンタクトしたことも、この人たちにどれだけのプレッシャーを与えただろうか。
「だから言葉を曲げずに必ず伝えてほしいんは、私らが反対しとるのは“土葬”でも“イスラムさん”でもないっちゅうことなんじゃわ。ただ場所だけ。私らの水源の近く、あそこだけは勘弁してほしい、それだけじゃ」
彼らはこうして、「私たちはムスリムフォビア(イスラム恐怖症、イスラム教への偏見をもつ人々)ではない」と繰り返し筆者に訴えた。この問題が「多文化共生」という大義名分の下に語られることで、ネット上において彼らは、頑迷にそれに反対する「異文化・異宗教否定者」へと貶められていたのである。

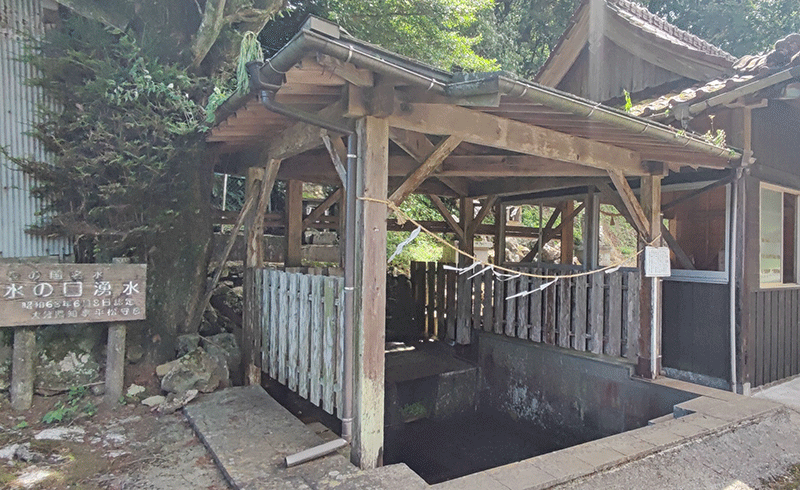
水源への深い“信仰心”
インタビューの後、彼らに連れられて筆者は、町有地で墓地予定地となった場所と、そこから550メートルのところにあるという山香町側の水源を巡った。
「このあたりは40年以上前にひどい渇水があってなあ。水がなければこのあたりの米やら牛やらの産業は全滅じゃから。苦労して苦労して、命かけて村の人たちみんな一緒になってようやくこの水源を掘り当てたんじゃ。あんとき、○○ちゃんのおいさんもおったな」
会長がそうメンバーに語りかける。この地域の水源というものが、当地で現代を生きる当事者のみならず、その前の世代、そのまた前の世代から守られてきたことを感じさせる言葉である。
半日をかけて、さまざまな現場を巡り道中を共にしていると、彼らの会話で繰り返される「水源と命」という言葉にはやはり、ただ単に水質の問題を問うのとは違うニュアンスがありそうである。
「国東半島の地形の影響を受け、江戸時代以前から水の確保が難しい自然環境にあった山香地域には、造成された溜池が131カ所ある。また、五穀豊穣のために神楽を奉納していた記録が各所にみられ、現代に至るまで水への感謝が変化なく続けられている」(山香町の郷土史『山香町誌』『続・山香町誌』などによる)
同町誌では、住民にとってこの地の水が特別な意味を持つと考えられる「水源信仰」に関する記述も多く見られる。現在地域住民に「水源を信仰しているか」と問えば、2025年のこの時代において「信仰」という言葉を積極的には使わないかもしれない。
しかし、現にこうした郷土史を見れば、この地には奉納されてきた神楽があり、雨乞いの行事があり、毎年「常提水神」を祀る常提水神社では「水の口湧水水祭り」と呼ばれる祭が開かれてきたのだ。
この地では、水の清らかさは数値で測れるものではなく、死や埋葬が想起させる「穢れ」と真っ向から対立する、侵すべかざる神聖なものなのだろう。
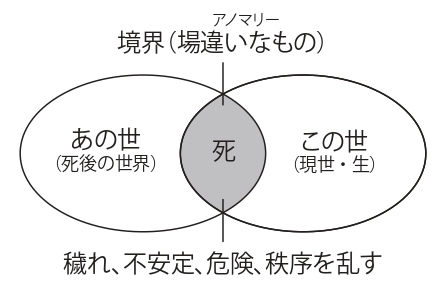
「信じるものへの忠節」と穢れ
「穢れ」といえば文化人類学ではよく「境界」という概念を持ち出す。英国の文化人類学者メアリ・ダグラスによれば、「穢れとは秩序を乱す場違いなもの(アノマリー)」で、2つの世界の中のどちらにも属すことができない「境界」に存在するものであるとされる。
この「2つの世界」を「死」を軸に考えてみると、「あの世」(死後の世界)と「この世」(現世)の境界にあるのが死だととらえることができる。2世界の境界にある「死」は不安定で危険であり、何か手をかけなければならない存在となる(この「手をかける」行為が葬儀などの「儀礼」であったりする)。
つまり、山香町の住民にとってみれば、生の根源にあるこの地の水源に、ムスリム土葬墓地問題によって突如、死が持ち込まれたわけだ。となればその境界には当然、「穢れ」が生まれる。
これは致し方のないことだ。こうした文化的な構造を見ずに、大義名分として「多文化共生」を持ち出すことは、筆者にはやはり、一足飛びの議論のように思われるのだ。もちろん筆者は、住民側を一方的に擁護したいわけではない。
しかし、水源信仰とイスラム教の土葬はいずれも「信じるものへの忠節」であり、法や技術や水質テストの数値だけでは解決しない問題ではなかろうか。
現在、この問題は紆余曲折の末、2024年8月の日出町長選で土葬墓地反対派の町長へ変わったことで、町有地の売却自体が白紙に戻ってしまった。日出町・杵築市山香町のこの事例は、土葬墓地の新規開設のハードルの高さを証明してしまったのである。
京都の寺で土葬が反対されなかったわけ
実は日本でも、ムスリムの土葬受け入れがうまくいっている墓地もある。
そのうちのひとつが、京都・奈良・滋賀の県境に位置する京都府相楽郡南山城村の高麗寺の墓地だ。
高麗寺は韓国最大の仏教宗派である曹渓寺を総本山とする韓国系寺院で、多くの在日コリアンの拠り所として存在してきたが、現在では、国籍・民族・宗派・宗旨・信仰不問の「高麗寺国際霊園」の中に土葬墓地エリアを併設している。
敷地内には第1墓地から第3墓地までが存在し、第1墓地は同霊園が開設された1971年より在日コリアンの民族墓地という位置付けで火葬墓地として、第2墓地は2022年から土葬墓地として、イスラム教だけでなくキリスト教、儒教など土葬文化を背景に持つ人々向けに国籍、宗教を問わず開放されている。第3墓地も土葬用として用意されており、今後、計3500基を超える土葬が可能になるのだという。
「同じ日本で墓地がなくて困っている外国人がいるんだといわれたら、自分たちにできることがあるなら、見て見ぬふりではなく手をさしのべるべきでしょう」
こう語る現在の高麗寺代表役員・崔炳潤氏に、土葬墓地設置の動機について聞くと、日本で受けてきた在日コリアンとしての自身の差別体験を挙げた。地域住民の反対はなかったのかとの問いには、もともと南山城村には近年まで土葬文化が残っていたことだけでなく、同村には地域住民との顔の見えるつきあいがあることを挙げ、特に反対は出なかったとのこと。
「数年間腰を据えてここに住んで、地域の行事や寄り合いに参加したり、炊き出しをしたりして、住民のみなさんの話を聞かせてもらいました。法律も大事ですが、こういうことは気持ちの問題も大きい。相手の顔が見えることがもっと大事です」
崔氏の語る「気持ちの問題」は、大分県の土葬墓地開設で住民が訴えた「水が穢れることへの忌避感」にもつながってこよう。土葬文化への理解や、相手の顔が見えることも、土葬墓地開設における重要なヒントなのだ。では、実際のところ今後、どのような形であれば土葬墓地の開設は可能となるのか。
国家レベルでの明確な“態度表明”を
新規の土葬墓地開設のハードルが相当に高いことは、先述した通り。たとえ周囲に民家のない広大な土地が見つかったとしても、水脈は地下でつながっている。「水質汚染」を謳う抗議は、どの地域で立ち上がってもおかしくないのだ。
ここで改めて本稿の「ムスリム土葬墓地」マップに戻ると、現在問題なく開設されている土葬墓地のほとんどが、「既存墓地の区画利用」であることがわかる。墓地の中には、自治体の条例や墓地管理者の規則によって土葬が制限されている地域もある。しかしこうした既存墓地の区画利用の場合、土葬が制限されていない墓地に、新たに土葬エリアを増設するという方法を採っている。これならば、既存墓地は行政に対し「墓地の変更許可申請」さえすれば、土葬墓地エリア設置の許可を得られる。
この方式の好事例には先述の高麗寺や、埼玉県の本庄児玉聖地霊園などがあり、いずれも住民からの反対運動などなく運営されている。こうしたやり方は、冒頭で挙げた宮城県においても、土葬墓地開設の有力な方法となるだろう。もちろん高麗寺でそうであったように、時間をかけて地元住民との“顔の見える関係”を築き上げることが、長期的な土葬墓地運営のために重要であることも忘れてはならない。
ただし近年、何事もなく運営されてきたはずの土葬墓地に対しても、土葬受け入れへの批判やムスリムフォビアを思わせる書き込みがSNSにおいてなされ、運営側が対応に追われるケースも起き始めている。
「個別の墓地や行政がこのような問題に対応するには限界がある。政府として、土葬需要に対して日本はどう応えるのか、態度を示してほしい」
実際にX(旧twitter)上での批判を体験した静岡県のムスリム専用墓地「清水霊園イスラーム墓地」の運営者はこのように語り、国家レベルでの対応を求める思いを吐露した。
墓地の経営許可についていえば実際のところ、もともとその許可権限は都道府県にあったが、2012年以降は県から市町村へとこの権限が移譲されている。このため実務レベルでは、市町村と墓地の所有者とが土葬墓地問題と対峙せざるを得ないのが現状だ。しかし墓地の運営者からすれば、自治体レベルなどではなく、国にこそこのムスリム土葬墓地についての“態度表明”を明確にしてほしいというのが本音なのだろう。
数値化可能なもの以外にも 突き動かされる私たち
最後に、国内土葬墓地開設に対して今後求められる条件を挙げてみよう。
第1に、国家単位での方向性の提示、第2に「多文化共生」というお題目の捉え直し。これは、外国人の持つ「他文化」だけでなく、大分県における「水源信仰」のように、私たちの側の文化や信仰を自覚し直すことも含まれよう。科学的に語られ、数値化可能なもの以外にも私たちは突き動かされていることを自覚することで、互いの信じるものへの理解も進むのではないか。
こうした相互理解を進めた上で第3に、京都・高麗寺における「互いの顔が見えるコミュニティづくり」といったものも必要とされるように、筆者には思われるのである。
参考文献
■中田考『イスラーム 生と死と聖戦』(集英社新書、2015年)
■メアリ・ダグラス『汚穢と禁忌』(ちくま学芸文庫、2009年)
■山香町誌編集委員会編『山香町誌』(山香町誌刊行会、1982年)
■山香町誌編纂委員会編『山香町誌 続編』(杵築市、2011年)
■吉田全宏「高麗寺国際霊園」(『Migrants Network』228号、2023年)
■公開シンポジウム「多様化する日本社会における老いと死:弔いと埋葬を巡る共生を考える」(於 東洋大学、2023年)