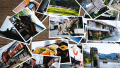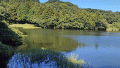お寺の後継ぎになることを拒み、抵抗を続けて生きていた若者が、人生観を変えて仏教の道に一歩を踏み出した時、世界が大きく変わった。歴代住職が守ってきたお寺をただ続けるのではなく、自分が必要だと信じる供養を行い、自分が思い描く理想のお寺を浅草の街に創る――﨑津寛光住職の「勇猛精進」の心がけには、目には見えないさまざまな支援が集まってくる。

壽仙院のヒストリー 寛光住職のストーリー
明暦の大火で浅草へ
国際通りとは昭和の時代、松竹歌劇団をはじめとするエンターテインメント公演で人気を博した浅草国際劇場があったことから付けられた名だ。東京メトロ銀座線・田原町駅、つくばエキスプレス浅草駅、そしてこの大通り沿いに佇む小さなお寺が壽仙院である。
江戸時代から遊郭や芝居小屋が立ち並び、歓楽地として栄えてきた浅草は東京でも有数の寺町でもあり、界隈には150以上のお寺がひしめいている。その多くは1657年の明暦の大火(俗にいう振袖火事)で移転してきたお寺で、壽仙院もその一つ。それ以前は日本橋小伝馬町にあり、創建は慶長8(1603)年――江戸幕府開府の年で、ゆうに400年を超える歴史を持つ。﨑津寛光住職はその第34世となる。

偉大な曽祖父の跡取り指名
「寺に生まれたというだけで、なぜ将来を決められるのか。そんな人生はまっぴらだ」
子供の頃からずっとそう思い、反発していたという。寛光氏が後継ぎを託されたのは4歳の時。関東大震災、東京大空襲。二度の大惨禍から壽仙院を守り、再建するという大仕事を遂げた先々代の曽祖父が末期の病床から語り掛けたという。「では寛光が継ぐまで私がパイプ役を」と祖母が法尼となり、約30年にわたって住職を務めることになった。
寛光氏は反発心を抱えたままま成長した。アメリカの大学に留学し、その後、商社に就職。優秀なビジネスマンとなり、30歳になる前、取引先であるドイツの会社から独立起業まで促されたという。
そこで彼は後継ぎ問題について話し、「世襲で寺院を継承するのは日本の悪習。私は継ぐつもりはないからご安心を」と説いて提案を受け入れようとしたところ、意外にもそのドイツ人社長は「君は間違っている」と諫めた。「欧州のプロテスタント教会も世襲のところはたくさんある。しかし、牧師たちは皆、立派に勤めている。君自身が世襲制にあぐらをかく僧侶にならなければよい」と継ぐことを薦めたのだ。
理想の寺づくりの二つの条件
人生の転機が訪れ、ついに寛光氏は腹を括って高齢の祖母に後を継ぐことを約束した。しかし、歴史ある壽仙院の伝統を守り続けるだけの保守的な住職になる気はなかった。欧米のキリスト教教会もアジアの仏閣も、誰でも自由に出入りできるのに日本の寺はなぜこうも敷居が高いのか。そもそも寺は今の社会に影響を与えるようなことを何もやってないではないか。ずっと抱えて来た不満・疑問を吐き出した。
こうなった以上、これらの不満・疑問には自ら立ち向かわなくてはならない。そこで彼は継ぐに当たって二つの条件を出した。「垣根のない寺づくりをする」「戦没者のために何か資する寺づくりをする」――真意がどれくらい伝わっていたのか分からないが、先代はもちろん承諾。総本山で修行し、僧籍を取得した寛光住職の理想の寺づくりが始まった。

戦地で倒れたままの先人にご供養を
ガダルカナル島への旅
戦後からすでに30年以上が経過した1970年代後半以降、豊かになった世の中では戦争は遠い過去の出来事になりつつあった。しかし、幼少の頃に祖父母から直接戦争体験の話を聞いて育った寛光住職は、戦記本やテレビのドキュメンタリー番組などで探究を深め、いつしか自分の目でかつての戦地を巡り、英霊のご供養をしたいと考えていた。
その希望を叶えたのが住職に就任する前の平成20年(2008年)4月。場所は激戦地だった南太平洋のソロモン諸島のガダルカナル島。前年に「全国ソロモン会」(ソロモン諸島方面の戦域で従軍した生存者や遺族の会)に入会していたが、最初は先入観を持たずに自分の目で現地を回りたいと、単身でかの地を訪れた。費用ももちろん自費である。
緑色のご遺骨
戦記などを読んでいたので、島の地理は概ね把握している。ただし、島内のほとんどは熱帯雨林で覆われている。むっとする熱気と湿気。飛行機や戦車の残骸。そしていたるところに転がる様々な遺留品。住職はお経を唱えて一週間で25カ所の戦闘区域を回った。その噂を聞きつけたのか、最終日に現地に在住するオーストラリア人(兵器や装備品の収集と研究をしているという)が譲ると言って、一つの箱を持って彼の前に現れた。
「箱の中には崩れた頭骨・大腿骨などが入っていました。衝撃を受けたのは、それがすべて緑色だったからです。私たちが普段目にするのは綺麗に荼毘に付された白いお骨ですが、その遺骨は60年以上(当時)経ってびっしり苔むしていたのです」
国のために命を賭けて戦った人たちが供養もされず、今もなお戦場となった地で何十年もの間、倒れたままになっている――その思いに胸を抉られた時から、この戦没者供養はライフワークになった。
兵士の魂が見せる自然現象
その後、寛光住職は帰還兵や遺族、仲間の僧侶らと一緒に戦地を訪れるようになる。場所ごとに戦友たちに求められるがまま、或いはご遺族ならその人の肉親が亡くなった場所でお経を唱えて供養する。
訪れる戦地もソロモン諸島に限らず、ミャンマー、フィリピン、グァムなどに広がり過去15年で30回以上、年2、3回ペースで行っている。現在は、ご遺族に限らず、戦没者の供養や遺骨収集に関心を寄せる人、そして若手のボランティアを募集し、面接・研修・訓練を経て現地へ赴く。野営キャンプを張って1回につき約100名のご遺骨を収容する。
「協力する僧侶は宗派など関係なく集まります。だから現地ではいろいろなお経が上がります。多様な僧侶が協力し合って供養する。供養とは何か、それを見直す活動でもあるのです。若いボランティアの中には仏式の礼拝の仕方や般若心経を覚えて来る人もいます。皆、今を生きることの大事さ・ありがたさをジャングルのなかで痛感するのです」
そう語る住職は、この活動を通していくつもの不思議な自然現象を経験するという。遺骨を収容して読経を終えると涙雨が降ったり、仮安置した祭壇に蛍が飛び交ったり、慰霊活動チームが日本に帰る日には必ず山や海に虹が掛かる。それを見ると今回も来て本当に良かったと思えるという。
「戦地に兵士の方々の念がある限り、ずっと続けるべきだと思っています」。
現在、寛光住職は全国ソロモン会の常任理事となり、壽仙院内に事務局を置いている。