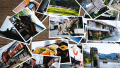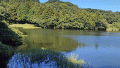独特な世界観で数々のマンガ作品やエッセイを世に放ち、アンダーグラウンドなサブカル界隈では“特殊漫画家”として知られる根本敬(65)。昨秋、彼は、「認知症告白」をしたタレント・蛭子能収(76)の「最後の展覧会」をプロデュースした。同じアングラ雑誌から世に出、「ずっとファンだった、10年上の大先輩」だという蛭子の老いを間近に眺め、「蛭子能収にもう一度絵を」という思いに根本氏を駆り立てたものはなんだったのか?
文:安田理央


2023年9月、東京・青山のギャラリーAKIO NAGASAWA GALLERY AOYAMAにおいて、「蛭子能収【最後の展覧会』展」が開催された。2020年に自身が初期の認知症であることを告白した、マンガ家でタレントの蛭子能収の絵画展である。
この展覧会を監修したのは、マンガ家・根本敬。1981年に雑誌「月刊漫画ガロ」(青林堂/当時)でデビューして以来、その過激で独創的な作風から、一般的なマンガの枠をはみ出した「特殊漫画家」などとも称され、蛭子と共に80年代以降の「ガロ」および「ガロ」を中心としたサブカルシーンを牽引してきた人物で、90年代には、奇妙な行動をとる人々を「電波系」と命名し、彼らにスポットライトを当てたことでも知られている。
『笑っていいとも!』(フジテレビ系)、『ローカル路線バス乗り継ぎの旅』(テレビ東京系)などのバラエティ番組において、“天然ボケの面白いおじさん”として長く活躍してきたタレント・蛭子能収を、そのイメージとはまったく違った“特殊な”感覚と思想を持った人物として常に注目してきた“蛭子ウォッチャー”でもあり、現在は『実話BUNKA超タブー』(コアマガジン)で、「蛭子能収 タブーなし! 但し『ぼぼ』は禁句」という連載も持っている。
「あれはもともと蛭子さんの連載だったんだけど、彼が書けなくなっちゃったから、おれが引き継ぐ形でやってるんですよ。思い出って加齢と共に忘れていっちゃうから、蛭子さんのことも書き残しておこうと思ってね。印刷物にしておくのがいちばんいいでしょう?
蛭子さんはおれより11才年上で、マンガ家としても『ガロ』で先にデビューしていて、ずっとファンでしたよ。おれの前にある“登れない山”みたいな存在で、目が離せないんですよね」






蛭子能収「最後の展覧会」展
2023年9月7日〜30日まで、東京・青山のギャラリー「AKIO NAGASAWA GALLERY AOYAMA」にて開催。根本敬監修のもと、蛭子能収の手による描き下ろし作品全19点が展示された。氏によれば、「このまま蛭⼦さんをフェイドアウトさせてはならない、絵を描くことからスタートした蛭⼦さんを最後は絵=芸術家として飾って貰えたらと考える⼈達が少なからずいた」ことによって企画されたという。
蛭子能収氏の絵画画像については→all images: ©︎Yoshikazu Ebisu, Courtesy of Akio Nagasawa Gallery
逸見政孝さんのお葬式でも「絶対に笑ってしまうから」
根本が語るエピソードとして印象深いものに、「葬式ではいつも笑ってしまう蛭子能収」がある。
「蛭子さんが葬式で笑ってしまうというのは、参列してるみんなが、本当はそんなに悲しくないだろうに神妙な顔をしてる――という状況がおかしくなっちゃうんだよね。で、『笑っちゃいけない』と思えば思うほど、笑っちゃう。
マンガ家の山田花子【註】が自殺した時に、マンガ家仲間で実家にお焼香しに行ったんですけど、行く最中にもずっと『笑っちゃったらどうしよう』ってしつこく言っててね。で、先方の家にあがる時に、おれの革靴のかかとが取れちゃったの、タイミング悪く。そうしたらもう蛭子さんは、ずっと身体を震わせて笑いをこらえてる。でもあとで、『あれは(山田の親御さんには)笑ってるっては気づかれなかったよ。泣いてるように見えたんじゃないか』なんて言ってましたよ(笑)。
アナウンサーの逸見政孝さんが亡くなった時も、『葬式では絶対に笑ってしまう。これでおれのタレント生命も終わりだ』ってしょんぼりしてたら、ディレクターが気を利かせてくれて、出席がナシになってことなきを得たってこともありましたね」
【註】山田花子:蛭子や根本らと同様、独特の作風で知られたマンガ家。1992年に24歳の若さで自死した。著書に『神の悪フザケ』『自殺直前日記』など。
「何もできないわけじゃあない」我が画業の師・蛭子能収 76歳、認知症の“リアル”
独特な世界観で数々のマンガ作品やエッセイを世に放ち、アンダーグラウンドなサブカル界隈では“特殊漫画家”として知られる根本敬(65)。昨秋、彼は、「認知症告白」をしたタレント・蛭子能収(76)の「最後の展覧会」をプロデュースした。同じアングラ雑誌から世に出、「ずっとファンだった、10年上の大先輩」だという蛭子の老いを、根本はどう眺め、何を思ったのか? タレントではない「マンガ家・蛭子能収」を愛し、「人間・蛭子能収」を知る根本氏に話を聞く。
2023年秋というタイミングに根本氏が、全作描き下ろしという形で蛭子能収の絵画個展を行うと考えたのは、『ガロ』マンガ家としての蛭子の“最後”を飾りたかったからだ。
「今ではタレントとしての蛭子能収のほうが知られているのかもしれないけど、いったん認知症になってしまったとなれば、出演するのは認知症関係の講演会や啓蒙的な番組ばかりになってしまうわけです。認知症の彼をタレントとしてはもう“笑えない”し、そこにしか価値がなくなってしまうからね。
でも、マンガ家のおれたちからすると、絵を描くことからキャリアをスタートした蛭子さんだからこそ、最後も彼に絵を描かせたかったんです。
蛭子さんは、『マンガなんていくら描いてもお金にならないから、タレントのほうがいい』って言ってましたけど、タレントは仮の姿で、本業はマンガ家だという思いは、絶対にあったと思うんです。だから最後は、今の蛭子さんが描ける範囲の絵で、なんとかギリギリ格好がつくうちに、展覧会をやらせたかった。
2023年の夏くらいから本格的に制作を始めたんですけど、その間にも、彼の症状はどんどん進行していきましたね。8月のうちになんとかしないと、これはもう本当に何も描けなくなるなって思いました。
後半は、自分でも何を描いているのか、わかっていなかったかもしれない。『これは何何だ〜』と一応説明はするけど、もう一度聞いたら、またまったく別のことを言ってたんじゃないかな。
あとここに丸い線を描けば完成っていう段階でも、意識がどっかに飛んでしまって突然描かなくなってしまう。『蛭子さん、あと丸を描いたら終わりだよ』って言っても、無表情でじーっとしてるんですよ。描かせようとするおれに対する反抗心なのかもしれないけど」
“子ども扱い”されることで 認知症が進行するのでは
認知症によって蛭子能収という人格が消えていく過程を、根本氏は間近で観察することになった。そこに恐怖を感じることはなかったのだろうか?
「自分の身に置き換えれば怖いのかもしれないけど、そうなった場合は、ある段階からわからなくなるでしょうからね。事実、蛭子さん自身は、現状の自分を何も不安には思ってないでしょうから。
でも、まわりのスタッフさんはどうしても、蛭子さんを『何もできない老人』として扱うわけですよ。それが余計に症状を進行させてるんじゃないかって思うんだけどね。
だって、おれと2人きりになって、昔話なんかしたりしてたらさ、蛭子さん、普通に歩くんだよ。『そこ、段差になってるから気をつけてよ』なんて言ったら、蛭子さんはちゃんと歩いてるのに、おれのほうが段差でつまずいちゃったりしてさ(笑)。
おれの知り合いに、“日本最高齢ラッパー”の坂上弘さんって人がいるんですよ。今、102歳。本人はお元気なんだけど、親族がみんな死んじゃったりして、それでしかたなく老人ホームに入ったんだけど、後悔しているらしい。全部生活を管理されて、全然自由がないって。102歳の誕生日には、まわりの人から赤ちゃん言葉で話しかけられたりしてね。
蛭子さんも、なかば“子ども扱い”をされたことで認知症の症状が進行してしまった――って側面もあるんじゃないかな。おれとしては、もっと普通に接してさ、『蛭子さん、たまにはカツ丼でもおごってくれよ』みたいにしたいんだけど」
根本氏は現在65歳。定義上は「高齢者」の仲間入りという年齢だ。彼は、自身の老いについてはどう考えているのか? 例えば終活を行おうという考えはないのだろうか?
「普通に会社勤めをしてたらもう定年の歳なんだろうけど、おれの場合、普段接してるのがそこから外れてる人ばっかりだから、つい忘れちゃうんだよね。
終活とか言ってるけど、そんなヒマがあったらほかのことをしたほうがいい。おれなんかは、子どもが手がかからなくならないことには、自分の終活なんてやる余裕はないもん(笑)。
まあ、自分が死んじゃったら、その後のことは自分ではわからないわけでしょう? 蛭子さんに今の自分がわからないことと同じだろうけど」

「〇番さん、お時間ですよ」 死ってそういうもの
死んでしまえばそれでおしまい。根本氏の死生観は、かなり達観したもののようだ。
「そういえば、前に蛭子さんが住んでいたマンションで、立て続けに4人だか5人だか人が亡くなったことがあるんですよ。その時に、『次は自分の番かもしれない』って蛭子さんが怖がってたんです。『順番が回ってきて、指名されたらおれは逝かなくちゃいけないんですよ』って言ってて。
それを聞いておれは思ったんですよ。おれが子どもの頃、家の近くの碑文谷公園(東京都目黒区)の池でボートに乗るのが好きで。混んでたら順番待ちで整理番号をもらう。30分とか45分たったら、『203番さん、時間です』なんてアナウンスがあって、そうしたら船着き場に戻らなくちゃいけない。生きる、死ぬってことは、そういうことなのかなって。
だって水木しげる先生も、『マンガ家仲間だった手塚(治虫)先生も藤子(・F・不二雄)先生もみんな死んじゃったけど、自分だけが生き残ってる』ってすごく誇りを持ってらして、93歳の時に『私は100歳まで生きると思うんですよ』って言ってたら、そのすぐ後に家で転んで頭を打って、あっさり亡くなられた(水木氏は享年93歳)。あ、“呼ばれちゃった”んだなって。
みんな、教えられてはいないんだけど時間が決まっていて、突然『何番さん、お時間です』ってお呼びの声がかかったら、行かなくちゃいけない。死ってそういうものなんじゃないかって、おれとしてはすごく腑に落ちる。死に対するときに、そういう自分だけの“神話”を持っていると、少し気持ちが楽になるんじゃないかなって思いますね。
それでも、死ぬ前にやっておかなくちゃいけないと思ってる仕事はあるんですよ。『未来精子ブラジル』ってマンガが、中断したまま30年たっちゃっていて(笑)。『あれはどうなってるんですか』って。30年言われ続けてる。あと100ページだけ描けばいいんだけど、なかなかまとまった時間が取れなくてね。これが未完のまま終わると、やっぱり心残りになるのかな。
まあ今だったら、死んだ後にAIが続きを描いてくれるかもしれない(笑)。でも死んだ後なんで自分ではわからないんだから、特別いやだとも思わないですね。別にいいやって。だから、『自分の葬儀はこうやってほしい』みたいなものも、あまりないですね。『月刊終活』の読者には悪いけど(笑)」
まだ土葬も多かった時代 “仏様”が水びたしに
根本氏にとっていちばん古い葬儀の記憶は、自身の祖父のお葬式の光景なのだという。
「棺桶が開かれていて、中に老人が横たわっていて、それを自分のおじさんとかおばさんが取り囲んで泣いているんです。『大人のくせに、なんで泣くんだろう』って不思議に思ったんですよ。その時、おれはまだ3歳だったから、死というものがわからない。仮に自分の母親だったとしても、わからなかったんじゃないかな。
その死んだおじいさんはおれのことを溺愛していて、おれのことをすごくかわいがってくれていたらしいんだけど、おれのほうには、おじいさんが生きている時の記憶は一切ない。
それでも、棺桶を前にしたその光景だけは、鮮烈に記憶に残っているんですよね。あまりに強烈だったから、生前のおじいさんの記憶が上書きされちゃったのかもしれない。
あと印象的だったのが、千葉のほうの遠縁のおじいさんのお葬式。おれが小学校の頃かな。まだ地方では土葬も普通にあったんでしょうね。それでおじいさんを埋めようと思って地面を掘ったら、水が出てきちゃった。しょうがないから、そのまま棺桶を水の中に突っ込んで埋めちゃったんですよ。でも、仏様が水びたしで、さすがにあんまりだろうってことになって、あとで掘り起こして、火葬し直したらしい(笑)。
その頃、その親戚の家に泊まりにいくと、家の裏が墓地なんですよ。近所の子どもがそこで遊んでたんだけど、地中に埋めた骨がだんだん地表に出てきちゃって、その骨をおもちゃにしてたりしてね。
そういう時代ですよ、おれの子どもの頃なんて。ついこの間まで、日本ってそんな感じだったんですよね」