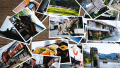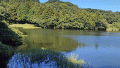江戸幕府の庇護のもと、近世期の寺院はどこもウハウハだった―。そんなイメージの強い江戸時代のお寺だが、実は当時も経営難に苦しむ寺院は多く、兼業やら観光客誘致やら、カネを稼ぎサバイブしていくための“戦略的寺院経営”に余念がなかったという。近世寺院の実態に詳しい歴史学者に聞く、江戸時代のお寺の経営戦略!(構成:門賀美央子)
「すべての人は、いずれかの寺院の檀家でなければならない」
江戸時代の寺院といえば、江戸幕府の命により成立したこの「寺檀制度」によって安定的な地位を獲得し、結果として幕府による民衆統制の一翼を担った。近代以降はその制度が徐々に崩壊し、檀家制度もいまや風前のともしび。寺院の新たな役割が求められている——。
檀家離れに苦しむ現代日本の寺院のありようを説明するにあたり、しばしば聞かれるこうしたストーリーを“全否定”する画期的な書物が今年1月、出版された。タイトルは『住職たちの経営戦略 近世寺院の苦しい財布事情』(吉川弘文館)。この本によれば、江戸時代にも寺院経営に苦しむ寺院は多く、ゆえに副業を持つ兼業住職もいれば、みずからの寺院を観光スポットにすべく努力する“アイデア住職”さえいたという。
著者は、淑徳大学人文学部准教授の田中洋平氏。「実は近世の寺院のありようは、現代の寺院に通じるところも多い」と語る田中氏に、江戸時代の寺院の“フトコロ事情”について聞いた。
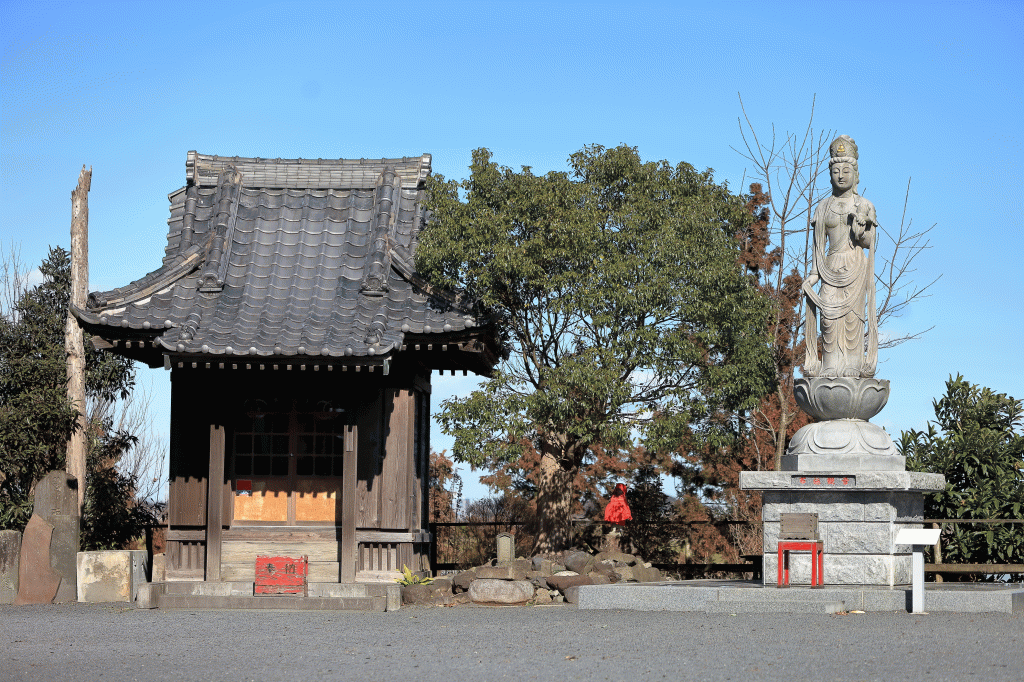
――本書では、近世から近代にかけての仏教界の様相を社会/経済面から見直すという非常にユニークな試みがされています。
田中洋平准教授(以下、田中) 現在の私は歴史学を研究していますが、大学は経済学部経営学科を卒業していて、歴史学に進んだのは大学院に入ってからでした。もっとも、元来歴史好きではありましたし、大学のゼミでも日本経済史を学んでいたのですが。
――経済史の中でも特に宗教界の経済事情に目を向けられたのは、何かきっかけがあったのでしょうか。
田中 私が大学に入学した1995年は、ちょうどオウム真理教の事件が起こった年でした。私はそれまで宗教にはまったく興味がなく、自分の家の宗派や菩提寺の名前すら知らないような人間だったのですが、あの事件はやはりショックでしたし、ずっと心のどこかに引っかかり続けていました。そこで、大学院に入って勉強することになった時に自分からいちばん遠い、理解しづらい宗教分野を研究対象にしようと思ったのです。しかしながら、大学時代に学んだ経済学や経営学も生かしたかった。それらを念頭に模索しているうちに「寺院経営」というキーワードが出てきました。
――本書は、正統的な歴史学のアプローチである古文書の分析を中心に行われていますが、これらの史料はどのように見いだされたのですか。
田中 大学時代、ゼミの先生に「宗教関係について考えたい」と相談したら、「群馬県に当地の修験者の日記が残っているから、それを使ってみてはどうか」とアドバイスを受けました。その修験者は加持祈祷だけでなく、神社の別当を務めたり、長屋を営んだり、長屋の店子に必要なものを手配したり、寺子屋の師匠をしたり、さらには養蚕までしていました。
――今風にいうなら、多角経営ですね。
田中 はい。現代の私たちは「修験者」ならば加持祈祷ばかりをやっていたように思いがちですが、実際のところ修験者という属性はその人物の一側面に過ぎない。彼は生きていくために、さまざまな経済活動を並行して行っていました。それらすべてを総合することで、1人の人間なり1軒の家なりが経済的に成り立っていたのです。この事実に気づいたのが、最初の起点となりました。
――ひと言で当時の仏教寺院のあり方を規定すると、どうなりますか?
田中 私は寺院を、「複合的な経済活動によって成り立つ一つの経営体」と位置づけています。そして、その定義が通用するのは江戸時代だけではありません。平安時代から現在に至るまで、寺院はあらゆる経営手段を総合した上で初めて成り立つものと考える必要があると思っています。
――本書では先生がそのような視点でやってこられたこれまでの研究成果の一端を一般読者に向けて書かれているわけですが、執筆する上で気をつけられたことはありますか?
田中 まず、一般の方々が中高の日本史の授業で近世の宗教世界をどのように教えられてきて、どれほどの知識を持っているのかを確認する必要がありました。教科書では江戸時代の寺院は、寺檀制度の下、国家の庇護を受けて安定していたと説明されています。しかし、実際にはそうとばかりはいえませんでした。ですので、読者のみなさんにはまずその部分に興味を持ってもらえたらなと考えました。
宗派性はあまりナシ⁉ 曹洞宗住職が“雨乞い”を
――読み始めて最初におもしろく感じたのが、江戸時代は寺院が「葬祭寺院」と「祈祷寺院」とに分かれていた、という部分でした。寺院は葬送儀礼が許されている寺院と許されていない寺院があり、寺請できるのは前者に限られるとのことでしたが。
田中 江戸幕府が全国の仏教寺院を統制するため、宗派ごとに本山/本寺によって組織化する「本末制度」を作ったのは教科書にも出てくる史実なのでご存知かと思います。この中で各地の寺は地域の葬送儀礼を行うことができる寺とできない寺に分かれました。そして、民衆管理の手段であった寺請をできるのは葬祭寺院のみでした。一方、祈祷寺院は葬送以外の宗教儀礼や共同体が必要とする祈祷、さらに人生儀礼の一端――たとえば子の名付けや病気平癒の祈願などをそれぞれの地域の中で担っていました。
――共同体の要請ということなら、雨乞いなども含まれていたのですか?
田中 もちろん入ってきます。雨乞いは基本的に修験者や陰陽師あたりが得意とする分野ではありますが、普通のお寺の住職でもやっていました。坐禅を教義とする曹洞宗ですら求められたら雨乞いの加持祈祷を行っていたんですよ。本来であれば祈祷には不向きな宗派のはずなのですが。実は江戸時代には、教義による宗派の相違は考えられているほど大きくありません。人々の需要があればなんでもやっていたのが実情です。寺の住職としてはやらざるを得ないし、むしろやらない理由がなかったのです。町で開業する内科医が胃痛を訴える患者に「私の専門は循環器系だから診られません」とはいわないようなものですね。
――神頼みのコンビニみたいな感じだったのでしょうか?
田中 はい、そうしたイメージでよいかと思います。さらに社会的な役割も大きかった。人々はどこかの寺の檀家になることで初めて身分保障がなされ、社会生活を送ることができました。極端ないい方をすれば、天皇や将軍から一般庶民に至るまで無視できない法度、ルールだったわけです。寺檀制度の枠組みは非常に強固で、たとえば私はA寺の檀家だけど、ちょっと都合があってB寺に移りたいといっても、それは許されません。離檀は原則として許されていなかったのです。普通に考えると離檀できない状況は、檀家の宗教的な欲求が強ければ強いほど、時としてフラストレーションの要因になりかねません。それを解消するのが祈祷寺院の役割でもありました。寺請や葬送は必ずA寺でやらなければならないけれども、それ以外の宗教的欲求は他の寺や神社で満たしても構わない。つまり、A寺の檀家でありながら、B寺で祈祷してもらったり、神社に参拝しても問題にならないわけです。檀家さんが寺檀制度内にいる限り、個別の信仰は許されていました。
江戸期にも起きた人口減少 経営難に対峙した寺院の姿
――寺請制度に関してもう少しうかがえればと思います。本書の中で、先生は明治時代になくなった寺檀制度が実体のない状態で漫然と続いていたけれども、それから約150年が経過したことで「制度の賞味期限切れ」が起こっていると指摘されています。これがまさに現在の墓じまい、檀家離れ問題の原因と考えてよいのでしょうか。
田中 ひとつの制度が制度としていったん確立してしまうと、強制力が働かない限り、その制度の崩壊はゆっくりと進行していきます。寺檀制度も、制度が廃止になった明治維新から160年が経とうとしている中で効力を失いつつあるのが今、というが私の印象です。つまり、檀那寺と檀家の関係をもとに戻すのは、時代を巻戻しでもしない限り無理。このまま進行していくことになるのでしょう。経済学的な制度分析の視点から見ると、そうした結論になります。
――逆にいえば、廃止されても一世紀以上も慣習として残るほど強固な制度に守られていた江戸時代の寺院さえ、その多くは当時からすでに経営戦略を立てて寺を守る必要に迫られていた、というのが本書の主旨ですね。特に興味深かったのが、江戸後期に人口減少にさらされた北関東地域で寺が生き残りをかけてあれこれ工夫していたという経緯でした。この部分などは現代にも通ずる現象のように思えます。
田中 まさに今と共通する事象です。現在、人口減少が社会問題になっていますが、歴史的に見ると人口減少は何度も繰り返されています。今に限った問題ではありません。その上で人口減少期の寺院がどのようにその波に耐えていったのか、あるいは耐えきれなかったのかが、歴史に学ぶことができるひとつだと思っています。
――北関東地域での人口減少はなぜ起こったのでしょうか?
田中 江戸時代前期頃の江戸は、北関東の人々にとっての一時的な出稼ぎ場所で、いずれは生地に戻るものでした。しかし、中期以降は江戸に永住する、あるいは客死するケースが増えていき、結果として人口減少が起きました。
――出稼ぎ中の身分保障してくれるのは、生地の檀那寺だったのですか?
田中 はい、そうです。住んでいるのは江戸だけど、檀那寺自体はそのまま地元で、というケースが多くありました。今でも住民票は地元に残したままほかの地域で働く、なんてことは普通にありますよね。こうしたケースだと「今、彼は江戸に出稼ぎに出ているから」と菩提寺が記録に残したりしているのですが、それが恒久的になってもう10年20年戻ってこないとなると、その段階で江戸に新たに菩提寺を、ということが起こり得ます。しかし、先ほどもいったように檀那寺を変えるのはハードルがとても高かった。もし江戸で新たに寺を見つけたいのならば、江戸の町名主の証明書に加えて元の寺の離檀証明書が必要だったのですが、基本的に離檀は認めてもらえないものでした。
――その点が非常におもしろく感じられました。今、離檀はホットな話題で、寺と檀家が揉めるケースがあるなどと報道されたりもしていますが、現代人の感覚では、なぜ弔う寺を変えるのにいちいち寺の許しを得なければならないのかがいまひとつわからない。しかし、そうした歴史的経緯があり、寺のほうに近世以来の昔ながらの意識が残っているのであれば、齟齬が生じるのも当然なのかもしれません。
田中 そうなんです。少し語弊があることを承知で申し上げれば、お寺さんの世界ではいまだに寺檀制度という言葉を使われています。しかし、寺檀制度は明治時代になくなっている。それなのにまだ当たり前のように出てくるという事実が、寺と檀家との問題を象徴していると私は思います。
明治維新と農地改革の荒波 「土地の喪失」で寺院が苦境に
――檀那寺と檀家の関係について、もう少し伺えればと思います。
田中 本書にも書いた通り、寺院経営が檀家に支えられてきた側面は、もちろん歴史的な事実としてはあります。しかし、寺を支えていたのが檀家だけかといわれたら、それは違う。最初に触れた修験者のように、複数の経済的な柱を持っているのが一般的でした。寺院の場合、檀家からの布施の他にも、所有する土地からの農業収入、檀家以外の信者からの喜捨、寺子屋などの運営から得る謝礼金、また貸金業など経済的手段は他にありました。現在でも地代収入や幼稚園などの経営を経済的な支えにしているお寺は少なくありませんが、それはこうした歴史を反映しています。
――ただ座って拝んでいればいいだけではなかったわけですね。
田中 江戸時代の記録を見ると、本当に多くのお寺が、少しでも田んぼや畑を増やそうと努力していた姿がありありと浮かんできます。ところが、明治時代の制度改革や第二次世界大戦後の農地改革などで土地が寺から離れていってしまい、これが現在のお寺の経営基盤を弱体化させた大きな要因のひとつになりました。
――経済的柱が失われた、と。
田中 はい。繰り返しになりますが、そもそもお寺は、同じ比重で寺院経営以外の事業と兼業することで成り立っていました。いい換えれば、経済的基盤は必ずしも宗教活動に限定される必要はない。ところが今の私たちはどうしても、宗教活動こそがお寺のメインで、それ以外はほんの付け足しと思いがちです。
――本書を読むと、宗教の営みもまた、実体経済の中の一部であることがよく理解できました。
田中 ええ、実体経済の中の一部でもありますし、お寺の経営を見ればその地域の特性がわかるというところもあります。双方向性があって、どちらから見てもおもしろいなと思っています。私はもともと経済畑の人間なので、お寺を通してその地域がどのように経済的に成り立っていたのかっていうところが、私の最大の関心事なのです。また、お寺が果たした地域の文化センター的な役割も興味深いところです。江戸時代の僧侶は僧としての役目だけでなく、寺子屋で勉強も教える、さらには俳句会みたいなのをして地域に俳句文化を広めたりもする。あらゆる地域活動の中心のようなものでした。多様な試みによって、マーケットを広げていったのですね。
――現在もある程度の規模のお寺だと幼稚園経営をやっているところは多いですし、都心の寺だと不動産運用で安定収入を得ていたりしますが、人口減少が続く地方の小規模寺院ほど、経営的に苦しくなっていると思います。先ほどお話しいただいた江戸後期の北関東の状況に似ているのではないでしょうか。
田中 そうですね。実際に今の社会状況は江戸時代中期から後期の状況に似ているだろうと思います。つまり、当時江戸に近い北関東で起こっていたことが、今は全国的な規模、大都市圏以外でも起こっているわけです。
――では、当時の状況に学べば、何か解決策が見つかるでしょうか?
田中 過去から何かを学ぶという点に関しては、ある程度慎重にならなければいけません。なぜなら、状況が似ているように見えても、歴史的な社会制度自体は大きく異なるからです。現代と江戸時代を単純に比較することは難しいのです。寺院の話に限っても、寺請制度があった時代と今では前提が大きく異なります。同じ部分と違う部分を見極めた上でどう考えるかが、まさに現代寺院の経営戦略に関わってくるのではないでしょうか。ただ、もちろん学ぶべきところはあって、たとえば江戸時代の寺院と同じように複数の経済活動を展開することができれば、経営も安定するとは思います。先ほど例に出ていた幼稚園や保育園の経営ですが、これなどは収入源としてのメリットはもちろん、それ以外の目に見えないメリットがたくさんあります。つまり、子どもたちを通して、地域の家族との関わりが生まれるわけです。地域において、寺の存在そのものが忘れられないというのは、長期的な目で見ると非常に重要です。このように、ひとつの要素からどう広げていくのか。ひとつのツールを持ったとしたら、そのツールから何を広げていくのかっていうのが、江戸時代の住職たちが実践していた経営戦略でした。
“秘仏”という経営戦略 桜見物で観光客まで誘致
――その点についても興味深い事例を紹介されていますね。最近は江戸庶民のツーリズムなどもずいぶんと知られるようになりましたが、本書では江戸時代からすでに寺院が参拝者や観光客誘致に熱心に取り組んでいた様子が詳らかにされています。
田中 今回はさほど詳しく書けなかったのですが、自分の寺をいかにアピールしてうまく売り出せるかも住職たちにとっては腕の見せどころでした。
――前々から、なぜ全国各地にこれほど「秘仏」があるのか不思議だったのですが、その謎も本書で解けました。
田中 経営判断としては、仏像を拝みにやってくる参詣客を集めるのに、日常的に人の目に触れられるような状態にすると希少性がなくなってありがたみがなくなるので得策ではないと考えることができます。しかし、まったく見せなければ信者を呼ぶ手段になり得ない。そのバランスの中で当時のお坊さんたちは、秘仏という方法論を見つけたのでしょう。

――本書では、秘仏の御開帳で得た資金を元にして、恒常的に稼げる観光名所まで作ってしまったお寺が紹介されていました。
田中 千葉県柏市の東海寺の事例ですね。東海寺では歴代の住職が何代にもわたって経営戦略を立て、実行しました。まずは地域にもとからあった弁財天信仰を自寺に取り込み、取り込んだらすぐにそれを開帳という形で短期間のうちに広めていく。ある程度認知度が高くなったら、今度はそれを12年に1回にして希少性を高める。一方、得た資金を使って所有地を増やし、経営基盤を固めていきつつ、近隣の山に桜を植えることで名所を創造してさらなる資産形成に乗り出しました。御開帳は12年に一度だけれど、桜は毎年咲くので、見物客を毎年確保できるというわけです。東海寺の場合、先行投資をしながら経営基盤を固めていったわけですが、代々の住職たちのその時々の経営判断が非常に巧みであったといえるでしょう。
――江戸時代の住職たちの奮闘は、今でも十分ヒントになるものを含んでいるように思いました。近世から近代に移る過程で、社会に大きな断絶があったように考えがちですが、実は同じような営みが連綿と続いていたということですね。
田中 その通りだと思います。現代に繋がる宗教的な枠組みは少なくとも江戸時代の中期以降にできて、それがずっと続いてきた。ただし、先ほど申し上げた通り、制度の慣性に陰りが見えたのがここ20〜30年の話ということになろうかと思います。
――そうした変化の中、歴史に学ぶにはどうすればよいでしょうか。
田中 逆説的ないい方になりますが、簡単には“歴史に学ばない”ことです。私たちは歴史の中に何かの教訓を見つけたら、それを次のステップ、未来へとそのまま生かそうとしがちですが、そもそも見つけたと思った教訓が事実なのかどうなのかをきちんと確定するところから始めないといけません。江戸時代の寺院がイメージとはまったく異なる生存戦略を取っていたのはこれまで説明した通りですが、時期や地域によってそれぞれ事情は大きく異なっています。そのバリエーションの多様さをきちんと見て、どれが自分の現状に最も近いのかをきちんと精査し、見極めた上で学ぶということが必要なのかなと思いますね。(了)
【田中洋平氏の著作】
『住職たちの経営戦略
近世寺院の苦しい財布事情』(吉川弘文館)
江戸時代の寺院はどこも、幕府の庇護のもとウハウハだった——。そんなイメージを覆す、画期的実証的歴史研究書。収入減と増える借金、檀家との主導権争い、先代住職の老後保障……。経営難に陥る零細寺院の姿を描き、寺の存続をかけ、地域を巻き込み展開した住職たちの苦闘に迫る。