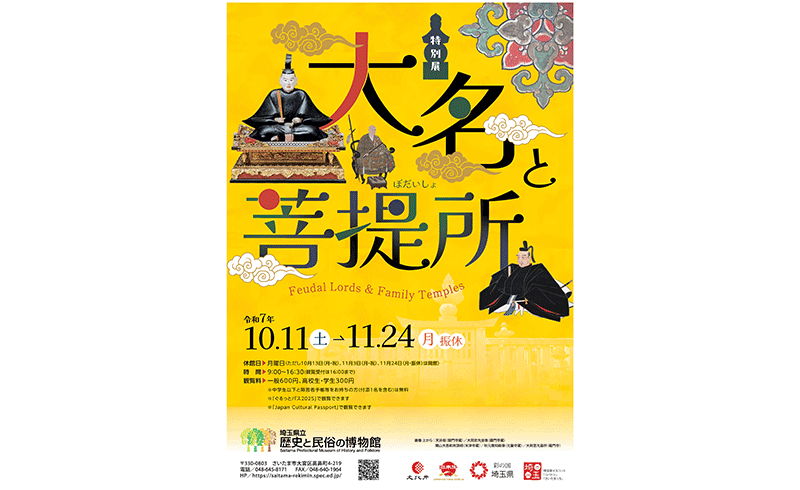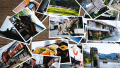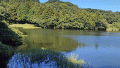埼玉県さいたま市にある埼玉県立歴史と民俗の博物館が10月11日より、埼玉県域ゆかりの「大名たちの終活」をテーマにした特別展を開催するという。“お家の存続”こそ最重要課題だった江戸時代の大名にとって、「菩提所」、すなわち墓所はどのような意味を持ち、そうした背景にはどのような死生観があったのか?同展覧会を企画した同館学芸員に話を聞いた。(文:山川徹 協力:埼玉県立歴史と民俗の博物館)
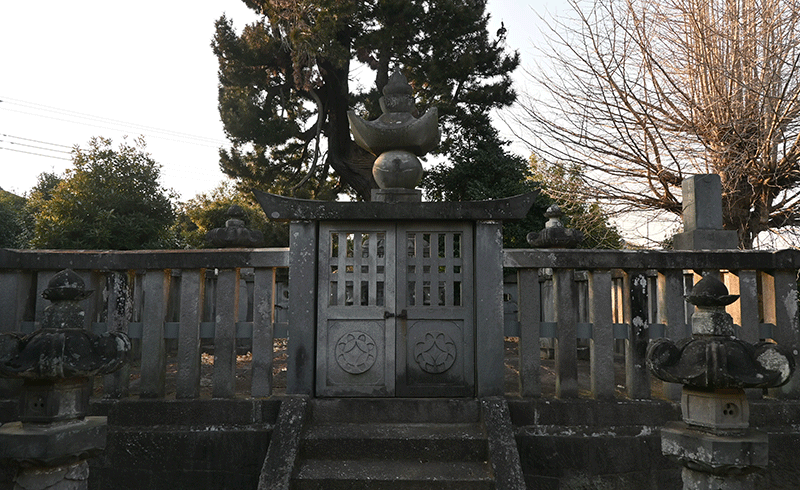
江戸時代の大名たちは、どんな死生観を持ち、どのような終活を行っていたのか?
そんなユニークなテーマに着目した企画が、埼玉県立歴史と民俗の博物館(埼玉県さいたま市)で10月11日より催される特別展「大名と菩提所」で披露されるという。「菩提所」とはすなわち、墓所のこと。つまりこの特別展は、江戸時代の武蔵国北部の「大名たちの墓」に焦点を当て、そうした菩提所のみならず、一緒に埋葬された副葬品、葬儀を取り仕切った菩提寺やそれら菩提寺などの仏教権力と大名との関係性なども素材として取り上げながら、当時の武家権力における葬儀、埋葬のあり方を考察するという意欲的な試みの場となっているのだ。
同博物館の学芸員で、今回の特別展を企画した黒田千尋さんは、企画の意図を次のように解説する。
黒田千尋(以下、黒田) 埼玉県は、東京――かつての江戸の北側に位置します。江戸の防備だけではなく、江戸と京都をつなぐ中山道や、徳川家康を祀る日光東照宮に向かう日光街道などが通る交通の要衝でした。そのため、現在の埼玉県にあたる武蔵国北部に建てられた忍城(行田市)、岩槻城(さいたま市岩槻区)、川越城(川越市)の城主は、老中などの幕府で重要な役職を担う大名が務めるという特徴がありました。
もうひとつの特徴が、大名たちが頻繁に入れ替わったこと。天正18(1590)年から、明治5(1872)年までの283年の間に、岩槻藩では、高力家、青山家、阿部家、板倉家――と、9家24代にわたり藩主が代わっています。川越藩は7家21代、忍藩では4家14代です。
では、入れ替わりが多かった大名たちと菩提所はどのような関係にあったのか。そこに着目すれば、いままであまり知られていなかった、大名の終活が見えてくるのではないかと考えたのです。
-1024x996.jpg)
「大名と菩提所」展示品01
「白綸子地梅樹に文字模様裂打敷」
打敷とは仏具などの下に敷かれる敷物。裏の銘によると、1775(安永4)年5月24日、川越藩秋元家7代涼朝(1717〜1775年)の菩提を弔うために、側室の貞性院が奉納。もとは貞性院が着用したものだという。
光厳寺(群馬県前橋市)蔵
※今回の特別展では写真展示のみ
「大名と菩提所」展示品02
「中山信吉木碑」
水戸藩付家老を務めた中山信吉(1577〜1642年)の墓前にかつて建てられていた亀趺碑(亀の形の台座に立つ碑)。角のない龍である螭と呼ばれる伝説上の生き物の首を持つ亀をかたどっているために「首螭亀趺」と呼ばれる。現存する亀趺碑は石製が多いために、木製は珍しい。死後、信吉の子である信正と信治が1644(寛永21)年8月に、儒学者である林羅山に撰文を依頼し、作成した。
智観寺(埼玉県飯能市)蔵
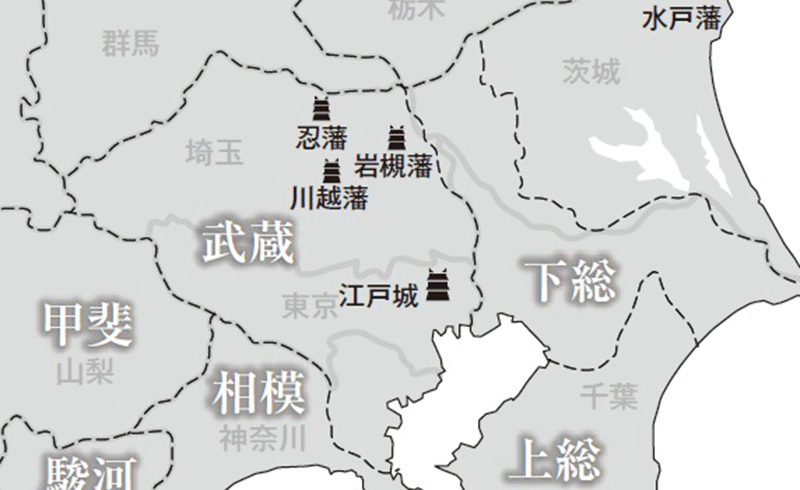
菩提所は、死後の冥福を祈る場だ。墓がある寺院を菩提寺と呼ぶが、弔いの場は墓所に限らない。供養のために法要が行われた場所や、かつて墓があった場所なども含むために広く「菩提所」としたという。
黒田 大名の菩提所というと、1カ所に歴代藩主のお墓がずらりと並んでいる光景を想像する人もいるかもしれません。もちろん転封で領地が変わったとしても、初代のお墓がある国元の菩提所に埋葬する家もある一方で、藩主が代わるたびに菩提所を変える家もありました。現実には、参勤交代があり、大名は、江戸と国元を何度も行き来する必要があります。江戸で亡くなる大名も少なくありません。国元にお墓があったとしても、江戸に埋葬する場合もありました。
たとえば、岩槻藩の藩主を5代57年にわたって務めた阿部家の墓所は、さいたま市の浄国寺、東京都台東区上野の寛永寺源龍院、同西浅草の東光院や西福寺などに点在しています。
阿部家のように参勤交代や、転封を繰り返す大名は、江戸と国元の両方に菩提所を持ったり、新たな領地に菩提寺を移動させたりしました。
川越にあった泰安寺は、川越藩主であった秋元家の菩提所でした。しかし秋元家の移封に際して、安永4(1775)年に川越から山形、その後、群馬の館林へと移転し、明治維新の頃に廃寺になるまで存続しました。
秋元家と入れ替わり、13代の川越藩主となったのが、前前橋藩主の松平朝矩です。松平家は、前橋から菩提寺である孝顕寺をともなって川越に入りました。しかし孝顕寺はまだ新しく狭かった。そこで松平家は、孝顕寺の西隣にあった川越大師喜多院に墓所を築きました。法要を執り行ったのは孝顕寺ですが、松平家のお墓はいまも喜多院にあります。ちなみに、孝顕寺は明治元(1868)年に前橋に戻っています。
こうした事例でもわかるように、大名と菩提所の関わり方は一様ではありません。それぞれの家によって、菩提所との関わり方は異なります。裏を返せば、大名と菩提所との関わり方をたどれば、大名家ごとの事情や、先祖への思い、さらには死生観までが浮かび上がってくるのです。
その点で注目したいのが、水戸藩付家老を務めた中山家歴代の墓がある飯能市の智観寺です。
中山家のもともとの姓は丹治でしたが、現在の飯能市にあたる武蔵国高麗郡中山を本拠にしたことから、中山姓を名乗りました。江戸時代に入り、中山信吉が水戸藩初代藩主の徳川頼房の養育係となったことから、中山家が代々水戸藩付家老を務めることになります。
水戸藩では、代々儒教式の方法で藩主を埋葬しました。水戸藩主の葬儀では、儒教にのっとって、遺体の口の中にものを含ませる儀式もありました。子が親の葬儀をどう執り行うのか。儒教では、そこがとても重視されます。
中山家の埋葬も儒教式です。儒教式の墓は、こんもりと土を盛った墳丘に諡を刻んだ碑を立てます。また廟所には、亀の形をした台座の上に碑を立てる亀趺碑を納めました。
中山信吉が亡くなってから380年以上が経ちますが、智観寺には中国の伝説上の生き物である角のない龍である螭の首を持つ亀をかたどった、中山信吉の亀趺碑がいまも保管されています。子孫にとって、いかに祖先が大切か。中山家が、儒教の教えを大切にした証左といえます。
僧侶にとって大名の葬儀は 誇るべき一世一代の“見せ場”
展示では、徳川将軍家の菩提所も取り上げた。徳川家の霊廟は「御霊屋」と呼ばれる。徳川家の葬儀や埋葬で重視されたのが、「継続性」だと黒田さんは指摘する。
黒田 3代将軍家光の代で、幕府の基礎ができあがったといわれています。それは、葬儀や弔いも例外ではありません。
初代家康は日光東照宮に、2代目秀忠は芝の増上寺、3代家光は日光の輪王寺に埋葬されました。4代将軍の家綱以降は、増上寺か上野の寛永寺に埋葬されるのが通例となりました。その後、谷中霊園に葬られた15代慶喜を除き、増上寺に6人、寛永寺に6人が埋葬されています。
徳川将軍は、代々神君家康公以来の前例にならうという意識を持っていました。継続性につながったのが、この“前例にならう”という意識です。それが、歳月を経て、やがて徳川家の伝統として受け継がれるようになったのです。
当然、各地の大名家も徳川将軍家にならうわけですから、家の継続性を意識しないわけがありません。江戸時代の大名にとって、もっとも大切なことが、家の存続です。断絶だけは、絶対に避けなければなりません。家を継続することが、江戸時代の大名にとって人生の目的であり、家の継続性を示すための葬儀や建墓こそが、大名にとっての終活だったといえるでしょう。
先祖を供養し、子どもとして親の葬儀を執り行うことは、大名にとって正当な後継者としての存在感を示す機会でした。代々の家の継続性や正当性を内外に誇示する場――それが葬儀だったのです。
代々の継続性を示すほかに大名家の葬儀には、3つの大きな役割があったと考えられています。
1つ目が、大名家同士の交際の場としての役割。縁戚の大名が香典を持ち、葬儀に参列する。そこに、大名家同士の関係性があらわれます。
2つ目が、寺院が格を示す場としての役割です。庶民の菩提寺に比べ、大名は格が高い寺院で弔われます。江戸時代は、現代よりも本寺と末寺の関係が明確でした。本寺は、いくつの末寺の僧侶を引き連れて法要を執り行うか。何人の僧侶を動員するかで寺格を誇りました。僧侶にとって、大名の葬儀は一世一代の見せ場でもあったわけです。
藩主の葬儀には、近隣の寺院からも僧侶が弔問に訪れました。水戸藩の例では、大名の菩提寺の住職は、弔問にきた僧侶が先に挨拶をするまでは、自ら感謝を述べなかったと記録されています。こうして寺の格式を示していました。
加えて水戸藩では、藩主の菩提所となった浄土宗と日蓮宗2つの寺院が、どちらが法要を務めるかを争う事件がありました。藩主の葬儀では、多額の供養料が入ります。藩主の葬儀は、お寺にとって、寺格を示すだけではなく、経済的な面でも大きな意味を持つ行事だったのです。では、なぜ、水戸藩は、複数の菩提寺を持ったのか。1つの寺院、1つの宗派に力を持たせるのを避けたかったという水戸藩の思惑もあったのでしょう。
大名の葬儀における3つ目の役割が、領民が藩主の存在を意識する数少ない機会だったこと。
忍や岩槻、川越の大名たちの葬儀がどのような形で執り行われたのか、残念ながら詳しい資料が残っていません。しかしある研究者の調査によって、葬儀を通じた藩主と領民の関係が明らかにされています。
江戸で亡くなった藩主が棺に入れられて、国元に帰ってくる。藩主の死から葬儀までのプロセスが、領民に藩主を身近に感じさせる装置として機能していたと見られます。
領民の視点から見れば、藩主は身分が違うだけではなく、物理的な距離のある遠い存在でした。
埼玉の大名に話を戻すと、宝暦6(1756)年から宝暦10(1760)年までの約4年間、岩槻藩主を務めたのが、大岡忠光です。在任期間中、大岡忠光が岩槻に滞在したのは、わずか10日ほどに過ぎません。忠光は、9代将軍徳川家重の側近である側用人だったために、ふだんは江戸にいたからです。
-1024x684.jpg)
「大名と菩提所」展示品03
「松平信綱坐像」
明治時代に彫刻家の高村光雲が製作した新座市の平林寺に保管されている忍城2代城主・松平信綱(1596〜1662年)の坐像。厨子の上から垂れる帳も、すべて木製だ。信綱は、死後に3代将軍徳川家光、4代家綱からの褒美や書状をことごとく燃やすよう遺言したため、遺品はほとんど残っていない。
金鳳山平林寺(埼玉県新座市)蔵 金鳳山平林寺(埼玉県新座市)蔵
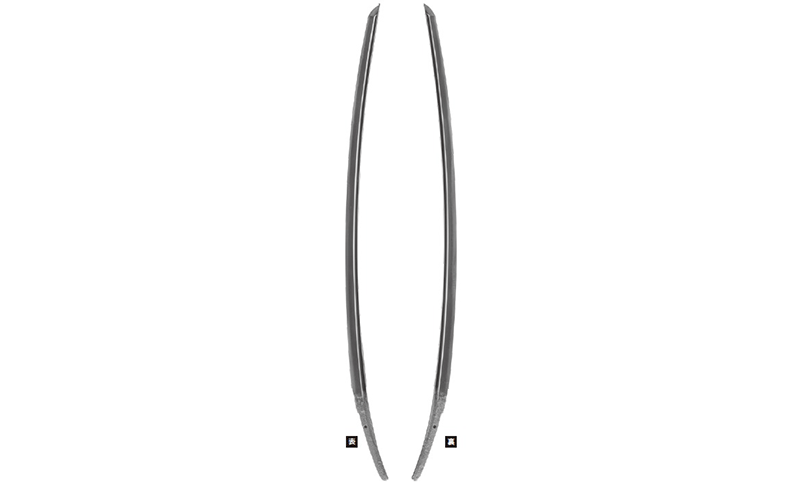
「大名と菩提所」展示品04
「国宝 太刀 銘 定利」
岩槻藩主阿部正春(1637〜1716年)が、4代将軍徳川家綱から拝領した「阿部家の太刀」。。京都綾小路派の刀工・定利が打った太刀。定利の最高傑作として知られる。1663(寛文3)年に日光社参の途中に岩槻城に立ち寄った家綱が下賜した。以後、代々阿部家に伝わり、のちに明治天皇に献上された。御物(皇室の私有品)となった際の木札が刀袋に縫い付けられている。
東京国立博物館(東京都台東区)所蔵
Image:TNM Image Archives
-1024x805.jpg)
「大名と菩提所」展示品05
「鎧甲目録」
岩槻藩主・大岡忠光(1712〜1760年)の没後すぐに岩槻の龍門寺に奉納された甲冑に附属する鎧甲目録、つまり岩槻藩主大岡家の“奉納カタログ”である。甲冑を構成する鑿甲や仮面、身甲、手甲、大袖、謄鎧、臑甲などの造作について記されている。兜の吹返や胸元から下がる杏葉などに、大岡家の家紋である「剣輪違崩」があしらわれる。また奥書によって、この甲冑一式が龍門寺の「廟堂」に奉納されたことがわかる。
龍門寺(さいたま市岩槻区)蔵
「大名と菩提所」展示品06
「土製のミニチュア食器」
岩槻藩大岡家6代藩主・忠固(1794〜1852)の嫡男だった久弥はわずか7歳で逝去した。その急逝した幼子をしのぶ食器。久弥の墓地からは、子どもの遊び道具である急須や皿、鉢などのミニチュア食器が出土。鯛や恵比寿の透かし細工の用途は不明だが、台座が附属しているため、立てて飾ることができたと考えられる。
大岡家藩主の副葬品は入れ歯 急逝した幼子の墓には玩具も
江戸時代の大名。現代の我々にとっても遠い存在だが、彼らを身近に感じられる展示がある。それが、菩提所に納められた、故人ゆかりの什物だ。什物のひとつひとつから、大名の個性や、考え方、遺族の思いが垣間見える。什物や、大名と一緒に埋葬された副葬品などの展示も〈大名と菩提所〉の大きな見所である。
黒田 菩提寺に奉納された什物で多いのが、武家の象徴である刀剣や甲冑です。
岩槻藩の阿部家では、4代将軍家綱から拝領した京都綾小路派の名工・定利の最高傑作といわれる太刀を代々受け継いできました。寛文3(1663)年、日光東照宮を参拝する途中、岩槻城に立ち寄った家綱より下賜され、のちに明治天皇に献上されました。現在、東京国立博物館に所蔵されている国宝の太刀を出品していただき、今回の「大名と菩提所」で展示します。
大岡忠光は所有した甲冑や太刀、脇指を菩提所の龍門寺に納めています。興味深いのは、奉納した品々の目録も残っていること。ほかの大名家や菩提所では、散逸してしまったり、何が奉納されていたかがわからなくなっていたりする場合も少なくありません。そんな中、代々の龍門寺の住職は、藩主の遺品を大切に保管してきたわけです。
大岡忠光は龍門寺に埋葬されましたが、それ以降の大岡家の藩主たちは六本木の湖雲寺に葬られました。最近、湖雲寺で発掘調査が行われ、多くの副葬品が出土しました。
故人の遺品である肥前焼のお猪口や硯などのほか、大岡家6代藩主の忠固のお墓からは入れ歯が出土しました。ただし、柔らかい石でできているので噛むのは難しかったはず。審美用の入れ歯だったのかもしれません。
コレクター気質だった忠固は、出土品だと思われる勾玉や、耳環などを生前に収集していたようです。故人が愛着を持っていた品々を棺に一緒に入れてあげたい。そんな遺族の気持ちは、江戸時代の大名も、私たちも変わりません。
大岡忠固の長男、久弥のお墓からの出土品からも遺族の思いが伝わります。7歳で急逝した久弥のお墓からは、子どもの遊び道具である急須や皿、鉢などのミニチュアが出土しました。忠固たち遺族は、どんな気持ちでこのおもちゃを棺に入れてあげたのか。想像すると胸が詰まります。
故人と遺族の関係性が忍ばれる什物もあります。さいたま市の光厳寺には川越藩主を務めた秋元家7代涼朝のために奉納された、仏具などの下に敷く打敷が残されています。この打敷は、側室の貞性院が、夫の供養に、と自身が愛用していた着物を仕立て直したものです。また秋元家では、9代川越藩主の喬知の150回忌にあたる文久3(1863)年に箪笥や行李などを覆う油単も光厳寺に納めています。
大名の個性や考え方という面で面白いのが、忍藩の2代目藩主である松平信綱です。信綱は新座市にある平林寺に埋葬されています。しかし信綱は、将軍から賜った褒美や書状はことごとく燃やすように、と遺言しました。家臣や遺族がその遺言を守ったので、ゆかりの品々はほとんど残っていません。 伝わっている話によると、自分の子孫には過ぎた物だと考えたようです。その背景には、過去の栄光にすがらずに生きるようにという子孫への戒めがあったのかもしれません。たくさんの什物を納める大名が多いなか、松平信綱は非常に珍しい考えの持ち主だったといえます。
DSC_8039(補)-1024x834.jpg)
幕府は“小規模葬”を奨励!?幕末には「葬儀マニュアル」も
江戸時代は1603年から1868年までの265年間も続く。なかでも江戸中期の元禄期(1688年から1704年)には経済が発展し、社会が大きく変化した。そうした変化は、大名の終活や葬儀、墓所の形に影響したのだろうか。
黒田 経済発展に対し、葬儀は徐々に小規模に質素になっていきました。それが経済的な事情なのか、先代よりも豪華な葬儀をよしとしなかったのかは、大名家の事情によって異なります。何よりも葬儀の縮小は幕府の方針でもありました。
江戸幕府は、倹約や風紀を維持するために、繰り返し葬儀を派手にしないよう法令を出しています。8代将軍徳川吉宗が行った享保の改革でも、「倹約」の一環として、葬礼の規模を制限するお達しが出ました。
吉宗は、徳川家の「御霊屋」の改革も行いました。代を重ねるに連れて増えていく「御霊屋」を減らそうと享保5(1720)年に御霊屋の新築や作り替えを禁止し、既存の御霊屋に合祀する形をとったのです。
江戸中期に出版文化が発達すると、イラスト入りで、どんな道具を使って葬儀を行うか、葬送の手順などを記したハウツー本も数多く出版されました。江戸末期に刊行された『葬事略記』には、年老いた両親がいる場合は、肖像画を用意しておくこと、遺言がある場合には記しておくことなど、いまに通じるようなさまざまな“終活”について記されています。
墓じまいや、直葬――。葬儀が形骸化し、墓や葬儀を不要と考える人たちも増えている。また樹木葬や散骨なども人気を集める。そんな時代に、家の継続性を願う場であった大名たちの菩提所は、何を訴えかけるのだろうか。
黒田 当然ですが、大名も命の終え方は選べません。早逝した大名もいれば、国元ではなく、江戸で亡くなった大名もいました。大名家の代々の終活をたどると、江戸時代の大名も社会の変化や、家の事情、亡くなる状況によって、菩提所やお墓、弔い方の形を変えています。
もちろん大名たちは、自分の家が永遠に存続し、繁栄することを願って、お墓を残したのでしょう。対して、現代では残された子どもたちに負担をかけたくないと墓じまいを検討する人たちの気持ちもわかります。
社会や価値観の変化とともに、お墓の形や葬儀の仕方が変わるのは自然なことです。
とはいえ、菩提所が残っているからこそ、現代に引き継がれる価値もあります。たとえば、岩槻藩士の子孫たちは、いまも大岡忠光が眠る龍門寺で、歴代藩主の法要を執り行っています。しかも毎年50人近い末裔の方々が集まるそうです。江戸が終わり、明治になって大正、昭和、平成という時代を経て、令和のいまになっても、大名の法要を執り行う――それは、藩士の末裔や龍門寺の僧侶だけではなく、時代や社会が変わっても、岩槻の人たちが、大名の菩提所という場を、大切に守ってきた証しだと感じるのです。

埼玉県さいたま市の大型公園、大宮公園内にある大型博物館。1971年に開館した埼玉県立博物館を前身とし、2006年、埼玉県岩槻市にあった埼玉県立民俗文化センターと統合する形でリニューアルオープン。国宝の太刀「銘 備前国長船住左兵衛尉景光」なども所蔵する。
住所:埼玉県さいたま市大宮区高鼻町4-219 開館時間:9時〜16時半(観覧受付は16時まで) 原則月曜日休館