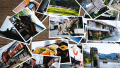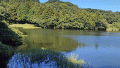日本は世界有数の「火葬大国」と呼ばれています。現在では99.9%もの人が火葬を選びますが、アメリカやヨーロッパの一部地域では土葬が一般的。この文化の違いはどこから生まれたのでしょうか? 今回は、火葬と土葬の違いや文化について深掘りしていきましょう。

日本の火葬文化のルーツ
まず火葬とは、遺体を火葬炉で焼いて骨を残す、現在の日本で一般的な葬送方法。そして土葬とは、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教で一般的な葬送方法で、遺体を棺に納め地中に埋める方法のことを指します。
火葬普及率が99.9%の日本ですが、実は日本もかつては火葬と土葬が併存していました。明治時代には一時的に「火葬禁止令」が出されたこともありますが、わずか1年で廃止に。その後、明治9年に西洋式火葬場が誕生し、火葬が本格的に普及し始めたのです。
現在火葬が主流になっている背景には、火葬が輪廻転生の一環とされている仏教の教えが関係しているよう。また、土地利用の効率化といった現実的な理由も大きな要因です。
これに対して、欧米で土葬文化が根づいているのはキリスト教の教えが影響しています。キリスト教では「死者の復活」が信じられており、肉体を燃やす行為はタブー。そのため、現在でも多くの地域で土葬が一般的なのです。
では、日本に住むキリスト教信者はどうしているのでしょうか? 実は現在の日本で土葬をおこなうためには特別な許可が必要で、手続きのハードルが高いのが現実です。そのため、火葬を選ぶケースがほとんどだといいます。
ちなみに、フランスをはじめとする一部の国では、土地不足の問題や火葬に対する忌避感の薄れから、火葬普及率が徐々に上昇。1970年代にはわずか1%だったフランスの火葬率が、2030年には約半数になる見込みであると言われています。これは現代社会における土地利用の課題が、火葬の利便性を見直すきっかけになっているとも言えるでしょう。
火葬と土葬の選択には、各国の文化的な背景や宗教的な理由が大きく影響していることがわかりました。しかし、昨今の土地不足や価値観の変化の影響で、ヨーロッパ圏でも徐々に火葬が主流になりつつあります。時代や環境によって文化や思想の変化を感じることができるのは、とても興味深いことではないでしょうか。