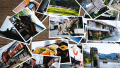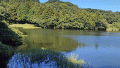博報堂DYグループAD plus VENTURE 株式会社しのぶば事業
代表 勢村理紗氏
株式会社めもるホールディングス
代表取締役 村本隆雄氏
むすびす株式会社
https://www.musubisu-osoushiki.jp
代表取締役社長 中川貴之氏
葬儀供養業界の誰もが大きな不安を抱えながら見据えるポストコロナの時代。日本有数のマーケティングサービス企業・博報堂DYホールディングスの参入は、その“ゲームチェンジャー”になるのかも知れない。さまざまな憶測が飛び交う中、「フューネラルマスターズクラブ」を主催し、葬儀業界の革新と経営戦略サポートに取り組む村本氏と中川氏が、勢村氏の事業コンセプトをエンディングビジネスの「ニューノーマル」として前向きに受け止めた。古い慣習・常識にとらわれない三人のディスカッションから、生活者発想のライフスタイル、IT技術の進化と浸透に基づいた、新しいヴィジョンが広がる。

オンライン追悼会「しのぶば」の紹介
自分の体験に基づき企画
通りがよいので簡単に「博報堂」と言ってしまうが、勢村氏が代表を務める「しのぶば」は、正確には博報堂DYグループのADplusVENTURE(アドベンチャー)株式会社の事業の一つである。同社はグループ56社から広く新規ビジネスアイディアを募集、審査、育成し、事業化する仕事を2010年から行っている。 勢村氏は8年前の2013年に母を亡くした実体験に基づき、オンライン追悼サービス「しのぶば」を発想し、企画。葬儀後の遺族や関係者のグリーフケア的なところに焦点を絞ったサービスを6月から開始した。それに際して、ぜひ多くの葬儀社とパートナーシップを結びたいと訴えた。生活者発想をご不幸の場でも
「しのぶば」は遺族が主催者となり、葬儀後の「故人を偲ぶ会」をオンラインで開催。故人にご縁のある人たちが参加しやすい時期・時間に集まることができ、どこからでも故人の思い出を持ち寄ることができる。メッセージや思い出の写真を集めたムービーの上映、追悼サイトの開設など、オンラインならではの機能と演出を提供する 「博報堂DYグループは生活者発想を活かして社会に新たな価値を生み出そうと活動していますが、今までは明るい面に向けた施策が多かったと思います。今回はそうじゃない、暗い面――辛い出来事にも生活者の視点を持って取り組みたい、と考えて企画・提案しました」 喜びや楽しみに繋がる明るい部分だけでなく、哀しみに繋がる葬儀・供養の場にも生活者発想で出来ることがあるはず、と語る勢村氏。その言葉を裏付けるように「しのぶば」の仕組みは、生活者がこの哀しみのライフイベントに際して負担に感じる部分にフォーカスし、それを和らげるにはどうすればいいかを追究して設計されている。コロナ禍の影響でオンラインでのコミュニケーションやお金のやり取りに対する抵抗感は薄れ始めている。今後、生活者がこうしたサービスを受け入れやすくなっていく可能性は高い。 (※注:実際は友人などが主催する場合が多いと想定されるが、金銭面でのトラブルなどを避けるため、あくまで遺族主催で行うことを原則としている)葬儀供養の場で生活者が負担に感じること
では、今の葬儀供養の場で生活者が負担に感じるのは具体的にどんなことだろうか? 家族葬が主流になり、葬儀に参列するのは遺族を含め、ごくわずかな人数である。そのために葬儀後、ご縁のあった人たちが集える場を設けたいと思う人がたくさんいる。けれども忙しい日常生活を送る中で、その準備にかかる時間的・経済的・精神的負担を考えると、よほど強い意思がなくては実行に踏み出せない。結局その人の思いだけで終わってしまうのが現実だ。 そうした負担感を取り除き、発注して趣旨を伝えれば、ほとんどの準備が整うのが「しのぶば」を利用する最大のメリットだろう。参加者からオンラインで会費を集められるシステムも用意されており、施主が経済的な負担を極力負わずに済む工夫もされている。開催期日も49日や一周忌など、従来の慣習にとらわれることなく参加しやすさを第一に考えてスケジューリングできるなど、自由度が高い。 そして勢村氏は葬儀社をパートナーとして考えており、「私達が皆様の事業のお手伝いをできることが必ずあると信じています」とメッセージを送った。
葬儀社からお別れをプロデュースする会社へ
オンライン葬儀がなかなか普及しない理由
昨年以降、感染予防対策、オンライン活動を含めた新しい生活様式として「ニューノーマル」と言う言葉を頻繁に耳にするようになった。「しのぶば」もエンディングのニューノーマルと位置付けることができだろう。 村本氏・中川氏ともに、「こうしたサービスも普及するかもしれない」と、最初はこのオンラインサービスに対してやや控えめに感想を述べていたが、葬儀に対する考え方をかなり刺激されたようだ。 葬儀業界でも都市部を中心に、オンライン葬儀がポピュラーになった。しかし実態はどうか? めもるホールディングスでは提供していないし、むすびすは用意はしているものの、利用は少ないという。中川氏は普及しない原因を考察し、何が問題なのかについて示唆に富むコメントを述べた。 「オンライン葬儀が普及しないのは、私たちが葬儀という形にこだわっているからでしょう。伝統的なものであれ、変わったものであれ、葬儀は葬儀。あるべき形に則った儀式であることに変わりはありません。まず、亡くなったらお葬式をする、という先入観を取り払い、お客様にどういう形のお別れをしたいのか聞き取って、それに応える必要があるのではないか、つまりこれから私たちは葬儀社でなく、〈お別れをプロデュースする会社〉に生まれ変わらなくてはならないと思いました」葬儀を構成する4つの要素
一方、村本氏は葬儀の役割を分解し、葬儀とはどんな場なのか考えていくと、4つの要素に分かれるのではないかという。 1.故人への感謝を伝える場 2.家族とのつながりを確認する場 3.故人を中心にご縁をいただいた人とのつながりを確認する場 4.いろいろな人とのつながりによって自分は生かされているという事実に気づく場 「私たちは今までこれらの要素をすべて2日間の葬儀に凝縮していました。けれどもそれは生活者の求めるものではなくなりつつある。家族葬・1日葬では1と2の要素は満たせるが、その後の3・4を満たし、故人を悼む人たちが自分の気持ちの整理をつけて人生の再出発に向かうためには、〈しのぶば〉のような場が必要なのかなと思います。葬儀社だけで完結できることは限られていて、いろいろな業種・業態の人とチームを組んだ一気通貫のサービスの提供が生活者のニーズに応えることではないかと考えます」遺族らの手づくり祭壇
また村本氏は、家族葬が提供し得る 1.故人への感謝を伝える場 2.家族とのつながりを確認する場 についてユニークな事例を紹介した。 それは一昨年あった同氏の義父の葬儀である。自社のホールで行ったが、葬儀社側では最低限のものしか用意せず、祭壇を家族に設営させたというのである。家族は家から写真や愛用品を持ち寄り、自由に祭壇を飾り付けた。結果、その満足度は非常に高かったという。つまりその祭壇製作の作業を通じて、全員が葬儀(家族葬)の本質である1と2に気づいたのだ。 これまでは葬儀社がフルサービスで完成品を提供し、参列者はただそこに来るだけだった。それが当然とされ、あるべき葬儀社のサービスとされてきた。しかし、生活者の意識は変わってきた。旅行やイベントをはじめ、様々な分野で製品・サービスを利用する際、生活者(消費者)はいわゆる「参加型」を望む場合が多い。「自分がひと手間かける余地」が付加価値を持つ時代になっている。サービス業である以上、葬儀も例外ではないというのが村本氏の見解だ。葬儀は遺族らの納得感がすべて
葬儀の持つ本質に気づくと、豪華な祭壇を提供することに価値はあるのか。生活者発想では祭壇は不要と言ってもいいのではないか。 村本氏は明言する。 「祭壇に値段を付けて稼ごうとするのはもう時代遅れのビジネスモデルです。そこにこだわっていると生き残れません。私たちは“祭壇を売る”という概念をすべて取り払わないといけません」 めもるホールディングスが展開している「ウィズハウス」という家族葬の会館は、セレモニーホールよりもむしろ生活空間である控室のデザイン・設計に重きを置いている。さらに今後はキッチンがあり、手料理を作って遺族・親族が食卓を囲む――そんな会館が好まれるようになるかも知れないと言う。「モノを売るのではなく、コト(体験)を売る方向にシフトするべきです」と語った。 これに対し中川氏は「お葬式は、お供え物とおもてなし」と見解を示し、祭壇は一種のお供え物であるから、宗教的な意味か、故人を表現する媒体であれば必要だという。ただし、その意味について遺族が納得できないのであれば不要になるのではないか、と述べる。 「お葬式は遺族や参列者の心の納得感がすべてであり、なぜこうした儀式をするのか、その意味付けが重要です。うちの会社ではスクリーン祭壇を使って空間づくりをしており、あると参列者が安心してその場に入りやすくなりますね。祭壇を作るにしてもそこにどんな意味付けをするかが課題だと思います」と語った。