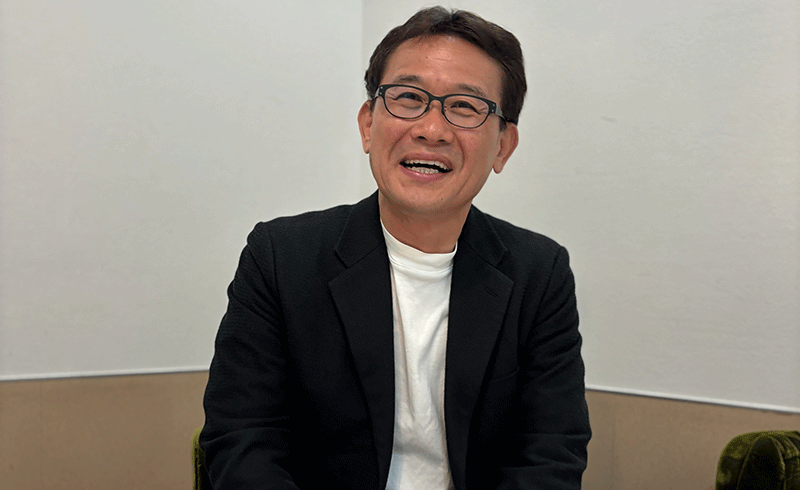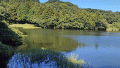「江戸時代までは土葬だった。近代以降徐々に火葬が広まった」「先祖代々の遺骨が納められた家墓を日本人は大切にしてきた」――。葬送・埋葬に関するそうした一般的な歴史観は、実は“ファンタジー”にすぎないのではないか? 日本各地へのフィールドワークを重ねてきた民俗学者にして歴史学者でもある大学教授に聞く、葬送とお墓の本当の歴史!(構成:門賀美央子)
日本人にとって墓地とは先祖との絆を結ぶ神聖な空間であり、家族の歴史が刻まれた記憶の場所である。それはどの地域でも変わらず昔から連綿と続いてきた古き良き伝統だ――というのが、現代人が持つ平均的な墓制観だろうか。
しかし、2025年4月に刊行された岩田重則『火葬と土葬 日本人の死生観』(青土社)を読めば、それが素朴な先入観に過ぎないことがわかる。
岩田さんは歴史学と民俗学を専門分野とする研究者で、本書では民俗学の手法による徹底したフィールドワークの成果に文献史学の手法を加え、さらに宗教史の視点も含みながら日本の墓制を検証した。

「僕の専門は多岐にわたっていて、民俗学もやれば歴史学もやる、という感じなんです。最近大学では歴史学の授業に比重が傾いていますが、かつては民俗学を教えていたこともあります。ですので、僕自身は、自分の専門領域を『日本をフィールドにした歴史学/民俗学』だととらえています。そのため、対象とする時代や事象もさまざまで、一昨年は『「玉音」放送の歴史学 八月一五日をめぐる権威と権力』(青土社)という本を上梓しました。これはアジア太平洋戦争が終わった頃の政治史や国家史を、メディアとの関係も含めた形で政治的あるいは軍事的に研究したものです。この流れに関連したものとしては、神社に関係する宗教論が研究分野のひとつの柱になっています。そして、もうひとつの柱が民俗学なのですが、フィールドワークに関しては、これはもう完全に独学なんです。というのも、もともと学んでいたのは日本の近現代史の思想史と政治史、つまり文献史学だったんですよ。つまり、基本は文献史学の中で育ってきたんです。ただ、学生の頃にはすでに民俗学に関心を持っていたので、興味のおもむくままあちらこちらのフィールドに出るようになっていました。最初のうちは村落構造の調査から入っていったのですが、転機は1989年か90年ぐらいに訪れました。この頃、初めて『両墓制』に出会ったんです」
両墓制とは、遺体の埋葬地と霊魂の祭祀対象としての墓を、場所を別にして持つ墓制のことだ。一般的に知られる両墓制では、埋葬地を埋墓(うめばか)、墓石のある墓地を詣墓(まいりばか)として区別する。埋墓が里から比較的離れた場所にあるのに対して、詣墓は村内の寺やお堂などに設けられることが多い。このような両墓制は、近畿地方を中心に関東地方、中部地方などに広く分布している。
「僕が初めて見た両墓制は三重県の美杉村(現・津市)のものだったのですが、こういう墓制があると知って愕然としたんです。その時はそれ以上深掘りすることはなかったものの、ずっと頭には残っていて、1990年代半ばくらいから真面目に墓制研究を始めるようになりました」
墓場の研究は岩田さんが専門とするもうひとつの領域、政治的・軍事的な戦争研究にも重なるという。
「墓地には必ず戦争で死んだ人の墓がありますよね。それもあって、フィールドでの民俗学的な墓制研究を、2つのテーマを混在させながらやってきました」
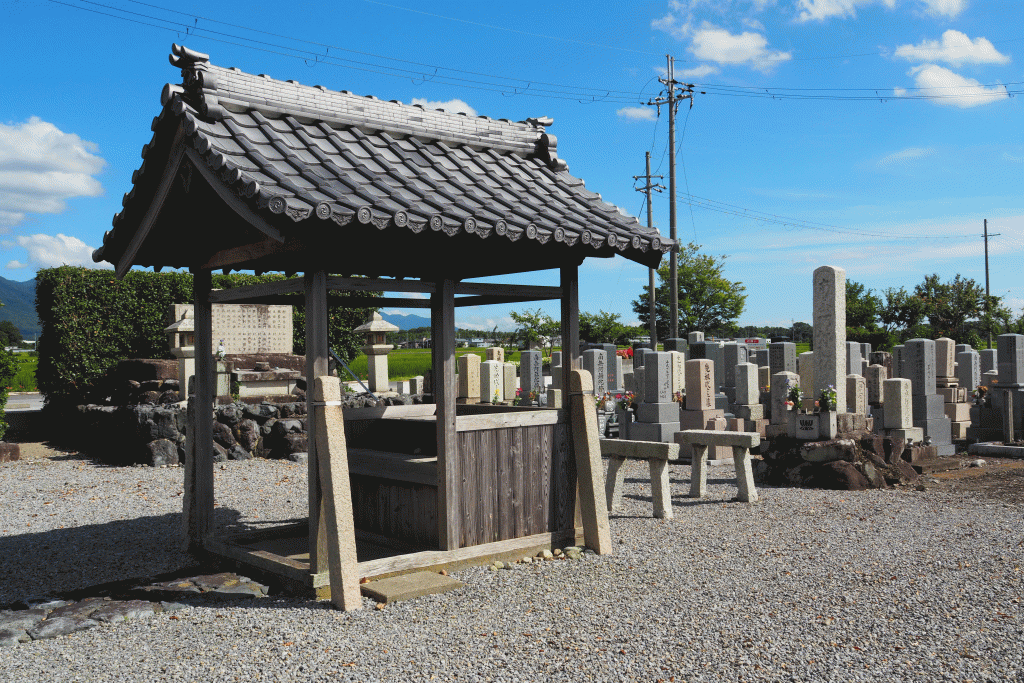
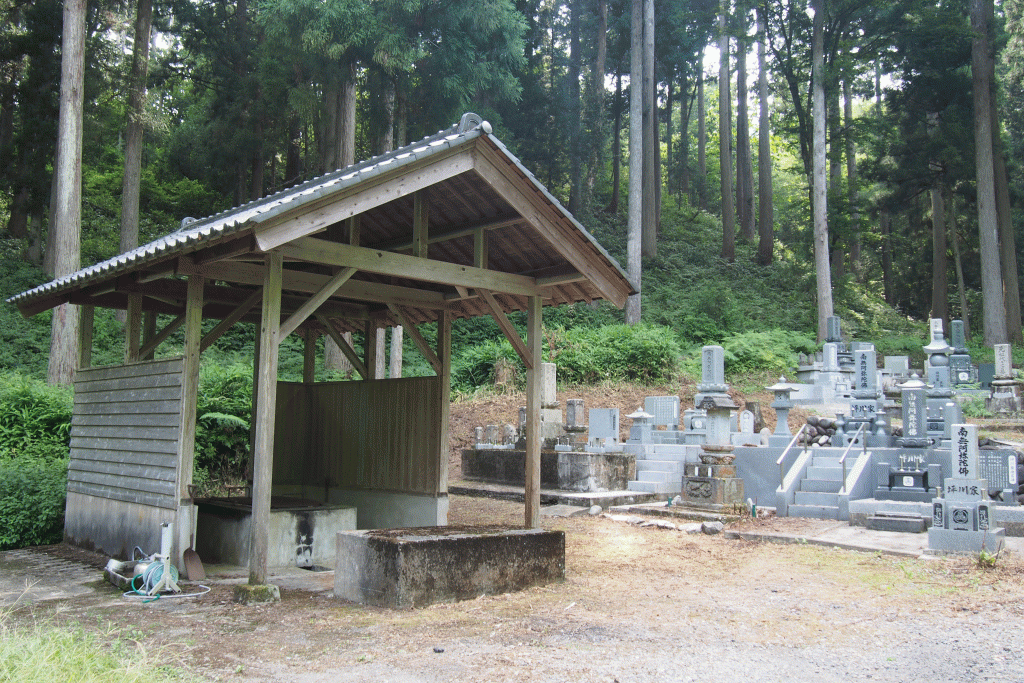
墓どころか位牌もない 骨は全部捨ててしまう
ところで、現在の日本は火葬率がほぼ100パーセントである。しかし、かつては土葬と火葬の両方が並行して行われ、昭和どころか平成に入ってもまだ土葬の地域は残っていた。全国まんべんなく火葬に切り替わったのはごく近年のことだ。
「1990年代には、まだけっこう生々しい土葬がありましたよ。サンマイなどと呼ばれる土葬用の区画を初めて見たときには、墓石がまったくなくて塔婆がただダーッと立っていたので、もしかしてと思って集落の人に『ここは土葬ですか?』と聞いたら、そうだという。でも、お寺の境内に墓石はあるんです。しかし墓の中は空っぽで、遺体を埋めているのはここだ、と。なるほど、これが両墓制なのかとちょっと感動してしまいました。それまで言葉としては知っていたものの、目の当たりにしたのは初めてでしたので。こういってはなんですが、その場所がやっぱりちょっと気味悪いんですよ。夏などはもう草がぼうぼうになっていて、蛇なんかも出たりする。僕も最初のうちは半ば怖いもの見たさでした。でも、だんだん学問的に面白くなってきて、腰を入れて研究を開始したのは2000年代の半ば頃でした。といっても、当初は単純に墓場が面白いなと思って、少しずつデータを蓄積したりするだけだったんですが」
土葬は昔々に行われていた埋葬方法であり、近代以降は徐々に火葬に切り替わっていった、というイメージが少なからずある。けれども、その変遷は必ずしも一直線ではなかった。岩田さんは、その経緯をフィールドワークと文献調査の両刀で詳らかにしていく。
「僕は静岡県静岡市の生まれです。現在の静岡市はもちろん火葬ですが、かつては土葬が主流でした。僕が子どもだった頃がちょうど火葬への転換期でしたね。それもあって、僕自身の中に『昔はどこも土葬だった』という固定観念がありました。しかし、これは僕に限ったことではありません。民俗学や歴史学の研究者の固定観念もやはり『昔は土葬』でした。ところが事実はそうではなかった。僕の場合、最初は両墓制の研究から始めましたが、2000年代ぐらいになってから調べ始めた両墓制地域の中に『うちはずっと昔から火葬だった』という地域が見つかるようになってきました。5つぐらいある集落のうち、ひとつぐらいは昔から土葬はやっていなかったと聞くわけです。そうした声に繰り返し当たる中で、僕自身おかしいなと思うようになり、これは概念の基本軸を転換しないとまずいかなと考えるようになりました。それが2010年代半ばぐらいだったかと思います。そして、その頃フィールドワークで、文献では読んで知っていた無墓制の地域にぶち当たったんです。このときはやっぱりショックでしたね。なにせ、墓どころか自宅の位牌すらないわけですよ。当然墓参りもしない。集落の火葬場で火葬しても、お骨はほとんど拾わない。本には部分収骨と書いたんですけど、実質的にはもうほとんど拾っていないに等しいのです。全部捨てちゃうんですよね。拾ったものも、墓や家には置かない。ではどうするかというと、寺などに納めるんですね。たとえばその一家の宗派が浄土真宗だと、遺骨の一部を京都の大谷本廟(西本願寺)や大谷祖廟(東本願寺)に持っていって納め、納めなかった残りは全部捨てる」
関西では部分収骨は当たり前だが、関東では骨を捨てるという発想がない。岩田さんも驚いたという。
「でも、そうした例を見ているうちに、僕も火葬制に研究の軸足を移すべきだと考えるようになりました」
いうまでもなく、無墓制の習慣は今に始まった話ではない。文字通り、先祖代々そうした方法が採られてきたのだ。
想像していた以上に多様な葬送方法と墓制。しかも、それは時代によって大きく変化していた。
並行して行っていた文献調査によって見えてきたのは、日本の埋葬文化には2度大きな転換点があった、という事実だった。

荒れるに任される火葬場と さして重要視されない墓
「一度目は大陸から仏教が入ってきて、それが国教として定着していった時期です。つまり、古代ですね。それまでは土葬だったのが、火葬が行われるようになりました。記録上確認できる日本初の火葬は『続日本紀』に記された道照という僧の葬送時で、700年に行われました。この火葬は道照の意思だったことが明記されています」
道照とは653年に第二回遣唐使の一員として入唐し、西遊記で有名な玄奘三蔵から教えを受けた人物だ。当時としては最先端をいく仏教人であり、国きっての名士だった。
「次に確認できるのは703年、持統天皇崩御の際に行われました。これは歴代天皇で初の火葬でもありました」
ただし、この火葬は天皇の没後すぐに行われたわけではなく、天皇家葬送儀礼の古式にのっとり、約1年間の殯(もがり/本埋葬するまでの間、遺体を棺に納めて喪屋内に安置し、近親の者が諸儀礼を行って魂を慰める習俗)を執り行った後、改めて火葬されている。
「この2つの事例は、日本の火葬の性格をよく表しています。つまり、仏教の影響の下、支配者層の葬法として始まったということで、これは火葬が権力の象徴だったことを示しているのです」
聖徳太子の時代に仏教が伝来してから150年ほどで、社会の上層部で新しい葬法が始まった。しかしながら、そのまま直線的に火葬社会になったわけではない。8世紀半ばから9世紀末にかけては再び土葬が増え、また火葬が主になるのは10世紀になってから。11世紀半ば、つまり平安時代になると火葬に加えて寺院納骨の風習が広がっていく。また、この寺院納骨は墓所として認識されるものではなく、あくまで阿弥陀如来への帰依の空間だった。一方、火葬地は墓所として認識されてはいるものの特に整備された様子もなく、荒れるに任されていたらしい。つまり、死者供養の対象となるのは火葬骨を納めた寺院だったとみてよい。墓はさほど重視されていなかったのだ。そして、この形式は中世後期以降、貴族階級から武士階級へと徐々に浸透していった。
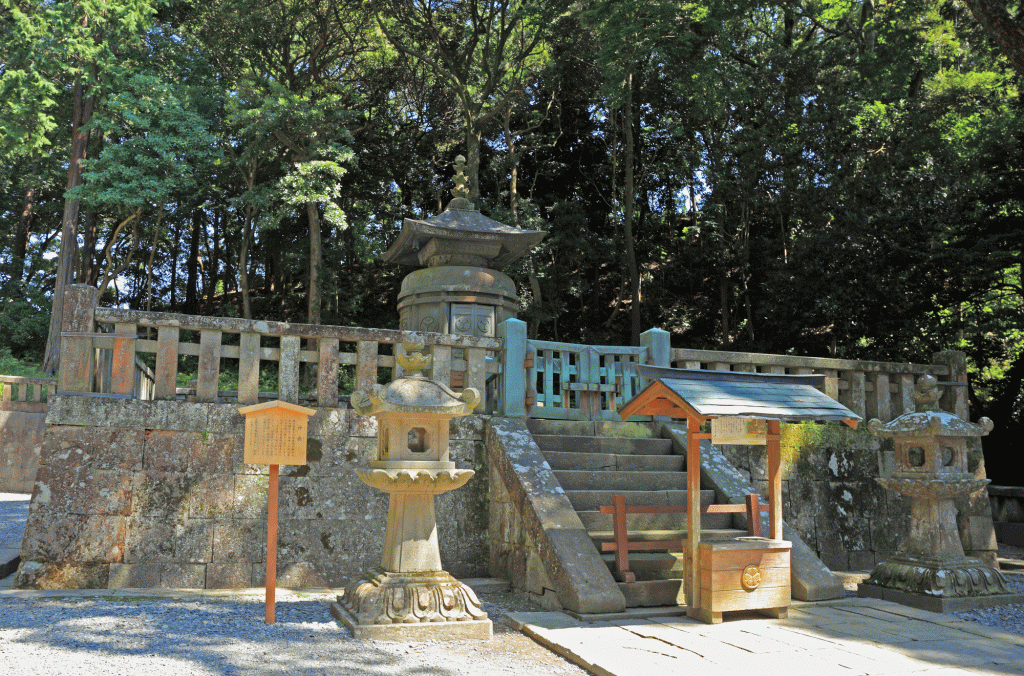
「ところが、近世に入る頃に突然土葬への回帰が発生します。実は、戦国時代を終わらせた豊臣秀吉と徳川家康は土葬を選択しているのです」
なぜ、2人の英傑は土葬を選んだのか。このあたりの経緯は著書に詳しいが、おおまかにまとめると、織田信長の影響があったのではないか、というのだ。信長は自ら神になることを生前から計画していた。それは本能寺の乱によって果たされないまま終わるわけだが、続く2人はその信長のプランを模倣し、神社に神として祀られる道を選んだ。しかし、仏教徒として火葬を選ぶと神にはなれない。そこで、それまでの伝統から逸脱して土葬を選んだのではないか、というのだ。
このように、時代ごとの変遷を詳しく見ていけばいくほど、現代に共有されている「昔は土葬で今は火葬」「都会は火葬で田舎は土葬」のような先入観がまったく正確ではないことがわかってくる。
「結局、古代に一度火葬が主流になっていたのが近世に入る時期に土葬に転換、しかし同時に火葬も継続され、宗派や地域の事情によって細分化していった、というのがいちばん実情にあった理解だと思います。これは一般的な研究者の理解とは少し異なるかもしれません。しかし、総合的に見ればおそらく間違ってはいないと自分では思っています」
都市部にこそ残っている 「ニッポン古層文化」
通俗的な理解とは見解が異なる点はもうひとつある。
一般的には田舎に行けば行くほど古い習慣や伝承が残っている、という思い込みがあるが、これに対しても岩田さんは異を唱える。
「実は、『火葬と土葬 日本人の死生観』の第1章を近江の火葬/無墓制の事例から始めたのは、狙いがあってのことでした。近江は滋賀県、つまり長らく日本の中心であった京都に隣接した地域です。結びつきも強く、決して周縁ではありません。むしろ中心といえるでしょう。しかし、そこに古い形の埋葬文化が根強く残っていた。かつての日本の中心部から本を始め、そして最終章も近江、つまり中心部で終わらせたのは、メタファーを意図してのことでした。誠実に研究をしてきた研究者ならたぶん読み解いてくれるものだと思うのですが……。
簡単に説明しますと、古い文化は田舎や僻地に残っているというような通俗的な認識が一般的にあって、それが文化研究の分野においても影響力を持っています。例えば、民俗学でいうと、柳田國男や折口信夫などはまさにそれで、日本列島では沖縄や東北地方にこそ日本の古層が残っているという発想ですね。柳田國男の『海上の道』などはまさに好例です」
『海上の道』は、柳田國男が1961年に発表した民俗学的考察で、日本人の祖先は海を渡って列島に到達したという「海上の道」説を提唱したものだ。特に南方から黒潮に乗って北上してきた海洋民族が日本文化の基層を形成したと考察し、そのルート上に日本文化の原型が残っているとしている。
「多くの民俗学上の有名な論文や書籍は、だいたいそういう認識を方法論に落とし込んで文化の展開を眺める形で書かれています。でも、僕は、本書で『いや、そうじゃないんだよ』と言いたかったのです。むしろ田舎というのは歴史も文化も浅い。逆に、富や権力を保持していた中央にこそ文化が蓄積している。そこから情報が伝達していった周縁にはたまさかそれが残存するだけです。新しい文化が発生する中央には、同時に古いものもそのまま蓄積されている。つまり、文化の古い形を知りたければ、むしろ中央を掘り下げていくしかない。そういう単純な理屈なんですけれども、墓場はその典型と思っています。また、今回、浄土真宗の事例を多く出させていただいたのは、かつての文化研究では浄土真宗の文化を脱落させていることが多いからなんです。いわゆる『門徒物知らず』という見方がそこにあったのかもしれませんが、結果として埋葬文化の考察において火葬が脱落した。だから、今回はあえて中央に近い滋賀の、浄土真宗の火葬および無墓制の事例を例として多用することで、従来無視されてきたところを軸にしながら論を展開しました」
みんながぼんやりと共有している認識から脱したところに、見えていなかった文化の古層がある。岩田さんがこの知見を得るに至ったのは、フィールドワークを重ねてきたからこそだという。
「やっぱり現地でしかわからないことってあります。でも、今の若い人はほとんど歩かない。それどころか研究者すらフィールドワークをあまり行わなくなってきた。しかし、本論が固定的な文化論、あるいは従来の研究内容だけに頼るのではなく、自分の足で確かめてきたからこそ得られた成果だということは、研究者であれば理解してくれるんじゃないかなとは思うのですが」
実は明治時代に広まった 「先祖代々の墓」という“伝統”
固定概念から自由になることは、現在の墓を巡る社会問題を語る際にも重要な視点をもたらしてくれる。
「まず、いわゆる“先祖代々の墓”。ああいうのが始まったのはおそらく江戸時代後期、幕末以降です。本書では触れていませんが、墓石に先祖代々なんて刻むことはそれ以前にはありませんでした。墓石が出てくるのは江戸時代の初期ぐらいからですが、最初は板碑状で、研究者用語ではかまぼこ型なんて言ったりするのですが、位牌の形に似たものでした。また、表面には家名ではなく個人の戒名(法名)が刻まれてあった。代々墓に関しては先行研究がありますし、僕も書いたことがありますが、江戸後期からやっと出てきて、広まったのはむしろ明治以降。つまり近代の現象なんです。それがなぜかずっと昔から続いているように世間は錯覚している。これらはいわゆる『創られた伝統』と呼ばれるものですね」
「創られた伝統」は英国の歴史研究家であるエリック・ホブズボウムやテレンス・レンジャーらによって提唱された概念で、現代の我々が古代や中世に発祥したと思い込んでいる“伝統”のほとんどは近代になってから創出されたものであることを喝破した。そして、日本のそれも実は大差ない。
「私のもうひとつの研究対象である靖国神社もまたそうなんですよね。もっといえば明治神宮、平安神宮、橿原神宮あたりだってそうです。ああした神社の形態は伝統でもなんでもなく、すべて近現代の政府によって意図的に、伝統を装う形で新たに創られたものにすぎません。我々はそういうようなものを“伝統”だと錯覚してステレオタイプ化して、それに慣らされてしまっているのではないでしょうか。でも、そういうのは多少壊れてもいいかなと思うんですけども」
一方、家族や先祖を思う場としての墓はあって然るべきものだとも考えている。
「僕もすでに父母を見送りましたが、やっぱり葬送儀礼は粗末にできないし、したくないと強く感じました。誰もがそうだと思うんですけど、親を見送るのは自分を見つめ直す機会になる。僕自身、人生の残りはあと三分の一ぐらいでしょうから、自分をどうするかっていうのもありますし。その上で、墓や葬式のあり方は多様でいいと思いますし、なくてもいいと思う。この3月に僕の父方の叔父が亡くなったのですが、その葬式はいわゆる家族葬で、本当にごく内輪だけで葬式をやった。僕は参列しなかったので後でお悔やみに行ったときに聞いたら、墓は新たに建てず最初から永代供養にして、お寺も実家の檀那寺ではなく宗派だけ同じの別の寺にしたということでした。遺された叔母もそれでいいと言っている。また、母の妹にあたる80歳を過ぎた叔母も、最初から寺院納骨にするつもりだと言っています。彼らは田舎の人たちなんですけど、それでもそういう意識になってきているんですね。分家というのもあるとは思いますが」
ただ、こうした変化は今に始まったものではない、と岩田さんは見ている。
「本書には事例としては含みませんでしたが、1980年代の終わりから1990年代くらいの関東甲信では土葬だけど墓石がない墓所もありました。理由をうかがうと、墓石を買う金がないからということでした。だから、昔から経済的な事情で墓石を建てないことも結構あったのでしょう。また、先ほど触れた昔の個人墓が全部残っていたらものすごい量になっているはずです。でも、それらは残っていない。つまり、墓石を建てないのは昔から案外普通だったのかもしれません。だから、伝統の名のもとにこだわる必要もないように思います。ただ一方で、心のよりどころが必要なのは間違いない。また、死にまつわる儀礼を粗末にしてはいけないとも感じています。どういう形を選ぶかは個人の死生観に大きく拠るのでしょう」(了)
『海上の道』柳田國男(岩波文庫)
柳田國男が1961年に発表した『海上の道』
【岩田重則氏の著作】
『火葬と土葬 日本人の死生観』岩田重則(青土社)
死者を誰がとむらうのか。亡骸をどのように、どこに埋葬するのか。そして、「墓」はいったいいつから、現在のような形の「墓」になったのか――。あらゆる土地の墓をめぐり、死と向き合ってきた人々の実像を文化や歴史の中に探り、そこに横たわる日本人の死生観の核心に迫る力作。