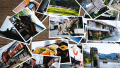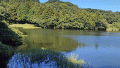終活として“遺言”の作成に取り組む人は少なくないでしょう。法的に有効な遺言を残すためには、作成時の正しいルールをあらかじめ理解しておくことが大切です。いったいどのような点に気をつければ良いのでしょうか?
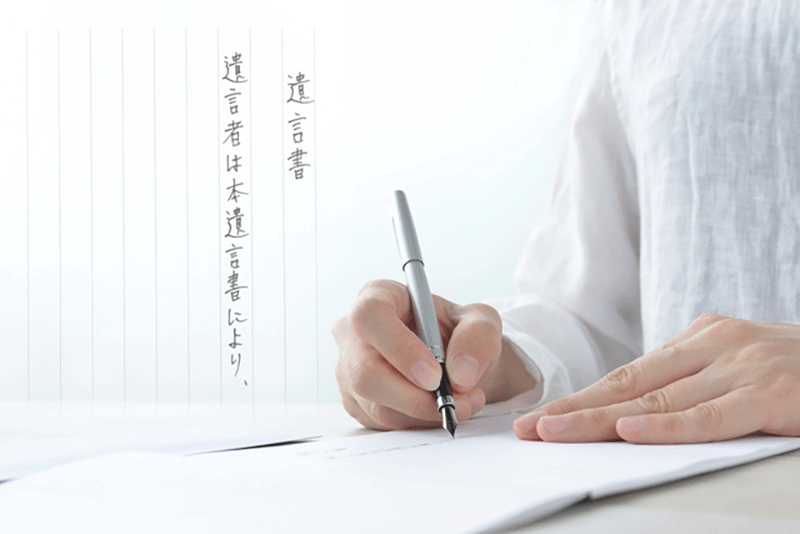
少しの不備で遺言内容が無効に……
遺言を残すうえでまず把握しておきたいのが、「遺書」と「遺言書」の違い。この2つは法的に区別されている概念です。
前者の「遺書」とは、故人が自由に残せるメッセージのこと。一般的には家族・友人に対する本人の想いや意思を書くものですが、法的な効力はありません。一方で遺産相続などの場面において力を発揮するのは、後者の「遺言書」です。
遺言書には大きく分けて2種類の形式があり、それぞれ作成方法も決まっているのが特徴。目的に合わせて正しい手続きを踏まなければなりません。
遺言書の種類のひとつが、「公正証書遺言」と呼ばれるもの。公証役場にて証人2名以上による立ち会いのもと、遺言者の意思を“公証人”に筆記でまとめてもらう形で作成します。公証人とは、法務大臣に任命され公正証書の作成といった公証業務を担う実質的な公務員。法律の専門家が作成するため書類上の不備が発生しにくいというのは、公正証書遺言を選択するメリットだと言えるでしょう。
加えて公正証書遺言の場合、原本は公証役場に保管されます。そのため遺言書を他人に処分されたり、勝手に内容を書き換えられたりするなどのトラブルも防止可能。作成費用はかかってしまいますが、その分安心できる要素も多いです。
遺言書のもうひとつの形式は、遺言者が手書きで作成する「自筆証書遺言」。遺言の内容と日付、氏名を自筆で記し押印することで、法的に効力を持つ遺言書が作れます。費用をかけず内容修正も簡単にできる点は手軽ですが、遺言者の死亡後は相続人や保管者が遺言書を家庭裁判所に提出する“検認”の手続が必要に。また書き方に不備があったり、必要書類を用意できていなかったりした場合、内容が無効になってしまうこともあります。
遺言書自体の紛失などにも特に注意が必要なので、自筆証書遺言の場合は法務局による「自筆証書遺言書保管制度」を利用するのがおすすめ。手数料はかかりますが、改ざん、盗難といったリスクは避けられるでしょう。
守るべきルールが多い、遺言書作成。自分の意思を周囲に正しく伝えるためにも、ときには専門家を頼るなど適切な対応が必要なようです。