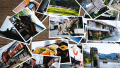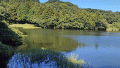静岡県沼津市を中心に活動するチーム「SMOW」(スモウ)は3社合同のプロジェクトで、墓石にするにはサイズや石の目が適さない石材を手元供養の墓石に活用しており、昨秋に実際の商品を販売開始した。その意図はなんなのか? 同チームのメンバーに話を聞いた。(取材・文:北 千代)

てのひらに納まる墓石を端材で作る
河原や海岸で、ふと目についた石がなんとはなしに気に入って、ポケットにすべり込ませる経験をしたことはないだろうか。気に入った石をポケットに入れる習性は、人間だけではないようだ。水族館の人気者・ラッコは、腹の上で貝殻を割って食べるための石を皮膚のしわにキープしているという。
どこにでもあり、時には道具にもなる一方で、信仰の対象となることもあるのが、石という素材の不思議さだろう。
今回ご紹介する「てのひらぼせきIL(イル)」もまた、石材の魅力を感じさせる。てのひらの上で転がしてみたくもあり、場をしつらえて鎮座させたくもなる。墓石にするには大きさや目が適さない石だからこそ発想された手元供養商品だが、このフォルムであることこそに重要な意味がある。製品化プロジェクトチームSMOWのメンバー各氏に話を聞いた。
NOWHERE(ナウヒア/静岡県沼津市)の榊原 亮氏と株式会社aim-design(アイムデザイン/静岡県富士宮市)代表取締役の望月 悟氏が、福島にある石材丁場を見学したことが企画立ち上げのきっかけとなった。掘り起こされた石材のうち、実際にお墓に使われるのは5〜7%。残りは埋め立てて廃棄される。墓石に長らく関わってきた榊原氏はこの現状を知っていたが、望月氏は石材の大半が無価値として廃棄されることに衝撃を受けた。
「石材が積まれている一画のすべてが墓石にできず価値がないものと言われたのですが、デザイナーの視点からは宝の山に見えた。デザインやブランディングによって、新たな価値を与えたいと思いました」(望月氏)
同時期に、空間デザインや企業ブランディング等に携わる株式会社design MEMORABLE(デザインメモラブル/静岡県富士市)の代表取締役小笠原清実氏から石材のプロダクトを作りたいと声がかかった。そこから、3社でプロジェクト会議が始まった。プロジェクトテーマ「石のある暮らし」=「Stone Made Our World」の頭文字からチームをSMOWと名付け、プロダクト製作に向け話し合いを重ねた。
時代に合致した墓標にしようという案は、榊原氏が出した。従来の手元供養のようにインテリアにマッチして、なおかつ、故人への思いを届けられる、本質を備えた、時代や暮らしにあった墓標にしたい。ならば手元供養ではなく、「てのひらぼせき」という新たなジャンルのお墓として世に送り出そうではないかという思いがあった。
チーム結成から2年をかけて完成した「てのひらぼせきIL」は、2023年11月に商品としてリリースされた。この墓石は、大人が両手を合わせるとその中にすっぽりと納まるサイズの丸みを帯びた形状で、内部に粉砕したお骨を納めることもできる。重さはおよそ300グラムと、ポケットに入れられるほどだ。

故人が今も「居る」から「IL」
このプロジェクトの過程では、デザインにいちばんこだわった。人が祈るときには、手を合わせる。その対象としてふさわしい形は何か。つまり、祈りの対象をデザイン化するということである。
デザイン案をスケッチブックやパソコン画面で描きながらディスカッションを重ねるうちに、祈りの対象の形ならば、それは「魂のカタチ」ではないか、と具体的なキーワードが上がった。もちろん、誰も見たことがないものである。そこでメンバーがそれぞれ、紙粘土を使って自分が考える「魂のカタチ」を作り、持ち寄った。何十種類も並んだ紙粘土模型をお互いに手に取り、てのひらに収めながら話し合い、形を整えていった。
墓石をしつらえる特別な場所だと意識できるよう、木製のシンプルな台座も付けた。だがあえて、花瓶や香炉といった仏具はセットしなかった。
「プロダクトデザインやインテリアデザインに携わる彼らと議論していくなかで、長く墓石に関わっていると、これまでの常識や習慣にとらわれてしまうことに気づかされました。私は添える仏具を魅力的にすることで価値を高めようという視点でしたが、デザイナーは、どこにでも置きやすくすることで、商品をお客様に育ててもらうという視点から発想していました。石という、それ自体は魅力的な素材を日常生活に取り入れるには、シンプルなほうがよいと気づきました」(榊原氏)
デザインが定まり、「IL」という商品名も決まった。故人が「居た」のではなく今もそばに「居る」というイメージを、手に取った人に感じてほしいという想いが込められている。ロゴデザインは、合わせた手と墓石をモチーフに、中央に空間を持たせて包み込む「祈りのカタチ」を表現した。