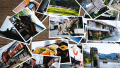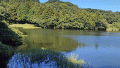健康に過ごすために重要なのが食事選び。健康的な食事は、栄養バランスや食事量などさまざまな点を考慮して選ぶ必要があります。そんな食事選びの最新の基準として登場したのが「DII」。健康維持に重要な指標とされているDIIとは何か、詳しく見ていきましょう。
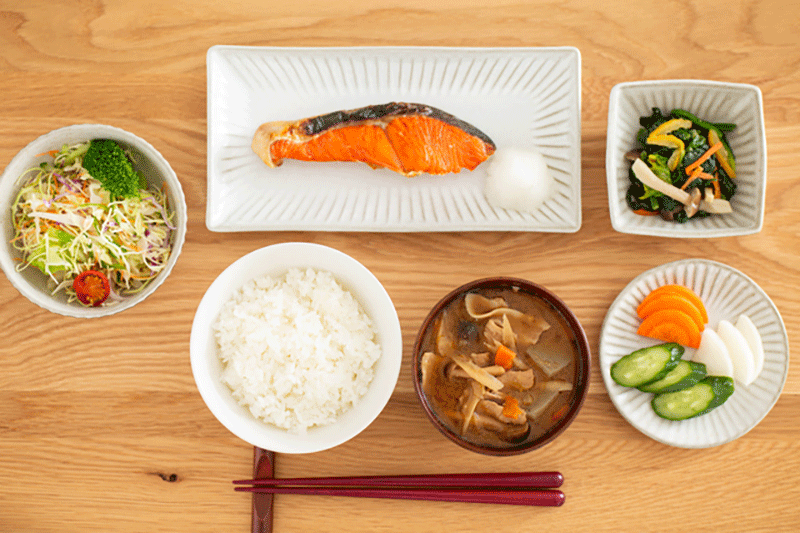
体内の炎症状態への影響を数値化した「DII」
米国サウスカロライナ大学の研究チームによって提唱された「DII」。日本語では「食事性炎症指数」と表記されます。「DII」が表すのは、体内の慢性的な炎症に関して、その食事が「炎症を抑える」効果があるのか、それとも「炎症を促進してしまう」効果があるのかということ。
「炎症」ときくと、喉が赤く腫れたり、熱を持って痛みがでたりするような症状を想像しますよね。目に見える急性の反応だけでなく、動脈硬化が「炎症細胞」によって悪化するように、生活習慣病にも炎症が大きな影響を与えていることがわかっています。
炎症を促進しやすいものを「高DII」、炎症を起こしにくかったり抑制したりするものを「低DII」と分類。低DIIの食品には、ニンニク・ショウガ・たまねぎ・緑茶・紅茶・ターメリック(ウコン)などがあります。反対に、コレステロール・中性脂肪・リン脂質・飽和脂肪酸・トランス脂肪酸などを含む食事が高DIIに。
実は食品だけでなく、栄養素も「高DIIな栄養素」と「低DIIな栄養素」に分類が可能。例えば炭水化物やタンパク質、パンやスナック菓子、揚げ物などの脂質を多く含むものは高DIIに分類されます。反対に、食物繊維を多く含む野菜やn-3系脂肪酸が豊富な魚類は低DIIに分類。食事に取り入れることで、炎症を抑える効果が期待できます。
現在、加齢による心身の衰えとDIIの関係性に関心が高まっています。国立長寿医療研究センター研究所は、40~59歳の女性を対象として調査をおこないました。その結果、高DIIの食事を取っていたグループの方が、低DIIの食事のグループよりも約12年後の握力低下が大きかったというデータもあり、加齢に伴う筋力低下にもDIIの影響があると考えられます。
健康的な生活を長く維持するための食事の基準として、DIIは今後私たちの生活にさらに浸透していくことでしょう。