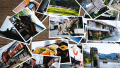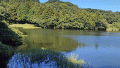言わずと知れた長寿大国・日本。2024年にWHOから発表されたランキングを見ると、日本の平均寿命は84.46歳と世界最長であることがわかります。長生きすることはもちろん大切ですが、「いつまで健康に過ごせるか」も重要ですよね。
その指標となるのが、「健康寿命」という概念です。健康寿命とは、介護などのケアを受けずに自立して生活できる期間を指す言葉。今回は、健康寿命に関する厚生労働省の調査結果から、健康寿命を伸ばすために意識すべきポイントをチェックしていきましょう。

健康寿命が最も長い都道府県は?
同じ日本国内でも、健康寿命は地域によって大きく異なります。厚生労働省は3年ごとに、全国20万世帯を対象として健康寿命の調査を実施。2024年末には、最新のデータとして2022年の調査結果が発表されました。
全国平均は女性が75.45歳、男性が72.57歳。2001年の調査開始時と比べると、女性で2.8歳、男性で3.17歳も延びています。さらに、平均寿命と健康寿命の差は女性が11.63歳、男性が8.49年と過去最短の結果に。「平均寿命と健康寿命の差」は“日常生活に制限のある期間”を示しているため、これが短縮されているのは良い傾向です。
都道府県別で見ると、最も健康寿命が長いのは静岡県でした。女性が76.68歳、男性が73.75歳と、男女ともに全国トップの結果です。一方で、健康寿命が最も短かったのは岩手県。女性が74.28歳、男性が70.93歳と全国平均を下回りました。脳や心臓の病気による死亡率が全国よりも高いことなどが原因として考えられています。
実は静岡県では、「運動」「食生活」「社会参加」を健康寿命の3要素として県民に周知していました。適度な運動を習慣化し、栄養バランスの取れた食事を心がけ、地域社会や趣味を通じて社会とつながることが、長く健康に生きるための鍵になります。当たり前の要素にも思えますが、高齢になっても意識し続けるのはなかなか難しいのかもしれません。
健康な老後を過ごすためにも、「健康寿命」を伸ばす取り組みは非常に大切です。健康寿命No.1の静岡県を見習い、「運動」「食生活」「社会参加」の3要素に取り組んでいきましょう。