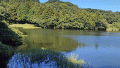野菜を茹でて調理すると、栄養がなくなってしまうというイメージを持っている人も多いかもしれません。しかし生の状態でカサがあるものをたっぷりと食べて栄養を摂取したい場合、“茹で”は効率的な調理法のひとつ。いくつかのポイントを意識すれば、素材の栄養をなるべく損なわないよう料理することも可能です。そこで今回は、栄養素をしっかりと摂取するために取り入れたい“茹で”調理の方法に注目しました。

食材によっては長時間の加熱がもったいないケースも
食材を茹でることによって流れ出てしまう恐れがあるのは、“水溶性”の栄養素。野菜などに多く含まれる「ビタミンC」をはじめ、「ビタミンB1」「ビタミンB2」「カリウム」といったものも水に溶け出しやすい性質を持っています。
さらにビタミンCの場合は、水溶性であることに加えて熱にも弱いのが特徴。そのためビタミンCを多く含んだ食材に長時間火を通すのは、栄養面からすると少しもったいないと言えるでしょう。
ビタミンCを含むほうれん草を例に挙げると、生のほうれん草を茹ではじめて1分経過しただけでビタミンCの残存率は74%ほどまでに低下。そして2分茹でた場合の残存率は61%になり、3分も茹でればもともと含まれていたビタミンCの半分以上が失われてしまいます。
一方で茹で時間を短くする工夫ができれば、ビタミンCが食材から大量に損なわれるのを防ぐことも可能。葉もの野菜であれば、お浸しなどサッと茹でるだけの料理にすると、加熱時間を1分程度に抑えられるのでおすすめです。
また茹でる際にお湯へ加える塩には、野菜の色味を綺麗な状態に保つ効果だけでなく茹で時間を短縮する効果も。塩を入れることで沸点が上がりお湯の温度もさらに上がるので、結果として加熱時間も短くなります。
なお“水溶性”の栄養素は茹でると消えるわけではなく、あくまで水に溶け出しているだけ。そのため茹で汁を別の料理に活用できれば、必要以上に栄養素を無駄にせずに済みます。特に加熱されても栄養価にあまり変化がない「水溶性食物繊維」を含む食材などは、スープ系の料理にするといった方法を取ればくまなく摂取できるでしょう。
工夫次第で食材の良さを効率良く堪能できる“茹で”調理。無理なく健康的な食生活を続けるためにも、積極的に取り入れてみてはいかがでしょうか。