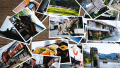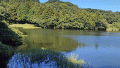高さ200m級の超高層ビルが立ち並ぶ東京の副都心・西新宿。淨音寺はそのビル街の一角にたたずむ小さな寺だ。外観は周囲に溶けこむコンクリート材のモダン建築だが、中に足を踏み入れると明るいヒノキづくりの本堂が広がる。30畳ほどの空間には、どこか懐かしい温もりがある。このお寺を預かる髙山一正住職は、死別の悲しみを癒すグリーフケアの活動に力を注ぐとともに、日本で数少ない節談説教の語り部としても活躍。双方の特徴・魅力を生かした独自の寺づくりを目指している。

再開発計画とともに本堂改装
淨音寺の歴史は、明治時代に始まる。明治40年頃、新潟県高田(現:上越市)から都市開教のために上京した髙山寒月住職(髙山一正・現住職の曽祖父)が「東京淀橋説教所」を設立。明治期の西新宿一帯は茶畑や桑畑が広がる土地だったため、東京淀橋説教所は「茶畑の説教所」として親しまれた。東京では、浄土真宗の説教所の草分け的な存在だったという。
同時期の1898(明治31)年12月、この地域に作られた「淀橋浄水場」は60年以上にわたって東京都内に水道水を供給していたが、戦後、1960(昭和35)年にできた東村山浄水場に機能を移転。あいた土地の再開発策として、1960年代後半から「新宿副都心」の建設計画が進み、1971(昭和46)年竣工の京王プラザホテルをはじめとして、超高層ビルが次々に建設された。
この副都心建設は、1991(平成2)年、当時は日本一の高層ビルであった高さ243mの東京都庁竣工とともに完成。大きく変貌する西新宿において、かつての東京淀橋説教所は淨音寺となって、地域に愛される寺として存続してきた。
都庁完成後も周辺地域の開発は進み、淨音寺がある成子地区(新宿区西新宿8丁目)もその対象となったため、淨音寺も本堂の再建築を余儀なくされた。現在の本堂が完成したのは2011年4月。建て直しに取り組んだのは、先代住職の髙山正克氏である。正克氏は淨音寺を、これまでの檀家(浄土真宗では「門徒」という)に限らず、誰にでも開かれたお寺、阿弥陀如来の教えをより広く伝え、この街に暮らす人・訪れる人に救いをもたらすお寺にしたいと願い、入りやすくシンプルな本堂をデザインした。

わずか24歳で住職に就任
1986(昭和61)年生まれの一正氏は父・正克氏について回想し、自身の子供時代・学生時代をこう振り返る。
「門徒の方には、この寺の息子・後継ぎという意味で『2代目さん』と呼ばれていました。暗黙のうちにこのお寺を継ぐことが決められているようで抵抗感がありました。しかし、父からは一度も継げとは言われなかったので、大学は理系(東京理科大)に進み、民間企業に就職しようと考えていたのです。
けれども私は、心のどこかで将来は住職になることを想定していたのでしょう。就職先を選ぶ際にもお寺を意識していて、仕事で得る経験をお寺に還元できないだろうか――そんなことを考えていたのです。そのことに気がついた時、『いずれそうするつもりなら』と考えを改め、寺の跡を継ぐ決心をしました。父に打ち明けたのは、本格的な就職活動が始まる大学3年の時です」
こうして一正氏は大学卒業後、22歳で築地本願寺(東京都中央区)にある東京仏教学院に2年間通学した。その間、父をサポートしていたが、父と一緒に活動できたのはわずか3年ほど。正克住職は、みずから設計した新しい淨音寺の完成を見ることなく、2011年初めに65歳で逝去。一正氏はわずか24歳で、父の遺志を受け継いで住職を務めることとなったのである。
今この時代において、小さなお寺を維持・発展させるには、多くの人に門戸を開き、仏教および宗派の思想を伝えるとともに、その寺ならではの情報・存在感を訴求する必要がある。そんなミッションを背負って若き住職は、奮闘の日々を送ることになる。

左が一正氏。右が先代の正克住職。
“グリーフケアのお寺”として門戸を開く
一正住職が死別などの悲しみ・喪失感を抱えた人に寄り添い、励ます「グリーフケア(グリーフサポート)」について詳しく知ったのは、先述の「未来の住職塾」で特別講師として招かれた尾角光美氏の話を聞いたからだ。グリーフサポートを広める活動に深い共感を覚えた一正住職は、尾角氏が代表を務める一般社団法人リヴオンの「いのちの学校」で詳細を学ぶ。
さらに「ファシリテーター養成講座」を受講し、一般社会とは異なる価値観・死生観を持つ宗教者だからこそできるグリーフケアがあるのではないか――住職はそうした考えに至った。そして、グリーフケアを淨音寺の活動の軸にしようと実践を始めた。
「うちでは年に数回、寺葬を行っていますが、そこではリヴオンで学んだ『大切な人をなくした人のための権利条約』についてお話しています。その後、ご法事の場でも繰り返しお話しするようにしています。『いつまでも大切な方は私たちを照らしてくださいます』と、関係性を紡ぎ続けることの大切さを伝えると、ご遺族の方が抱えている思いを吐露してくださるきっかけになるのです」
淨音寺では、公式サイトでもグリーフケアの大切さを訴え、寺葬を行った遺族に限らず、グリーフを抱えた人の相談にいつでも応じられるよう門戸を広げている。
また、一般的には「死別による悲しみ」と解釈されている「グリーフ」は、一正住職によれば失業や失恋、引っ越しなどのライフイベントによって人が抱える喪失感もすべて含まれるのだという。こうしてグリーフという概念を広くとらえ、心沈む人をサポートしていきたいと語る一正住職は、その一環としていくつもの試みを行っている。たとえば、訪れた人が思うままに本堂でピアノを弾くことができる「寺ピアノ」。生と死について気軽に語り合う「デスカフェ」の開催。こうした試みを重ねながら、お寺ならではのグリーフケアをしていきたいと、一正住職は語るのだ。

節談説教の説教師として活動する
グリーフケアに力を注ぐ一方で一正住職は、「節談説教」に心打たれ、チャレンジしたいと学び始めた。節談説教とは浄土真宗の宗祖である親鸞聖人が説いた念仏の教えを広めるために伝承されてきた、法話の一形態である。発祥の年代は定かでないが、親鸞聖人の死後、鎌倉時代後半から徐々に発展してきたと考えられている。
この独特の説教法は、仏教に馴染みのない民衆に対して、語りにドラマチックな抑揚をつけて伝えるもので、人々の感情に強く訴えかけるのが特徴だ。演題は「親鸞聖人御一代記」「蓮如上人御一代記」などが代表的だが、仏教説話、篤信の信者の言行録などバラエティ豊かで、娯楽が少なかった時代に広く人々に受け入れられたという。さらには、芸能的な色合いが濃いことから、江戸時代に花開いた落語、講談、浪曲など、日本独自の語り芸の母体ともなったのである。
戦後間もない頃までは、全国各地の寺を巡業する人気説教師もおり、今でいう「おっかけ」のような信者たちもついて回っていたという。しかし、伝説や物語から素材がとられたその内容には封建的・差別的な要素も強く、現代の価値観とは相容れない文化ではないかと、社会からも浄土真宗本山からも批判された。そのため一時期、説教師も激減し、絶滅の危機に瀕していた。
その価値が再び認められるようになったのは、昭和後期から。それまで批判的だった浄土真宗でも考えを変えて、語り継がれてきた伝統を守ろうと、2007年には「節談説教研究会」を設立。2年に1回、育成セミナーを開催している。
現在、節談説教を行う説教師は全国で100名あまりいるという。髙山一正住職はそのひとりとして、2017年、築地本願寺で開かれた「節談説教研究会結成10周年記念布教大会」に出仕。2023年には、淨音寺で関東大会を開き、熱演を聴かせたのだという。