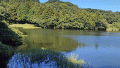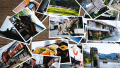健康を気にする人にとって大事なキーワードとなる「血糖値」。血糖値が「高い」ことが良くないということは有名ですが、「急に上げない」ことも重要です。また、血糖値は食事のとり方でも変化します。血糖値を上げすぎないための“食べ方”を見てみましょう。
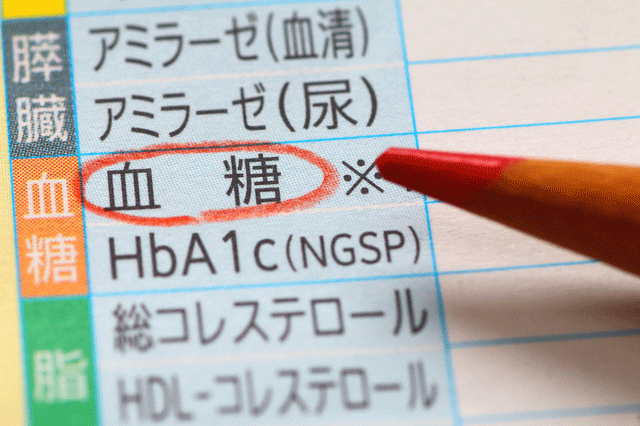
血糖値が引き起こす病気と防ぐための「食べ方」
そもそも「血糖値」とは、血液に含まれるブドウ糖の濃度のこと。食事に含まれる炭水化物が体内で消化・吸収され、ブドウ糖となり、体のエネルギーとなります。血液中にブドウ糖が増えすぎた高血糖の状態が続くと「糖尿病」に。血管の弾力性が失われ、血管が傷つくことで神経や腎臓に症状が表れ、脳卒中や心筋梗塞を引き起こすこともあります。
健康な人の血糖値は、「インスリン」というホルモンで一定の範囲内に管理されています。しかし、中には「食後に血糖値が急上昇する」という人も。常に高血糖状態の「糖尿病」とは異なるものの、「血糖値の急上昇」も血管のダメージになります。
そこで重要なのが、血糖値を「上げすぎない」食事方法。「ベジファースト」はご存じの方も多いでしょう。これはサラダなどの食物繊維が豊富なものを先に食べることで、その後の食事での糖の吸収が穏やかになり、血糖値の急上昇を防げるというものです。
また、血糖値がピークとなるのは食後1時間ほどですが、この「食後1時間」でお菓子などを食べると、糖質が追加されて血糖値のピークが長く続くことに。「食後のデザート」も含め、食事の間隔は「少なくとも2~3時間」あけることを基本にしたいですね。
デザートを食べる場合には「フルーツ系」がおすすめ。フルーツには「果糖」という糖分が含まれていますが、比較的血糖値が上昇しにくいと言われています。ただし果糖は中性脂肪に変わる性質があり、体重増加につながるので「量」には注意しましょう。
さらに、食べる「スピード」も血糖値に大きく影響します。「早食い」は腸に一気に糖分が運ばれて短時間で血糖値が上昇します。逆に「ダラダラ食い」も血糖値が高い状態が長く続くことに。適切なペースで食事をすることが大切です。
自分の血糖値は自覚できないものです。大きな病気につながる血管へのダメージを軽減するためにも、血糖値を上げすぎない“食べ方”を意識してみてはいかがでしょうか。