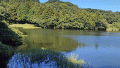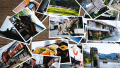群馬県前橋市の葬祭用灯籠の総合メーカー・株式会社太閣産業は、成長が早い竹を使った灯籠を作っているが、その一方で、LED電球ではなく白熱電球を使用せざるを得ないというジレンマも抱えているという。同社代表取締役社長の片平孝弘氏に、ご供養のあり方から考える、SDGsとの向き合い方について聞いた。

竹は“エコの優等生”
株式会社太閣産業が生産・販売している竹ひごを使った灯籠は、メーカーがSDGsにどう取り組むかについて、考えさせられる商品だ。
同社が竹ひごを使った灯籠を発売し始めたのは、今から20年以上も前のことになる。SDGs(Sustainable Development Goals/持続可能な開発目標)が国連で採択されたのは2015年なので、当然のことながら発売当初はSDGsという言葉すらなかった。だが、当時からすでに、竹材が“エコの優等生”であることは知られ始めていた。木は植林してから伐採して木材として使用できるまでに数十年かかるが、竹は自生していて植林の必要もなく、成長が早いので一度伐採しても3年から5年で再び伐採できる。あまりにも生命力が強いので、竹林を活用せずに放置すると周囲に根を張り、土砂崩れなどの災害を引き起こすほどの“竹害”をなすことすらある。竹の間伐材を活用することで、里山が守られるという面もあるのだ。持続可能な開発には最適な素材といえよう。
灯籠の素材として同社が竹を使い始めたのは、中国との取引の窓口となっている商社から、竹の産地である浙江省の工場を紹介されたためだ。日本の竹細工は工芸品のように専門職人の技術が頼りで、量産が難しい。そのため、従来のお盆用の灯籠では、あまり使われていない素材だった。代表取締役社長の片平孝弘氏も、商社に紹介されたときは、「本当に量産できる品質のものが作れるのだろうか」と疑心暗鬼だったという。だが、中国は竹の加工技術に長けており、竹の加工品が生活の一部となっている。予想を上回る生産技術があり、国内では数量的に生産体制を整えるのが難しかったため、紹介された中国の工場で竹を加工するところまでを行い、日本で塗装以降の工程を手がけることにした。
今、同社で生産している灯籠のうち、竹を使っているものは竹ひご状に加工してから成形した商品が多い。それというのも、竹を切って加工すると、風合いはよいが割れができやすくなり、太さもまちまちになってしまう。そこで、量産を実現するために、中国で竹ひごを半製品(素木)に組立て加工し、日本国内で塗装、配線加工等を行うことになったのだ。

右:路地行燈をヒントに誕生した「竹蘭(鉄仙)」
日本の生活になじむ竹細工
商品企画においては、片平氏がラフスケッチを描いている。竹細工の伝統工芸品を参照して、意匠に取り入れることもある。例えば、「竹蘭」や「竹彩」などの商品は、茶の湯(夜の茶会)で、茶室までの足元を照らすために使われる路地行燈が、現代化されて和風インテリア照明として使われていることをヒントに、灯籠の形状に取り入れた。
「今、竹の独特の風合いは見直されてきているのではないでしょうか」と片平氏は話す。
「竹細工の生活雑貨は、日本の生活のいろいろなところにあります。昔からあって今も親しまれているデザインは、長い時間の中で洗練されてきたものともいえます。ですから、少し現代風にアレンジするだけで生活になじむので、お客様に受け入れていただきやすいと感じています」(片平氏)
一方で、竹以外の素材では、なかなかエコ素材には切り替えにくい現実もある。スタンダードな三本足の灯籠は、プラスチック素材のほか桐材のものも発売しているが、桐材では価格が上がってしまうので、主流はやはりプラスチック素材だという。
ほかのエコ素材としては、約15年前、製紙会社との共同開発で、原料のうち紙が50%以上を占めるEペレットという素材を使い、試行錯誤して製品化してみたことがあった。しかし、外見がプラスチックのように見えてしまうため、エコ素材であることを訴求しがたく、今ひとつ販売が振るわなかった。室内の目立つところへ置く商品である以上、いかにエコ素材であっても、見た目で訴求できなければ、消費者の心を捉えるのは難しいともいえるだろう。
「価格は上がりますが、飽きのこない竹ひごや木製の灯籠で、少しでも長く使っていただきたいという思いはあります。葬儀だけでなくお盆でも使えることをアピールして、長い目線で選んでいただける努力もしていきたい」(片平氏)

右:塗りと白木の2つのデザインがある「つぼみ」(写真は白木)