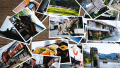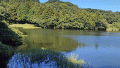仏教の形式で葬儀をおこなう時に必要な「戒名」。葬式で読経の際に読み上げられたり、位牌に刻まれる名前という漠然とした知識はあっても、詳しくは知らないという人も多いのではないでしょうか。一体戒名とは何なのか、戒名の意味やつける際のルールなどを解説します。
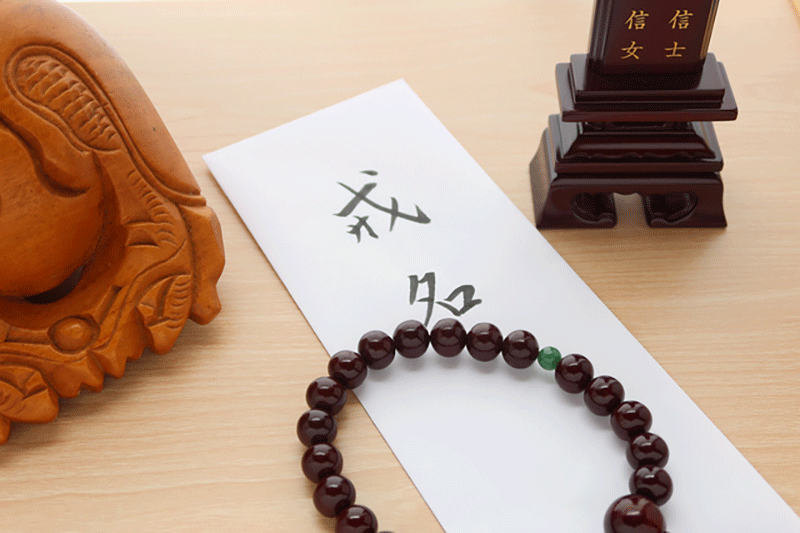
死後の名前としての「戒名」
仏教の世界において戒名とは、あの世における故人の“新しい名前”。仏の弟子となった証として授けられ、先祖代々の菩提寺がある場合はそのお寺の住職から授与されるのが一般的です。
戒名は4つの「号」で構成され、最高位の「院号・院殿号」は社会的貢献度の高い人物にのみ与えられます。院号や院殿号がない場合は「道号」が戒名の一番上に付き、生前の人柄や趣味、場所や住所に関連した2文字を当てますが、水子や幼児、未成年者には道号はつけません。
道号に続く「戒名」は漢字2文字で構成され、現世の本名から1文字を取るのが習わし。残りの1文字は故人の職業や尊敬する人物に関する文字などが使われます。ただし、何でも良いというわけではありません。天皇家に関する文字や年号、「病」「狂」など不吉なことを連想させる文字は使えないため注意が必要です。動物を表す文字も、一部の「吉兆」とされるもの以外は使用できません。最後は「位号」で、年齢や性別、社会や寺院への貢献度によって称号が変化します。
戒名の授与は無料ではなく、お布施となる「戒名料」が必要。各寺や宗派によって金額は異なりますが、およその相場があるので把握しておくと良いでしょう。ランクごとの戒名料は最も位の低い「信士」「信女」で30万円前後、最高ランクの「院居士」「院大姉」になると100万円ほどになることもあります。
戒名は死後に授けられるイメージがありますが、本来は生きている内に戒名を授かるのが一般的でした。現在も「生前戒名」として存命中に授かることは可能で、死後に授かるよりも戒名料が安くなるというメリットもあります。
戒名を授かるのにはお金がかかるため、近年では戒名を必要としない「無宗教葬」を選ぶ人も増えてきました。また、宗派のルールや構成を守っていれば戒名は自分でつけることもできます。ただし菩提寺がある場合は、事前に相談しておきましょう。