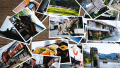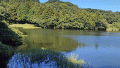骨がもろくなる「骨粗しょう症」は、加齢とともに誰にでも起こり得る病気です。特に自覚症状がないまま進行するため、骨折や転倒をきっかけに初めて気づくケースも少なくありません。そこで今回は、骨粗しょう症の仕組みと予防法について紹介します。
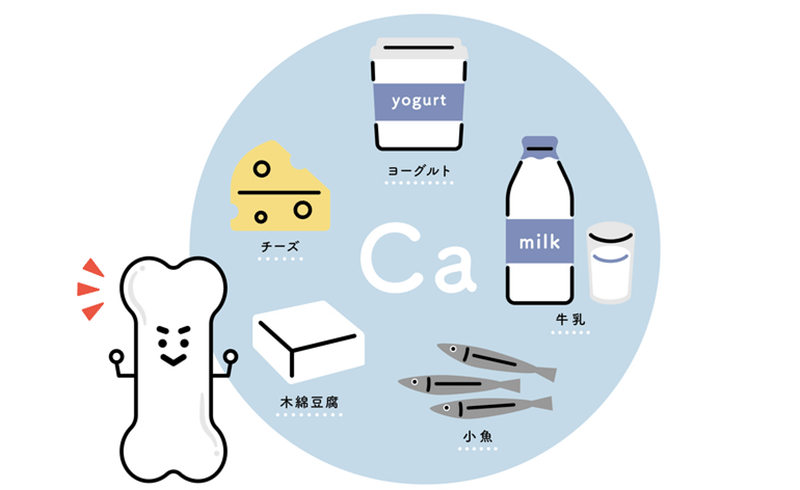
まずは骨密度のチェックから
骨粗しょう症とは、カルシウムやマグネシウムなどが不足することで骨密度が低下し、骨の内部がスカスカになる症状のこと。閉経後の女性に多いことと、進行しても痛みなどの明確な症状が出にくいのが特徴です。
早期発見のためには、定期的な骨密度検査を受けて状態を把握しておくことが大切。骨密度を測定する方法にはいくつか種類があります。骨密度検査で用いられるのは、腰椎などを高精度に測る「DXA法」、かかとに超音波を当てる「超音波法」、手の骨をX線で撮影する「MD法」など。目的や体の状態に合わせた測定方法を選べます。たとえば超音波法は放射線を使用しないため、妊婦でも安心して受けられるでしょう。
症状が進行すると、ちょっとした転倒や衝撃でも骨折する可能性が高まります。また、背骨が圧迫骨折を起こすと身長が縮んだり、背中が丸くなることも。
骨粗しょう症を予防するには、まず日々の食生活を見直すことが大切。カルシウムの摂取を意識するとともに、カルシウムの吸収を助けるビタミンDや、骨の質を高めるビタミンB6も一緒に摂るよう心がけましょう。バランスの取れた1日3食の食事が基本となります。また、日光に当たり体内でのビタミンDの合成を促すことも有効です。
さらに、適度な運動も予防に効果的。ウォーキングや軽いジョギングにダンベルを持って負荷を加えると、骨に適度な刺激が伝わり強化につながります。筋トレも骨への刺激になるため、無理のない範囲で続けるとよいでしょう。なお、水中ウォーキングは重力の負荷が軽減されるため、骨粗しょう症対策としては実はあまり推奨されていません。
骨折のリスクを軽減するためにも、早めに骨密度検査を受け、予防につながる生活習慣を取り入れていきたいですね。