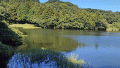いつも通りに始まった夫婦の朝。
ともに朝食を取り、休日だった夫はルーティンワークの家事を終えた後、毎週通っているジムに向かった。繰り返されてきた日常は、そのたった数時間後に崩れる。
10月24日に発売された書籍『見えない死神 原発不明がん、百六十日の記録』は、書評家の東えりか氏が、コロナ禍という特殊な状況下で遭遇したあまりにも理不尽な別離を綴る渾身のノンフィクション作品であり、心の準備をする間もなく死別に向き合わなければならなかった妻が悲嘆から回復していく軌跡を書き留めた記録でもある。
愛する夫の死をどのように受け止め、怒りや悲しみを乗り越えたのか。そして、体験を書籍という形で社会と分かち合おうと決心した理由とは。(文:門賀美央子)

東えりか(あづま・えりか)
書評家。千葉県生まれ。信州大学農学部卒。動物用医療器具関連会社の開発部に勤務の後、1985年より小説家・北方謙三氏の秘書を務め、2008年に書評家として独立。日本経済新聞、「週刊新潮」等で多数の連載を持つ。
近年、がんは「死の病」から「克服可能な病」へと大きく変化してきた。種類とステージにもよるが、治療法が確立しているがんでは最短1週間程度の入院で済むこともある。また、末期がんからの生還も、奇跡ではなく医療の成果として受け止められるようになってきた。
背景にあるのは、診断技術と治療法の飛躍的な進歩だ。PETやCTなど画像診断の精度向上により早期発見が可能となり、治療法の進化に加え、新薬の登場が患者の生存率を押し上げた。また、がんゲノム医療の発展により、その患者に合わせた「個別化医療」が実現している。
つまりがんは、昔と違い「絶望的な病気」ではないのだ。
しかし、依然として厄介ながんも残っている。ノンフィクション本を主な対象とする書評家・東えりかさんの夫である保雄氏を襲ったのが、まさにそういうがんのひとつである「原発不明がん」だった。
「がんになるのは怖いけれども、不治の病とまではいえない。私も夫もそういう認識でいました。特に夫は長年抗がん剤の開発に携わってきた人だったんです。ですから、がんの知識は専門医と同等程度はあったと思います。怖さを熟知する一方、早期発見できれば恐れるに足りないこともよくわかっていました」
病の性質を知り尽くしているから、毎年必ず人間ドックに行き、少しでも具合が悪ければ病院に行くほど健康には気を配っていたという。
「そんな人がある日、突然スポーツジムで激しい腹痛に襲われて入院、半年足らずで他界してしまったんです。入院後は原因がわからないまま約2カ月半が過ぎ、最終的にがんと判明した頃にはすでに体が満足に動かないほど悪化していました。最期は自宅で迎えましたが、発病から死去までたった160日ほどでした」
コロナ禍で対面わずか7度 やっとわかった「原発不明がん」
「発症するまでに食欲不振や体重減少は起こっていました。とはいえ、ある程度の年齢になってくると、誰でもちょっとした体調不良は抱えるものです。だから、本人も私も基本は元気だと思っていました。それなのに突然倒れて、原因がわからないまま3カ月も気を揉むわけですよね。本人はもちろん、コロナのせいで会えない私も余計につらかった」
そう、保雄氏の闘病期間は、ちょうどコロナ禍末期にあたっていたのだ。さらに、入院した病院で大規模な病棟の引っ越しがあったことなども重なり、緊急入院から退院までのおおよそ5カ月にわたって夫婦が直接対面できたのはわずか7度。LINEや電話などで日々連絡を取り合っていたとはいえ、双方の心細さはいかばかりだっただろう。保雄氏が入院してからがんと診断されるまで、約2カ月半の時間がかかっている。しかも、最後の最後までがんの中心となっている原発箇所がわからないままだったため、有効な治療方針も立てられないままだった。
もちろん病院側もただ手をこまねていたわけではない。検査でがん細胞が見つからないため、がん以外の病気の可能性についてはしらみ潰しに調べていた。しかし、原因を特定できないままいたずらに時は過ぎ、腹水からがん細胞らしきものが見つかった頃には、保雄氏はすでに立てなくなっていた。
原発不明がんは希少がんの一種に含まれるが、「希少がん」とは発症頻度が極めて低く、年間発症率が人口10万人あたり6例未満であるがんを指す。つまり、患者数が圧倒的に少ない。発生部位は多岐にわたり、個別には非常にまれながん種が約200種とも300種以上ともされるが、そのため診断法や治療法の確立が遅れやすく、臨床試験や医療体制が十分に整っているとはいえないのだ。残念ながら、希少がんを的確に診断し有効な治療につなげられる病院は、国内でもわずかしかない。
「最初に危篤状態になったのはがんの可能性を告げられてからたった1週間後のことです。こんなことが起こるなんて、呆然とするばかりでした。私は書評家ですから、罹患者がきわめて少ない奇病や今の医術では対処がむずかしい難病について書かれた本を山ほど読んでいます。でも、まさか自分と自分の夫にそんな病気が降りかかってくるとは思っていませんでした。それに保雄の闘病中はただただ目の前のことに忙殺されるばかりで、時には最悪のことも考えてしまいます。心に余裕なんてありません。私が夫の身になにが起こっていたのかを落ち着いて考えられるようになったのは、すべてが終わってしばらく経ってからのことです」
東保雄さんが罹患した「原発不明がん」とは?
がんがすでに他の臓器やリンパ節に転移しているにもかかわらず、どこに最初に発生したか(=原発巣)が検査を重ねても特定できないがんのこと。日本では年間約7000人が診断され、全がんの1〜5%を占める比較的まれな疾患とされる。診断にはCTやPETなどの画像検査、血液検査、病理検査などを総合して行い、原発巣を探す努力が続けられるが、1カ月を目安に治療を開始する方針がとられている。
原発不明がんは、リンパ節に限局する「リンパ節転移型」、肝臓や肺、骨などに広がる「臓器転移型」に大きく分けられ、さらに性別や病理所見によって細分類される。治療は原発巣が不明でも全身化学療法を主体に行われ、一部の予後良好群では局所療法や手術が選択されることもある。原発を特定できなくとも、個々の患者に最適な治療法を見いだすため、専門チームによる包括的診療が重要とされている。
思わず葬儀社に事前相談へ 叶えられた「人が集まる葬儀」
保雄氏の余命いくばくもないのが誰の目にも明らかになるにつれ、東さんの心は混乱していった。愛する夫がまもなく眼前からいなくなる。そんな予感を前に冷静でいられるはずがない。
だからだろうか。病院で抗がん剤治療の打ち切りを告げられた日、東さんは自分でも驚くような行動に出ていた。自宅近くの葬儀会社をひとり訪ねたのだ。
「なぜあの時あんなことをしたのか。保雄はまだ生きているし、がんばっている最中だったのに。死を前提にしたような行動を取ってしまったことについて、私は今も保雄に申し訳ない気持ちでいます。ただ、やっぱり取り乱していたのでしょう。打ち切りを言い渡された翌日、家の近所にある葬儀会館が目に入ると、私はそこにふらふら入っていきました。葬儀社の方は詳しいことは何も聞かずに、ただ必要なことだけを優しく丁寧に教えてくれました。そして、何かあった時には気軽に電話してくださいねと声をかけてくれました。今となってはなぜあのタイミングであのような行動に出たのか自分でもよくわからないのですが、もしかしたら、混乱する気持ちのまま、胸の内を吐露しに行ったのかもしれません。それに、死を避けられないのであれば、せめてお葬式だけはきちんと出したいという気持ちがどこかにあったんでしょうね」
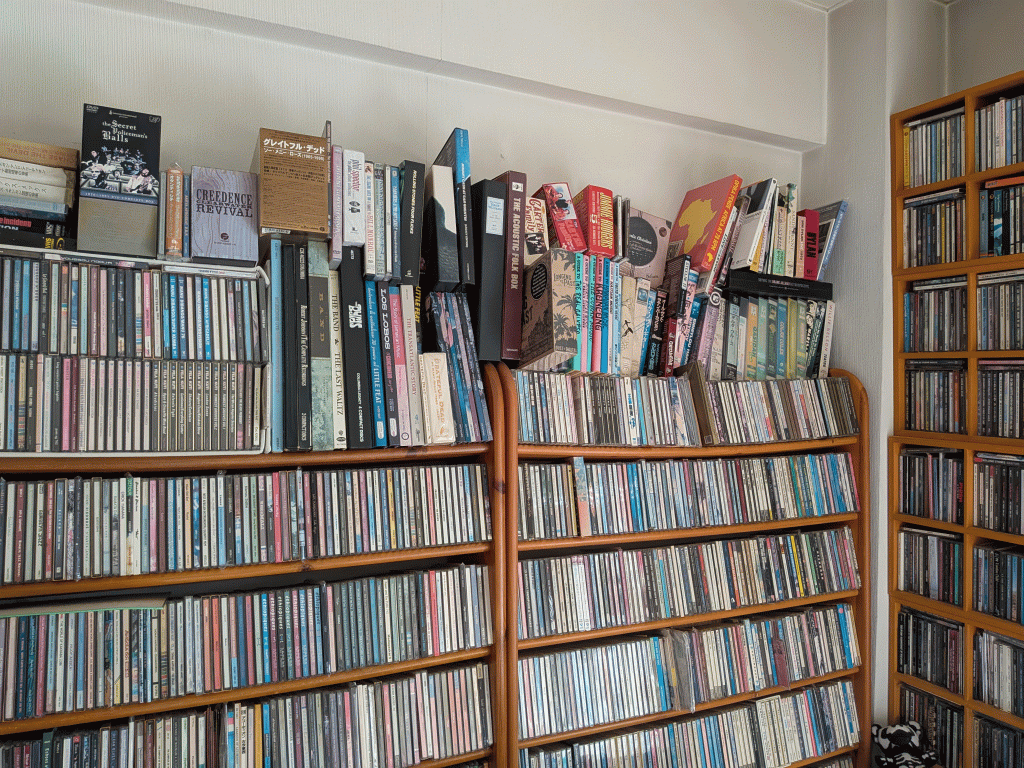

家族葬のようにごく内輪で済ませる式ではなく、友人・知人や仕事関係者にも来てもらう葬儀をしよう。それは保雄氏の病気が発覚する前から、夫婦の間でなんとなくできていた了解事項だったという。
そう考えるようになったきっかけはいくつかあった。
たとえば、ある文筆家のケース。その人に頼みたい仕事があり、仲立ちしてもらおうと担当編集者に連絡を取ったところ「何を言っているんですか。あの人はもう亡くなっていますよ」と言われて驚いたことがあった。よくよく考えると確かに遺族から喪中欠礼はがきの形で死去を知らされていた、ような気がする。しかし、いくら考えても訃報それ自体は記憶に残っていなかった。原因は、死に際して儀式や告知が一切行われなかったからとしか考えられない。死を家族で囲い込んでしまった結果、人ひとりの終焉が記憶に残らないものになってしまうことに、東さんは違和感を覚えたそうだ。
また、保雄氏死去の1年前に義母が亡くなった際の家族葬の経験も、その思いに輪をかけた。式は滞りなく行われたものの、寂しさは否めなかった。やはり友達ぐらいは呼びたかったよねと話しながら、自分たちの時にはやっぱり一般的な葬儀にしようという結論になっていたのだ。まさか、それがすぐに起こってしまうとは想像もしていなかったが。
だが、いくら受け入れられないとはいえ、余命宣告された事実は動かない。ひと月先か3カ月先かはわからないけれども、近々いなくってしまうのだ。その意識が自分を動かしたのではないかと東さんは言う。
「夫が死ぬ前に葬式の段取りをしようとしていたなんてちょっと人に言えないという気がしたし、保雄に対しても申し訳なさすぎますが、でもやはり心備えのひとつとしては悪いことではなかったと思います」
というのも没後、受け取っていた番号に電話をしたところ、すでに社内で情報が共有されていたらしく、すぐに家まで駆けつけてくれ、葬儀に関する一連の段取りもスムーズに行われたのだ。東さんの希望はしっかりと聞き届けられ、さらには有益な情報も得られたという。
たとえば、東さんが居住する自治体では公設の火葬場の混雑が長らく続いている。よって、順番が来るまでの数日、遺体の保管を委託しなければならないが、その委託料がばかにならない。ならば、多少費用は高くなっても早期に予約可能な火葬場を使うという手があると、気に触らないよう気遣いながら教えられた。
「結局、私は早く火葬する方を選びました。保雄はすごく体裁を気にする人だったので、自分の遺体がいつまでも留め置かれることをよく思わないだろう、と。多分、反対に私を見送ることになったとしても彼はそうしたでしょうね」
葬儀についても、生前相談していた通り、通夜と告別式をきちんと執り行う方式を選んだ。コロナ禍下とはいえ、2023年の3月にはマスクの着用も個人の裁量に任され、最盛期のような移動や会食の制限もなくなっていたからだ。
ひと昔前はごく当たり前だった形式――祭壇を飾って、導師を招き、参列者や有志からの供花もすべて受け入れた。来てくださる方はどなたでも、できるだけたくさん来てください、というスタンスをとった。最終的には通夜告別式合わせて300人ほどが参列した。

保雄さんの棺に入れた供花。本人の生前の希望にしたがい、色花を入れたという(東えりかさん提供)
「本当は通夜振る舞いもしたかったんです。でも、コロナ禍では従来のような大皿取り分けスタイルは取れず、ひとり一人前ずつ御膳を用意する形しかできないって言われて。でも、何人来るかわからないお通夜では数が読めないから、予約注文するのは無理です。それに、保雄は相当なグルメだったので、お仕着せの会席料理を参列者に出すなんて絶対許さないだろうと思いました。だから、葬儀場のすぐそばにある、2人でよく行っていたおいしいお店にお願いして、ちょっとした会食パーティーのような形にしました。そこにはおそらく70~80人ほどの方が来てくださったと思います。
保雄の知り合いには入院の事実をあまり知らせていなかったので、病気だったことも知らない方がほとんどでした。だから、一体何が起こっていたのかを知りたがる方も少なからずいました。夫の関係者は医療関係や薬品メーカーの人も多いので、みんな聞きたいわけですよ。だから、私の口からきちんと説明できたのはよかったと思います。また、保雄は私が出版業界の人間だというのをまったく話していなかったので、北方謙三さんや宮部みゆきさんといった作家のみなさんからの供花があったことに驚いていたみたいです。『え、どうしてそんな人たちから?』って」
悲しみの淵からの快復徐々に セラピー犬の助けも借りて
にぎやかな葬儀になった。だが、それが終わり、支えてくれた身内も帰っていくと、ひとりになった。
孤独と悲しみが襲ってきた。
「しばらくはやっぱりふさぎこんでいました。誰とも連絡を取りたくなくなっちゃって。母からかかってくる電話ぐらいは取りましたけど、ほかはまったく。でも、昔からの友人たちは心配してわざわざ訪ねてきて、世話を焼いてくれました。食事を持ってきてくれたり、心療内科にかかる段取りを眼の前で付けてくれたり。彼女たちの支えがなければ、ずっと自分の殻に閉じこもっていたでしょう。でも、ひと月ぐらい経つと、なんだか悲しむことにも疲れてしまった自分がいたんです。夫のことばかりを考えていても戻ってくるわけじゃないし、ちょっと外に出てみようと思って」
2023年は桜の開花後に冷え込む日が続き、4月を過ぎても東京はまだ花が残っていた。そこで、知人に声をかけたところ、1時間ぐらいなら時間が取れるからと散歩がてらの花見に付き合ってくれることになった。その知人もまた東さんの身を心配してくれていたひとりだっただが、会って話すうちに、実は自分も6年前にパートナーを亡くしていたと突然告白された。初耳だった。
また、東さんが習っているフラワーアレンジメントの講師も、夫に先立たれた体験を話してくれた。
その2人が口を揃えて言ったことがあった。仕事に戻ることが何よりの逃げ場になった。眼前の仕事が、もっとも深刻な時期のよきグリーフケアになったのだ、と。
経験者の助言に背を押され、東さんは仕事復帰を決意。その後、手記が書き上げられ、出版に至るまでの経緯についてはここで紹介するより本を読んでもらったほうがよいだろう。だが、このインタビューでは、グリーフケアに関して書籍には収められていない興味深いエピソードを聞くことができた。
「私を心配して連絡をくれた友人の中に温泉研究家の山崎まゆみさんという方がいるのですが、私が彼女にふと『グリーフケアになるような温泉があれば紹介して』と言ったんです。誰にも邪魔されず骨休めをしたいから、って。でも、彼女はグリーフケアという言葉を知りませんでした。そこでどういうものか説明すると、これから先は絶対それが必要になると言い始めたんですね。山崎さんは長らく全国の温泉宿の女将さんたちと一緒に新しい温泉滞在の形を模索しているのですが、グリーフケアのための温泉滞在プランは検討の価値がある、と思ったようです」
また、こちらは書籍でも言及されているが、心療内科クリニックで受けたアニマルセラピーは確かに効果があったという。
「心理カウンセラーをしている友人が、12キロも痩せるほどの状態だった私を見て『とにかく専門医に行け』と心療内科を紹介してくれたのですが、そこの先生というのが実はアニマルセラピーを日本に初めて導入した先生だったんです。だから、クリニックにもセラピー犬がいたんですよ。セラピー犬は、待合室で座っていた私を見るなりまっすぐ向かってきて、横にちょこんと座って離れなくなりました。当時、私は自分では普通にしているつもりですが、犬にはそうでないのがすぐにわかったのでしょうね。この子の存在は、何よりも私の心を和らげてくれました」

少しずつとはいえ、元の生活を取り戻すよう努力していった。それが功を奏したのだろう。秋が深まる頃にはようやく気分が楽になり始めた。しかし、それでもなお「なぜ夫を助けられなかったのか」というとてつもない後悔だけは消えない。
最初の病院で起こったいくつものアクシデントと診断の遅さが、命を縮める原因になったのではないか。転院先の医師には前の病院で医療過誤を疑わせるような部分はなかったと説明を受けたものの、それは本当なのか。どうあっても、納得できない。強い疑念が執筆への道に東さんを追い立てた。
『見えない死神 原発不明がん、百六十日の記録』には、このような一節がある。
いまなら冷静に、もう一度、彼の死因となった原発不明がんという希少がんが、なんであったのかを調べることができるのではないか。彼の無念を理解できるのではないだろうか。
保雄が倒れてから、ジェットコースターのような闘病の日々が続き、ふたりとも冷静に対処する余裕がなかったのは事実だ。なぜ彼がこんな病気にかかってしまったのか、助かる方法はなかったのか、もしほかの人が同じ病気になったら、私に何かアドバイスできることはないだろうか。(228頁)
「いざ書こうと決めると、まずは保雄に起こったことをきちんと整理し、確認する作業から始めました。もともと北方謙三さんの秘書をやっていたので書籍執筆に必要な段取りは熟知しています。また、独力で解決できそうにないことはその手段を知る人に相談するという知恵もある。私は自分が持つあらゆる伝手をたどって、必要と思う人たちに会い、話を聞いていきました。でも、私と同じような事態に直面しながらも、自分で調べたりする手段を持たない人の方が多いはずです。だったら、単なる体験記で終わらせず、広く分かち合うべき情報を取り入れるべきだと思ったんです」
希少がんセンターとの出会い 患者会の存在を周知したい
前述の通り、保雄氏がかかった「原発不明がん」は希少がんに含まれる。そのため、東さんの調査は希少がんそのものの実態にも及んだ。その過程で知ったのが、国立がん研究センター中央病院内の「希少がんセンター」の存在だった。取材を進めていくうちに東さんには希少がんセンターが、あらゆる災厄の後に希望だけが残ったというギリシア神話の「パンドラの箱」のように感じられたという。センター内にある希少がんホットラインには患者とその家族を支えるための組織があったからだ。
「患者会の存在です。希少がんにかかる人は当然ながら数が多くありません。だから、孤独に陥りやすい。それは家族や遺族も同様です。でも、希少がんセンターには患者会があって、同じような境遇の人たちとつながることができる。また、遺族へのケアもある。つまり、新たな望みや慰めを得ることができるかもしれないんです。保雄が亡くなった2023年頃には、希少がんセンターは東京の国立がんセンターにしかありませんでした。それが今では全国7カ所に広がっています。また、希少がんホットラインの開設も進められています。
ところが、公的機関であるせいか、どうもこうした組織があることをうまく発信できていない。しなきゃいけないのはみんなわかっているけれど、どうしていいかわからないんですね。だから、周知の一端を担えればいいと思って本書でも取り上げたのですが、当然それだけでは足りません。もっと幅広く、効率的に情報が伝わる仕組みがないといけない。
たとえば、がん保険の相談窓口のように患者とダイレクトにつながる場は、希少がんセンターの存在を知ってもらうにはちょうどいいじゃないですか。また、遺族に関しては葬儀会社がセンターを紹介する窓口になってくれたら、私と同じような後悔を抱える人たちのグリーフケアを広げられるのではないかと思います。そういう仕組みを作っていくお手伝いができないか、今考えているところです」
「希少がん」啓発のために設立 「日本希少がん患者会ネットワーク」
一般社団法人日本希少がん患者会ネットワーク(RCJ)とは、患者数が少ないために診療体制や研究が遅れがちな「希少がん」の現状を改善するべく、2017年に設立された支援団体。
患者や家族が尊厳を保ち安心して暮らせる社会を目指し、医療・政策・情報発信・国際交流などの多角的活動を展開。がん治療の最新情報を届けるがん情報サイトの運営のほか、臨床試験への参加促進を目的とした「希少がんコミュニティーオープンデー」の開催や、患者会・支援団体のネットワーク構築、医療関係者や製薬企業との連携による政策提言を実施している。
また患者・家族間の交流を支えるオンライン掲示板「ラクーン(Rare Cancers Community On the Net)」を運営し、希少がんに関する実態調査や啓発活動を通じて、診断・治療・研究の遅れを克服するための基盤づくりにも力を注いでいる。

哀しみを整理するための営為として始まった取材は、希少がんの患者とその家族、そして遺族のための情報収集と拡散という新しいステージに入ろうとしている。「グリーフ」の解消は単なる癒やしに留まらず、人生を次の場に導く原動力になるのかもしれない。東さんの活動は「ケア」のその先を見せてくれているのではないだろうか。(了)
【東えりか氏の著作】
『見えない死神 原発不明がん、百六十日の記録』 集英社/2200円(税込)
原因不明の激しい腹痛から始まった謎の病気。入院から3カ月後に告げられた病名は「原発不明がん」だった。発症から夫が亡くなるまでの約160日間の記録、そして起こった出来事の真実に迫ったノンフィクション。第22回開高健ノンフィクション賞最終候補作。
『見えない死神』イベント告知
東えりかさんの『見えない死神 原発不明がん、百六十日の記録』の刊行を記念して、12月20日(土)に大阪の隆祥館書店でトークイベントを開催します。ゲストは大阪大学名誉教授の仲野徹さん。詳細は以下のURLよりご確認ください。