『四谷怪談』のお岩様を縁結びの神様に。怨霊のイメージを払拭し、現代に生きる人々の心を支える「祈願の寺」に生まれ変わった陽運寺。住職の植松健郎氏は、荒行を成し遂げた修法師として、人々の悩みを聞き、神仏に祈りを捧げる。祈祷を経済の柱とする新しいスタイルの寺は、女性向けの華やいだ演出と丁寧なサービス・情報発信で若者を中心に人気を集めている。
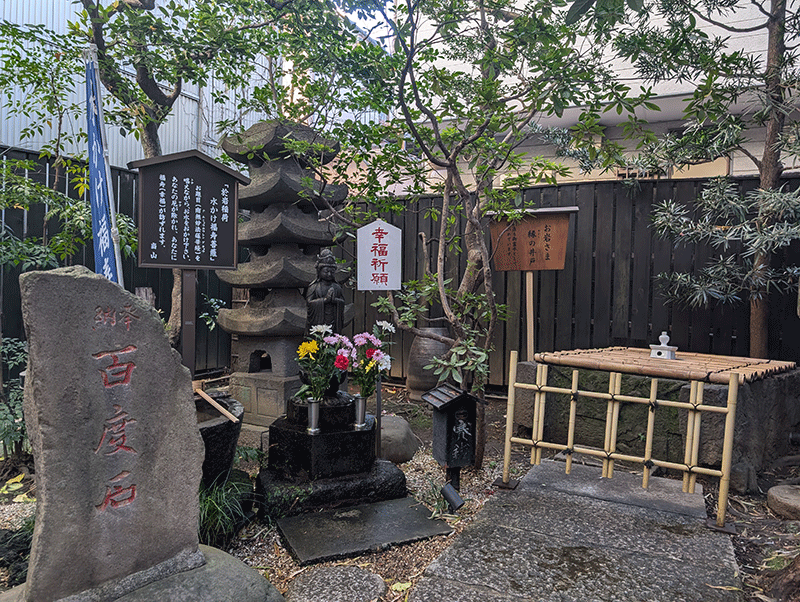
境内の一角で水かけ福寿菩薩と並ぶ「お岩様縁の井戸」は神秘的なイメージを醸し出している
副都心・新宿に近い四谷。この地名を聞くと、『四谷怪談』を連想する人も多いだろう。しかし、現在の四谷は怪談のイメージとはかけ離れた、賑やかな商業施設や落ち着いた住宅街が広がる街だ。そんな四谷の一角にある陽運寺は、「お岩様」を祀る縁結びの寺として、多くの人々の信仰を集めている。
お岩様といえば、顔がただれ、目が腫れ上がった恐ろしい幽霊の姿を思い浮かべるかもしれない。これは、江戸時代後期の戯作者・鶴屋南北(四代目)が手がけた歌舞伎『東海道四谷怪談』の登場人物像によるものだ。しかし、史実におけるお岩様は、徳川家の御家人の娘であり、夫・伊右衛門との仲も良く、才気にあふれた女性だったと伝えられている。彼女は家を繁栄させ、良妻賢母として周囲から慕われていたという。その評判から、彼女の死後「お岩稲荷」という神社が建立され、時代を経て陽運寺へと受け継がれた。現在では、お岩様の本来の姿に立ち返り、縁結びや開運を願う人々が訪れる寺として親しまれている。
「修法師」として陽運寺再建の担い手に
現在、陽運寺の住職を務める植松健郎氏は、もともと練馬区の在家で生まれ育った。大学生の頃、父が陽運寺の住職に就任したことをきっかけに、この寺を訪れるようになったという。当時の陽運寺は、境内全体が鬱蒼とした樹木に覆われ、昼間でも薄暗い雰囲気だった。『四谷怪談』のお岩様を祀る寺として知られていたが、まさに怪談の舞台を思わせるような佇まいだったという。
ある日、植松氏が境内の掃除をしていたところ、前の通りを歩く親子連れの姿が目に入った。幼い子供は、寺の前を通るのが怖いと泣き出し、母親は困った様子で子を抱きかかえ、門前を足早に通り過ぎていった。その光景を目の当たりにし「このままではいけない。この寺を人々に愛される場所へと再生したい」という思いが植松氏の胸に宿った。
大学卒業後、僧籍を得た植松氏は、陽運寺の副住職となり、日蓮宗の大荒行堂で修行に励んだ。荒行堂とは、毎冬100日間にわたり、1日2回の食事と2時間半ほどの睡眠時間しか取らず、それ以外は1日7回の水行と読経を続ける過酷な修行である。実は彼が僧侶の道を選んだのも、この修行に挑戦したかったからだという。そして、荒行を成満し、霊験を高めたことで「修しゅほっし法師」の資格を得ると、いよいよ本格的に寺族とともに陽運寺の再建に乗り出したのだった。
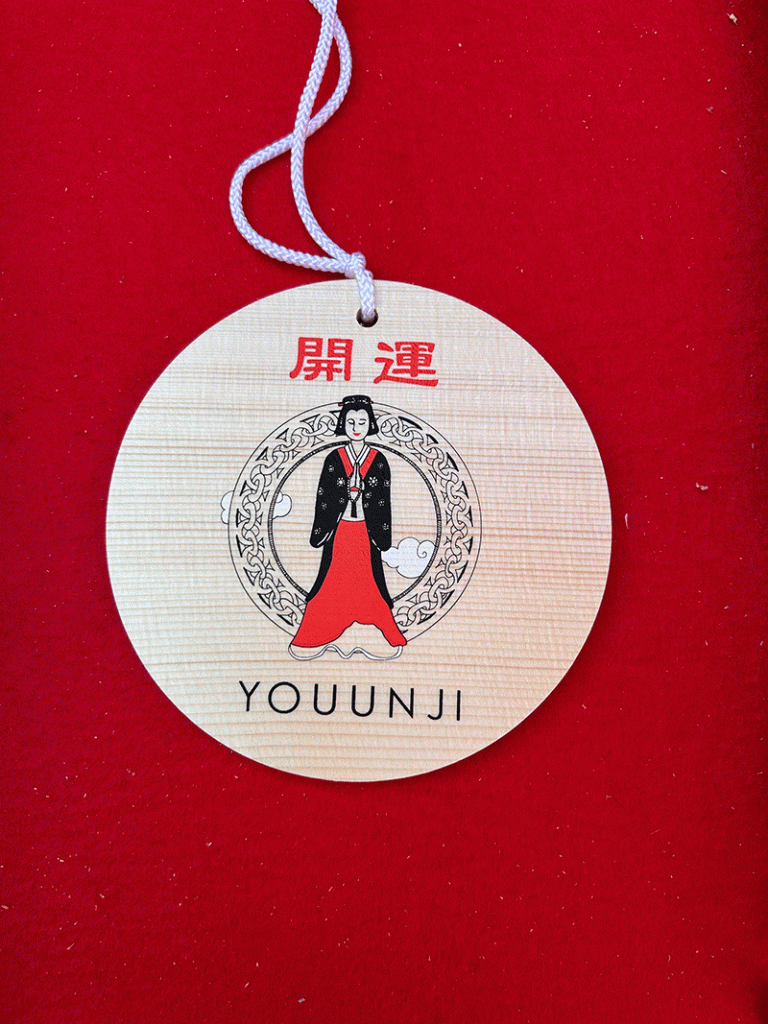
お守り
現代によみがえる理想の女性 お岩様
「修法師」がいて祈祷を行う――それは寺としての大きな強みだが、植松住職はそれだけでは人を呼ぶには不十分だと考えた。そこで、『四谷怪談』によって広まった怨霊のイメージを払拭し、本来のお岩様が持つ、賢く幸福な女性像を再び世に伝えることを目指した。その陽運寺再建事業の心強い支えとなったのが、妻だった。女性ならではの視点を取り入れることで、より多くの人が訪れやすい寺になると考えたのだ。植松住職は当時を振り返り、こう語る。「妻とは荒行堂での修行を終えた後に出会いました。それから、お岩様の伝承を活かしてどのような寺にしていくべきか、若い二人で試行錯誤を重ねていったのです」
まずは絵が得意だった住職の妻が、お岩様の絵を絵馬として制作。それに合わせて住職自身が日曜大工で絵馬掛けを作る。こうした具体的なモノづくりと、新しい寺のコンセプトづくりを同時に進めていった。
そうするうちに、お岩様の〝夫婦円満〟の側面に注目し、「縁結び」をメインコンセプトに据えた寺として打ち出すことを思いついた。一人でも訪れやすい雰囲気をつくり、これまで寺社に馴染みのなかった若い女性たちにも関心を持ってもらう。その女性たちが友人や恋人を誘い、自然と寺の門をくぐる人が増えていく。このようにして、陽運寺は伝統を大切にしながらも、時代に即した新しい形の寺院へと生まれ変わった。

女性客をもてなす空間デザインが施された庭では、四季折々の情緒を楽しめる
身も心もリフレッシュ お寺を都会の「温泉旅館」に
陽運寺が目指すのは、温泉旅館のように人々が心身の疲れを癒し、元気を取り戻せる場所だ。植松健郎住職は、「お湯に浸かる代わりに、神仏に手を合わせることで、気持ちが軽くなり、前向きになれる空間をつくりたい」と考え、境内を整備。入り口には暖簾をかけ、境内にはカフェを併設し、女性が親しみやすいデザインのグッズを充実させた。
また、訪れた人がSNSでシェアしやすいように、写真映えを意識したアイテムを揃え、情報発信の中心をインスタグラムに据えた。ホームページも洗練されたデザインに刷新し、参拝者が知りたい情報をわかりやすく整理。こうした工夫が功を奏し、取材当日も、平日にもかかわらず、20代から50代の女性グループが次々と訪れ、お参りや散策を楽しんでいた。
陽運寺は、こうした〝癒し〟の要素と並行して、〝祈願・祈祷〟を重視した新たな寺院のあり方を模索している。植松住職は修法師としての資格を持ち、毎月さまざまな祈願祭を開催。「月例お岩さま開運祈願祭」では法話や瞑想を行い、「祈りの日」では運勢や気学の話を交えながら厄除けや方位除けを行う。また、個別の相談に応じた特別祈願や、遠方の参拝者向けの代行祈願も提供。これらの祈願はホームページに詳細なメニューとして掲載され、利用者が選びやすい仕組みになっている。
経済的な面でも、陽運寺は従来の寺院とは異なる運営方法を取り入れている。収入の柱は、祈願・祈祷料をはじめ、お守りやご朱印、お土産などの物販、そして賽銭。檀家制度は持たず、葬儀や法事も行わない。昨年から今年春にかけての本堂の屋根修繕も、信徒や一般からの奉納金で賄われた。「訪れる人が心を癒し、願いを託し、また来たいと思える場所」として、陽運寺は伝統と現代的な感覚を融合させた新たな寺院の姿を築きつつある。
心のケアができる 僧侶が求められる時代
こうした新しいスタイルの成功は、現代の人々がお寺に何を求めているのかを示している。悩みを抱えた人々がカウンセラーではなく、僧侶のもとを訪れるのはなぜなのか。植松住職はこう語る。
「それは、お坊さんなら神仏に祈ることができるからです。話を聞くだけなら誰にでもできますし、それで気持ちが晴れる人もいるでしょう。でも、そうではない人が大勢います。悩みを抱える人の多くは、目に見えない力の存在を求めています。神仏の力や先祖の霊に感謝しながら、どう生きるべきかを伝え、祈りとともに導くことができるのは僧侶だからです。だからこそ、寺離れが進んでいると言われる今、私たち僧侶の役割はますます重要になっているのではないでしょうか」
2006年にわずか数人の参加者で始まった合同祈願祭は、現在では月3回開催され、100人近くが参加するまでに成長した。個人祈願も20代から50代の人々を中心に申し込みが相次ぎ、住職のスケジュールは常に埋まっているという。
お岩様の物語と、それに基づくコンセプトワーク。そして住職の特技を活かした心のケア。四谷怪談ゆかりの小さな寺には、新しい時代の寺づくりのヒントとなる、大きな可能性が秘められている。






